※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
ワーママとして仕事と家庭の両立に励む中で、自身の体調不良により退職という選択肢が頭をよぎることは、決して珍しいことではありません。
これまでのキャリアが退職でもったいないと感じたり、退職後の生活に漠然とした不安を覚えたりするのは、とても自然な感情です。
本当に体調不良で退職すべきか、そしてワーママの辞めどきはいつなのか、答えの出ない問いに悩む方も多いでしょう。
退職後に後悔しないだろうかという心配と、一方で心身の負担から解放されて辞めてよかったと思える未来を期待する気持ちが交錯し、決断できずにいるかもしれません。
この記事では、そんなあなたの悩みに寄り添い、客観的な情報に基づいて後悔のない選択をするためのヒントを多角的に解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。
記事のポイント
- ワーママが退職を考えるべき心身のサインやタイミング
- 退職後の後悔や生活への不安を具体的に解消する方法
- 会社とトラブルにならず円満に退職するための具体的な手順
- 退職後のキャリアを前向きに捉え、次のステップへ進むヒント
ワーママが体調不良で退職を考えるときの判断基準

ワーキングマザーが体調の不調を理由に退職を考え始めるとき、そこには様々な葛藤や不安が伴います。
キャリアを中断することへの抵抗感や、経済的な心配から、なかなか決断できない方も少なくありません。
ここでは、退職を本格的に検討すべきタイミングや、その際に生じる感情との向き合い方について解説します。
- ワーママの辞めどきはいつ訪れる?
- 本当に体調不良で退職すべき?
- キャリアが退職でもったいないと感じる
- 退職後の生活に対する漠然とした不安
- もし退職したら後悔するかも…
- 休職という選択肢も視野に入れる

特に体調崩した時は『もう無理かも…』って何回思ったことか。
でも、うちの場合は幸いにも乗り切れたんだけど、もしあの時に辞めてたらって思うと、ちょっとゾッとするわ。
でもね、無理は禁物ってホント思う。自分の体と心、一番大事にしなきゃダメだよね!
ワーママの辞めどきはいつ訪れる?
ワーキングマザーが退職を考える「辞めどき」は、特定のタイミングで突然訪れるというより、複数の要因が重なった結果として意識されることが多いです。
例えば、子どもの頻繁な体調不良や保育園からの急な呼び出しが続き、仕事に集中できない状況は大きな要因となります。
また、慢性的な寝不足や疲労が蓄積し、心身の健康が明らかに保てなくなったときも、働き方を見直すべきサインと考えられます。
加えて、子どもの成長に伴う環境の変化も無視できません。
特に「3歳の壁」と呼ばれる、時短勤務が終了したり、保育園の環境が変わったりする時期は、仕事との両立が格段に難しくなることがあります。
希望していたキャリア形成が困難になる「マミートラック」に陥ったと感じたときや、会社の待遇変化によって働きがいを失ったときも、自身のキャリアを考え直すきっかけになるでしょう。
これらの出来事が複合的に重なり、仕事と育児の両立が物理的にも精神的にも限界に達したときが、一つの「辞めどき」と言えるのかもしれません。
本当に体調不良で退職すべき?

体調不良を理由に退職すべきかどうかは、その症状の深刻さや回復の見込みによって判断が分かれます。
まず、現在の体調不良が仕事の継続を困難にするほど深刻である場合、退職は正当な選択肢となります。
民法第628条では、「やむを得ない事由」があれば雇用期間の定めがあっても契約を解除できるとされており、自身の健康を損なってまで働き続ける義務はありません。
医師の診断を判断材料にする
客観的な判断材料として、医師の診断書は非常に有効です。
医師から「療養が必要」「現在の業務を続けるのは困難」といった診断を受けた場合、それは退職を決断する上で強力な根拠となります。
診断書があれば、会社側も状況を理解しやすく、退職手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
一方で、症状が一時的なものであり、休養によって回復が見込める場合は、すぐに退職を選ぶのではなく、後述する「休職」という選択肢を検討することも大切です。
自身の体調を第一に考え、専門家である医師の意見を参考にしながら、冷静に判断することが求められます。
キャリアが退職でもったいないと感じる
長年築き上げてきたキャリアが、退職によって途絶えてしまうことにもったいなさを感じるのは、当然の心理です。
特に、やりがいのある仕事や責任ある立場を任されている場合、その気持ちは一層強くなることでしょう。
しかし、ここで一度立ち止まって考えてみてください。
心身の健康を損なってしまっては、そのキャリアを継続すること自体が難しくなります。
無理を重ねて働き続けた結果、症状が悪化し、復帰までにさらに長い時間を要してしまう可能性も否定できません。
また、キャリアの捉え方を変えてみることも一つの方法です。
一度退職したとしても、それはキャリアの終わりを意味するわけではありません。
療養期間を、今後のキャリアプランを見つめ直したり、新しいスキルを身につけたりするための充電期間と捉えることもできます。
健康を取り戻し、改めて自分に合った働き方でキャリアを再開することは、長期的に見ればより豊かな職業人生につながるかもしれません。
退職後の生活に対する漠然とした不安

退職を決断する上で大きな障壁となるのが、経済的な不安や社会との繋がりが絶たれてしまうことへの不安です。
特に、住宅ローンや子どもの教育費など、固定の支出がある家庭では、収入が途絶えることへの心配は深刻です。
この不安を軽減するためには、事前の準備が鍵となります。
まず、退職後の家計を具体的にシミュレーションしてみましょう。
現在の貯蓄額を確認し、失業保険や配偶者の収入でどの程度の期間生活できるのかを把握するだけでも、漠然とした不安はかなり解消されます。
また、社会との孤立感に対する不安については、意識的に外部との接点を持つことが有効です。
地域のコミュニティや子育てサークルに参加したり、興味のある分野のオンラインセミナーを受講したりと、社会との関わりを保つ方法は数多く存在します。
退職を「孤立」と捉えるのではなく、新しいコミュニティに参加する「機会」と捉えることで、前向きな気持ちを維持しやすくなるでしょう。
もし退職したら後悔するかも…
「退職」という大きな決断を前に、「もし辞めたら後悔するのではないか」という恐れを抱くのは自然なことです。
特に、職場の人間関係が良好であったり、仕事内容に満足していたりする場合、その気持ちは強くなります。
後悔の可能性を減らすためには、退職以外の選択肢を十分に検討したかどうかが重要になります。
例えば、上司に相談して業務量を調整してもらうことはできなかったか、部署の異動を願い出ることはできなかったか、時短勤務の期間を延長することはできなかったか、といった点です。
これらの選択肢をすべて検討し、それでもなお退職が最善の道であると判断したのであれば、その決断に自信を持つことができます。
また、「辞める」か「辞めないか」の二者択一で考えるのではなく、「今は一旦休む」という選択肢を持つことも、後悔を避ける上で有効です。
次の項目で解説する休職制度の活用は、そのための具体的な手段となります。
休職という選択肢も視野に入れる

体調不良を理由に退職を考える際、すぐに辞めるという決断を下す前に、休職制度を利用できないか確認することをおすすめします。
休職は、会社に在籍したまま一定期間休みを取り、療養に専念できる制度です。
休職の最大のメリットは、復職の道が残されている点です。
療養によって体調が回復すれば、元の職場に戻ることができます。
また、休職期間中は、健康保険から傷病手当金が支給される場合があります。
これは、給与のおおよそ3分の2が最長で1年6ヶ月間支給される制度で、療養中の経済的な不安を大きく和らげてくれます。
退職してしまうと、当然ながら給与は途絶え、失業保険の給付を受けることになりますが、自己都合退職の場合は給付までに待機期間があります。
その点、傷病手当金は経済的な安定を保ちながら療養に専念できる有効な手段です。
まずは自社の就業規則を確認し、休職制度の有無や条件を調べてみましょう。
退職という不可逆的な選択をする前に、一度立ち止まって検討する価値は十分にあります。
| 比較項目 | 休職(傷病手当金を利用) | 退職(失業保険を利用) |
|---|---|---|
| 在籍状況 | 会社に在籍 | 会社を退職 |
| 収入の目安 | 給与のおおよそ2/3(最長1年6ヶ月) | 離職前賃金の50~80%(給付日数は年齢・雇用保険加入期間による) |
| 社会保険 | 継続(保険料の自己負担は発生) | 国民健康保険・国民年金に切り替え(または配偶者の扶養に入る) |
| 復職の可能性 | あり(原則として元の職場へ復帰) | なし(転職活動が必要) |
| 主な手続き | 会社への休職届、医師の診断書、傷病手当金申請 | 会社への退職届、ハローワークでの失業保険申請 |
-

ワーママの睡眠時間、平均は?睡眠不足を解消する工夫
続きを見る
ワーママが体調不良での退職を円満に進める方法

退職を決意した後、次に考えるべきは「どのようにして円満に退職するか」です。
特に体調が万全でない中での手続きは、精神的にも負担がかかります。
ここでは、会社とのトラブルを避け、スムーズに退職手続きを進めるための具体的な方法や、退職後のキャリアを前向きに考えるためのポイントを解説します。
- 辞めてよかったと思える退職の進め方
- 診断書で退職の意思を明確に伝える
- 退職理由の上手な伝え方と例文
- 転職活動を有利に進めるポイント

私も派遣だけど、もし辞めるってなったら、やっぱり円満に、気持ちよく終わりたいなって思うもん。
特に体調不良が理由なら、周りに心配かけずにスムーズに進めたいよね。
こういう時こそ、冷静に、でも自分の気持ちに正直に、ってのが大事かな。
次のステップに進むためにも、終わりよければすべてよし!って感じでいきたいよね。
辞めてよかったと思える退職の進め方
最終的に「辞めてよかった」と感じられる退職にするためには、計画的かつ誠実な対応が不可欠です。
感情的に「もう行きたくない」と無断欠勤やバックレ(無断退職)をしてしまうのは、最も避けるべき行動です。
これは社会人としての信頼を失うだけでなく、会社から損害賠償請求をされるリスクも伴います。
まずは、会社の就業規則を確認し、退職の申し出をすべき期限(例:退職希望日の1ヶ月前など)を把握しましょう。
法律上は2週間前の申し出で退職可能ですが、円満退職を目指すなら、引き継ぎ期間を考慮して会社のルールに従うのが賢明です。
お世話になった上司や同僚への挨拶も、気持ちよく次のステップに進むためには大切です。
直接会うのが難しい場合は、メールや電話で感謝の気持ちを伝えるだけでも印象は大きく異なります。
最後まで責任ある行動を心がけることが、結果的に自分自身の心の整理にも繋がり、「辞めてよかった」という納得感を得るための鍵となります。
診断書で退職の意思を明確に伝える
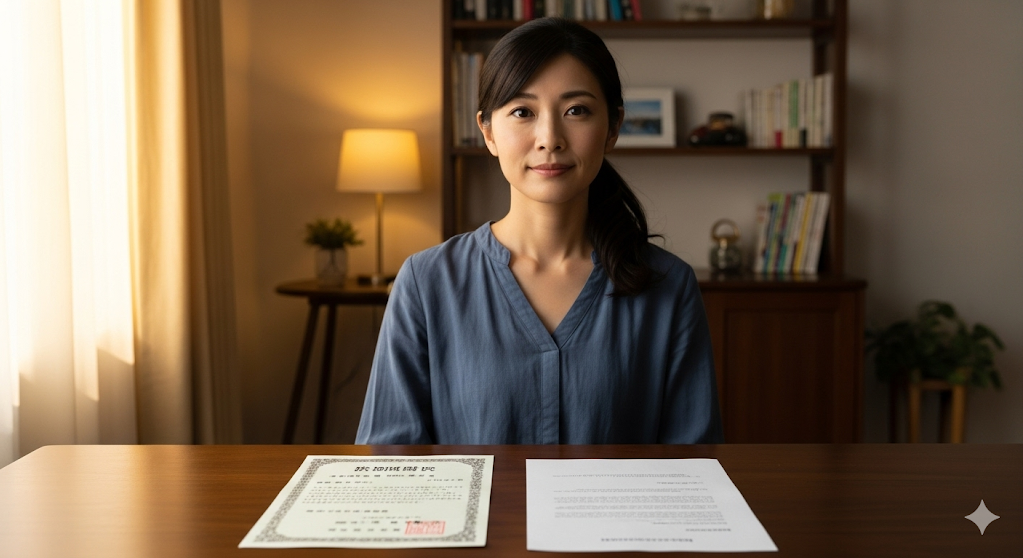
前述の通り、体調不良で退職する場合、医師の診断書は必須ではありません。
しかし、退職の意思を客観的に裏付け、交渉をスムーズに進めるための強力なツールとなります。
特に、会社側から強い引き止めにあった場合や、退職をなかなか認めてもらえない状況では、診断書の有無が大きく影響します。
診断書を提出することで、「個人の都合」ではなく「医師の判断に基づくやむを得ない退職」であることを明確に示すことが可能です。
これにより、会社側も無理な引き止めはしにくくなります。
また、有給休暇の消化を申請する際にも、診断書があると「体調不良のため出社が困難であり、有給休暇を取得して療養したい」という主張が通りやすくなるでしょう。
退職の意思が固いこと、そしてその理由が正当であることを示すために、可能であれば医師に相談し、診断書を取得しておくことを推奨します。
退職理由の上手な伝え方と例文
退職の意向を伝える際は、たとえ会社への不満が原因であったとしても、ネガティブな表現は避けるのがマナーです。
体調不良が直接的な原因であるため、その事実を正直に、かつ簡潔に伝えるのが最も良い方法と言えます。
伝える相手は、まず直属の上司です。
電話やメールで伝えることになりますが、体調が許すのであれば、声で直接伝えられる電話の方が誠意は伝わりやすいかもしれません。
電話で伝える場合の例文
「お忙しいところ恐縮です。〇〇です。以前から体調が優れずお休みをいただいておりましたが、医師と相談した結果、治療に専念するため、退職させていただきたくご連絡いたしました。本来であれば直接お伺いすべきところ、お電話でのご連絡となり申し訳ございません。」
メールで伝える場合の例文
件名:退職のご相談(〇〇部 〇〇)
「〇〇部長
お疲れ様です。〇〇です。
長期にわたり休暇をいただき、ご迷惑をおかけしております。
誠に勝手ながら、一身上の都合により、〇月〇日をもちまして退職させていただきたく、ご連絡いたしました。
体調の回復に努めてまいりましたが、医師からも当面の治療に専念すべきとの診断を受け、退職を決意した次第です。
本来、直接お伺いしお伝えすべき重要な事柄を、メールでのご連絡となりますことをお許しください。
後日、改めて退職届を郵送させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。」
ポイントは、「治療に専念するため」という前向きな理由を伝え、会社への感謝と、直接伝えられないことへのお詫びを添えることです。
転職活動を有利に進めるポイント

退職後、体調が回復し、再び働く意欲が湧いてきたら、次のキャリアに向けた転職活動を始めることになります。
ブランクがあることや、子育てとの両立を懸念されるのではないかと不安に思うかもしれませんが、準備次第で有利に進めることは可能です。
まず、自身の強みやスキルの棚卸しを丁寧に行いましょう。
前職でどのような経験を積み、どのような貢献ができたのかを具体的に言語化しておくことが大切です。
面接で退職理由を聞かれた際は、正直に体調不良であったことを伝えて問題ありません。
重要なのは、その後に「現在は完治しており、業務に支障がない」こと、そして「体調管理のために心がけていること」をセットで伝えることです。
これにより、採用担当者の不安を払拭できます。
また、一人で活動するのが不安な場合は、転職エージェントの活用が非常に有効です。
ワーキングマザーの転職支援に強いエージェントであれば、時短勤務や在宅勤務など、柔軟な働き方ができる求人を紹介してくれます。
職務経歴書の添削や面接対策も行ってくれるため、安心して転職活動に臨むことができるでしょう。
-

ワーママのフルリモート転職|後悔しないためのコツと注意点
続きを見る
ワーママが体調不良で退職する前に考えたいこと

もし、仕事や家庭のことで一人で悩みを抱え、心身の不調を感じている場合は、専門の相談窓口を利用することも一つの方法です。
厚生労働省が運営する下記のサイトでは、電話やSNSでの相談先を見つけることができます。
ワーキングマザーが体調不良を理由に退職を考えることは、自身のキャリアや家族の将来に関わる大きな決断です。
後悔のない選択をするために、この記事で解説したポイントを改めて整理し、冷静に状況を見つめ直してみてください。
ま と め
- 体調不良での退職は法的に認められた労働者の権利である
- ワーママの「辞めどき」は育児、仕事、健康のバランスが崩れた時
- キャリアがもったいないと感じるのは自然な感情だが健康が最優先
- 退職後の経済的な不安は事前のシミュレーションで軽減できる
- 退職を後悔しないために休職など他の選択肢も十分に検討する
- 休職制度と傷病手当金は療養と経済的安定を両立させる有効な手段
- 退職を決めたら会社の就業規則に従い計画的に手続きを進める
- 無断欠勤や突然の退職は避け、最後まで誠実な対応を心がける
- 医師の診断書は円満退職のための客観的な証明として役立つ
- 退職理由は「治療への専念」など前向きな表現で伝える
- 電話やメールで伝える際は感謝とお詫びの言葉を添える
- 退職後の転職活動では体調が万全であることを明確に伝える
- 転職エージェントの活用はブランクのあるワーママにとって心強い味方
- 何よりも自身の心と体の健康を第一に判断する
- 一人で抱え込まず、家族や専門家など信頼できる人に相談する

