※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
仕事に家事、そして育児と、毎日目まぐるしい日々を送るワーキングマザー(ワーママ)の皆さん、本当にお疲れさまです。
「自分の睡眠時間は足りているのだろうか」と、ふと不安になることはありませんか。
この記事では、「ワーママの睡眠時間」というテーマに焦点を当てています。
例えば、他のワーママの平均的な起床時間は何時なのか、多くの人が悩む睡眠時間が4時間というのは現実としてどうなのか、といった疑問に答えていきます。
また、そもそも6時間寝たら十分ですか?という根本的な問いや、理想とされるワーママが8時間睡眠を確保するための具体的なヒントまで、幅広く掘り下げて解説します。
この記事を読み終える頃には、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、心と体を守るための具体的な一歩を踏み出せるはずです。
記事のポイント
- ワーママの平均的な睡眠時間と起床時間の実態
- 睡眠不足が心身に与える具体的な影響
- 睡眠時間を確保するための実践的な工夫やアイデア
- 睡眠の質を向上させるための具体的な方法
ワーママの睡眠時間、その厳しい実態

- ワーママの平均的な起床時間は?
- ワーママの睡眠時間が4時間という現実
- 6時間寝たら十分ですか?専門家の見解
- 睡眠不足が招く心身への健康リスク
- 日本の働く母親は世界一寝ていない?

私も今でこそ平均6時間は寝てるけど、当時は4時間睡眠とかザラだったし…。
この記事読んで「わかる〜!」ってなってるママ、多いんじゃないかな。
ワーママの平均的な起床時間は?
多くのワーママにとって、朝は一日の中で最も忙しい時間帯の一つです。
そのため、ワーママの平均的な起床時間は、一般的に朝6時台が最も多いと考えられます。
ある調査では、半数以上のワーママが6時台に起きているという結果も報告されています。
なぜなら、子どもが起きる前に朝食やお弁当の準備、洗濯といった家事を済ませ、保育園に送る準備などを効率良く進める必要があるからです。
もちろん、これはあくまで一つの傾向であり、起床時間は家庭の状況によってさまざまです。
例えば、より早くから自分の時間や仕事の準備をしたい方は5時台に起床することもありますし、パートナーの出勤時間や子どもの登園時間に合わせて7時台に起きる方もいます。
いずれにしても、多くのワーママが限られた時間の中で、家族のために朝早くから活動を開始しているのが実情です。
ワーママの睡眠時間が4時間という現実

残念ながら、ワーママの睡眠時間が4時間、あるいはそれ以下というケースは決して珍しいことではありません。
特に、子どもの年齢が低い時期、とりわけ新生児期から生後3ヶ月頃までは、夜間の授乳や夜泣きの対応で、まとまった睡眠をとることが極めて困難になります。
このような状況では、睡眠が細切れになり、合計の睡眠時間が4時間に満たない日も続きます。
調査によっては、0歳児を育てる母親の約6割が、1日の睡眠時間が4時間以下であるというデータも存在します。
もちろん、子どもが成長するにつれて状況は少しずつ改善される傾向にありますが、仕事の繁忙期や子どもの体調不良などが重なると、再び深刻な睡眠不足に陥ることもあります。
このように、多くのワーママが日常的に過酷な睡眠状況と隣り合わせで生活しているという現実を、まずは認識することが大切です。
6時間寝たら十分ですか?専門家の見解
「最低でも6時間は寝ているから大丈夫」と考えている方もいるかもしれませんが、6時間睡眠が十分かどうかは個人差があるものの、一般的には不十分であるとされています。
厚生労働省が発表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、成人に推奨される睡眠時間は6時間以上とされていますが、これはあくまで最低ラインです。
多くの専門家は、日中の活動レベルや健康状態を最適に保つためには、7時間から9時間の睡眠が理想的だと指摘しています。
6時間睡眠が慢性化すると、自分では気づかないうちに集中力や判断力、作業効率が低下する「睡眠負債」という状態に陥る可能性があります。
これは、日中のパフォーマンス低下だけでなく、長期的にはさまざまな健康リスクを高めることにも繋がりかねません。
したがって、6時間という数字に安心するのではなく、ご自身の体調や日中の眠気を一つのサインとして、最適な睡眠時間を探ることが求められます。
睡眠不足が招く心身への健康リスク

前述の通り、慢性的な睡眠不足は、単なる日中の眠気だけでなく、心身に多岐にわたる深刻なリスクをもたらす可能性があります。
具体的にどのような影響が考えられるのか、下の表にまとめました。
| リスクのカテゴリ | 具体的な影響の内容 |
|---|---|
| 認知機能・生産性の低下 | 集中力、記憶力、判断力が低下し、仕事でのミスや家事の効率ダウンに繋がります。車の運転など、危険を伴う作業でのリスクも高まります。 |
| 精神的な不調 | 睡眠時間が5時間を切ると、うつ病や適応障害といったメンタル不調のリスクが顕著に増加すると指摘されています。イライラしやすくなり、子どもやパートナーとの関係に影響が出ることもあります。 |
| 生活習慣病のリスク増大 | 睡眠不足は食欲をコントロールするホルモンバランスを乱し、過食に繋がりやすくなります。結果として、肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めることが分かっています。 |
| 免疫力の低下 | 睡眠中に分泌される物質には、体の免疫機能を維持する働きがあります。睡眠が不足すると免疫力が低下し、風邪や感染症にかかりやすくなります。 |
このように、睡眠不足はワーママ自身の健康を脅かすだけでなく、仕事や家庭生活全体の質にも大きく影響を及ぼします。
自分と家族を守るためにも、睡眠不足のリスクを軽視しないことが大切です。
日本の働く母親は世界一寝ていない?
日本のワーママが置かれている睡眠環境の厳しさを示すデータとして、国際比較調査の結果が挙げられます。
経済協力開発機構(OECD)の調査によると、加盟国の中で日本人の平均睡眠時間は最も短く、特に男性よりも女性の方が短い傾向にあります。
この背景には、日本特有の社会構造が関係していると考えられます。
共働き世帯が増加している一方で、家事や育児の負担が依然として女性に偏りがちな現状があります。
総務省の社会生活基本調査のデータを見ても、有業の女性は男性に比べて、家事や育児といった無償労働に費やす時間が約6.7倍にもなるという結果が出ています。
つまり、仕事という有償労働に加えて、膨大な無償労働を担っているため、結果として睡眠時間を削らざるを得ない状況に追い込まれているのです。
この事実は、日本のワーママの睡眠問題が、個人の努力だけで解決できる範囲を超えた、社会全体で向き合うべき課題であることを示唆しています。
-
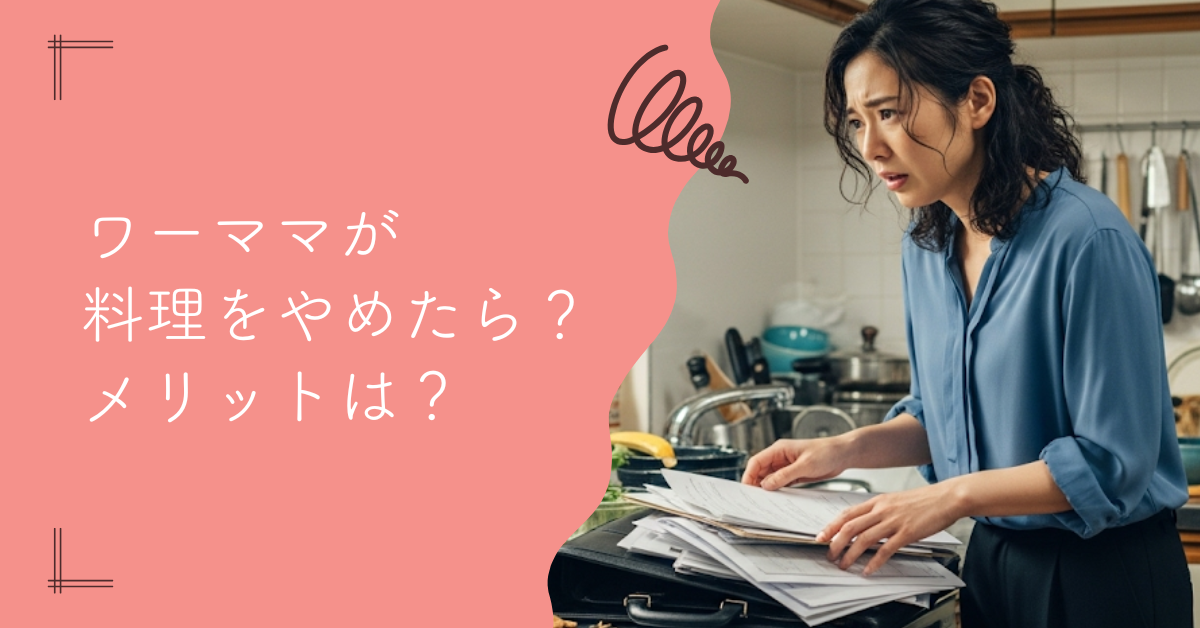
ワーママが料理をやめたら?メリット・デメリットと後悔しない方法
続きを見る
ワーママが睡眠時間を確保するための工夫

- ワーママが8時間睡眠を目指すには
- 朝型にシフトして夜の時間を確保する
- 家事の時間を削減する具体的なアイデア
- 睡眠の質を高めるための環境づくり
- 外部サービスを上手に活用する方法

家電に頼ったり、たまには手を抜いたり。
無理しないのが長く続けるコツ!
ワーママが8時間睡眠を目指すには
多くのワーママにとって、8時間睡眠を確保することは、非現実的な目標に感じられるかもしれません。
しかし、諦める前に、まずはその実現を阻んでいる要因を整理し、考え方を変えることから始めてみてはいかがでしょうか。
ワーママが8時間睡眠を目指すための第一歩は、「すべてを完璧にこなす」という考えを手放すことです。
家事も育児も仕事も100点を目指していては、時間がいくらあっても足りません。
まずは自分の中で「絶対に譲れないこと」と「手を抜いても良いこと」の優先順位を明確にすることが鍵となります。
例えば、「子どもとの時間は最優先するが、部屋の掃除は週末にまとめて行う」「夕食は品数を減らしても、栄養バランスは考える」といったように、自分なりの基準を設けるのです。
完璧主義の呪縛から解放されることで、心に余裕が生まれ、睡眠時間を確保するという選択肢が見えてくるようになります。
この後のセクションで、そのための具体的な方法を詳しく解説していきます。
朝型にシフトして夜の時間を確保する

睡眠時間を確保するための有効な手段の一つが、生活リズムを「夜型」から「朝型」へシフトさせることです。
夜に溜まった家事を片付けてから寝ようとすると、就寝時間がどんどん遅くなってしまいます。
そこで、思い切って子どもの寝かしつけと一緒に自分も寝てしまい、その分、翌朝少し早く起きるというスタイルに切り替えるのです。
朝の時間は、誰にも邪魔されない貴重な自分時間にもなり得ます。
朝型シフトのメリット
朝型に切り替えることで、いくつかのメリットが期待できます。
まず、夜に子どもと一緒に寝ることで、まとまった睡眠時間を確保しやすくなります。
また、静かな朝の時間帯は集中力が高まりやすく、夜にだらだらと行うよりも効率的に家事や仕事の準備を進められることがあります。
例えば、夕食の下ごしらえや洗濯などを朝のうちに済ませておけば、帰宅後の負担が大幅に軽減され、夜の時間をゆったりと過ごせるようになります。
無理なく移行するための注意点
ただし、急に生活リズムを変えるのは難しいものです。
まずはいつもより15分早く起きることから始めるなど、少しずつ体を慣らしていくことが大切です。
また、朝早く起きるためには、夜早く寝ることが大前提となります。
夜更かしの原因となるスマートフォンの使用を控えるなど、入眠環境を整える工夫も同時に行いましょう。
家事の時間を削減する具体的なアイデア
睡眠時間を確保するためには、日々の家事に費やす時間をいかに削減するかが大きなポイントとなります。
幸い、現代には家事の負担を軽減してくれる便利なツールやサービスが数多く存在します。
時短家電を積極的に導入する
「三種の神器」とも呼ばれる、食器洗い乾燥機、ドラム式洗濯乾燥機、ロボット掃除機は、ワーママの強力な味方です。
これらの家電を導入することで、食器を洗う時間、洗濯物を干して取り込む時間、床を掃除する時間といった、これまで当たり前だと思っていた家事の工程を大幅に自動化できます。
初期費用はかかりますが、「時間をお金で買う」という発想で、長期的な視点で導入を検討する価値は十分にあります。
食事の準備を効率化する
毎日の食事の準備は、特に負担の大きい家事の一つです。
週末に1週間分の献立を考えて常備菜を作っておく「作り置き」は、平日の調理時間を大きく短縮してくれます。
また、カット済みの食材と調味料がセットになった「ミールキット」や、栄養バランスの取れた食事を届けてくれる「宅配サービス」なども積極的に活用しましょう。
スーパーでの買い物時間を減らすために、ネットスーパーや食材宅配を利用するのも有効な手段です。
睡眠の質を高めるための環境づくり

確保できる睡眠時間が限られているからこそ、その「質」を高めることが非常に大切になります。
短い時間でも深く眠ることができれば、心身の回復度は大きく変わってきます。
就寝前のリラックスタイムを習慣に
質の高い睡眠のためには、心身を「お休みモード」に切り替える準備時間が必要です。
就寝1〜2時間前には、ぬるめのお湯にゆっくり浸かる、好きな香りのアロマを焚く、ヒーリング音楽を聴く、軽いストレッチをするといった、自分がリラックスできる方法を見つけましょう。
逆に、脳を興奮させてしまうスマートフォンやパソコンの強い光は、就寝前には見ないように心がけることが安眠への近道です。
快適な寝室環境を整える
寝室の環境も睡眠の質を左右する重要な要素です。
温度や湿度は、自分が快適だと感じるレベルにエアコンなどで調整します。
光が気になる場合は、遮光カーテンを利用するのも良いでしょう。
また、意外と見落としがちなのが寝具です。
自分に合わない枕やマットレスを使い続けていると、熟睡を妨げる原因になります。
体に合った寝具を選ぶことで、睡眠の質は格段に向上する可能性があります。
外部サービスを上手に活用する方法
「全てを自分でやらなければならない」という考えは、時に自分自身を追い詰めてしまいます。
睡眠時間を確保するためには、家事や育児を外部のプロに頼るという選択肢も積極的に検討しましょう。
家事代行やベビーシッターの利用
掃除や料理などを専門のスタッフに依頼できる家事代行サービスは、家事の負担を劇的に減らしてくれます。
週に1回、あるいは月に数回利用するだけでも、心の余裕が大きく変わるはずです。
また、子どもの預け先として、ベビーシッターの利用も有効です。
信頼できるシッターに子どもを預けて、自分一人の時間を作り、仮眠をとったり、リフレッシュしたりすることは、明日への活力に繋がります。
一時預かり保育などの公的・民間サービス
自治体が運営する一時預かり保育やファミリー・サポート・センターは、比較的安価に利用できる心強い味方です。
最近では、親が休息を取ることを目的とした、睡眠ブース付きの一時預かり施設なども登場しています。
こうしたサービスを利用することに罪悪感を覚える必要は全くありません。
むしろ、親が心身ともに健康であることが、子どもにとって最も良い影響を与えるということを忘れないでください。
-

ワーママの土日家事で終わる問題を解決するヒント
続きを見る
理想的なワーママの睡眠時間を考える

ま と め
- ワーママの平均起床時間は多くの場合で朝6時台
- 睡眠時間が4時間以下のワーママも決して少なくないのが現実
- 個人差はあるものの一般的に6時間睡眠では不十分とされる
- 専門家は成人に7時間から9時間の睡眠を推奨している
- 慢性的な睡眠不足は集中力や判断力の低下を招く
- イライラや気分の落ち込みなど精神的な不調にも繋がる
- 肥満や生活習慣病など身体的な健康リスクも高まる
- 日本のワーママの睡眠時間は国際的に見ても短い水準
- 背景には女性に偏りがちな家事や育児の負担がある
- 8時間睡眠を目指すには完璧主義を手放すことが第一歩
- 生活リズムを朝型にシフトすることも有効な手段
- 時短家電やミールキットで家事の時間を積極的に削減する
- 確保できる時間が短くても睡眠の質を高める工夫が大切
- 就寝前のリラックスタイムや快適な寝室環境を整える
- 家事代行や一時預かりなど外部サービスを上手に頼る

