※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
パートを始めたい、あるいは勤務時間を増やしたいと考えている主婦の方にとって、「平均でどれくらい稼げるの?」「働きすぎて損をすることはない?」といった疑問は尽きないものです。
主婦のパートにおける平均年収や平均月収は一体いくらなのでしょうか。
また、よく耳にする「年収の壁」について正しく理解し、パートでいくら稼ぐのが得なのかを知ることは、失敗や後悔をしない働き方を考える上で非常に大切です。
この記事では、主婦パートの平均時給や平均時間といった基本的なデータから、フルタイムパートの場合の平均年収との比較、そして稼いだパート代をみんながどうしてるのかまで、気になるお金の情報を網羅的に解説します。
税金や社会保険の仕組みを理解し、あなたにとって最適な働き方を見つけるための一助となれば幸いです。
記事のポイント
- 主婦パートの平均的な収入の実態
- 複雑な「年収の壁」の仕組みと種類
- 扶養内で働くか外れるか、損しない働き方の目安
- キャリアアップ助成金など国の支援策のポイント
主婦パートの平均年収・月収はどのくらい?実態を解説

- データで見る主婦パートの平均時給
- 主婦パートの平均時間はどのくらいか
- フルタイムパートの平均年収と比較
- 「年収の壁」とは?種類と違いを解説
- 所得税がかかる103万円の壁
- 社会保険に加入する106万円の壁

私も最初はよくわからなくて、「働き損」になるところだった(汗)
毎年ちょっとずつ制度も変わるから、自分でしっかり情報収集するのがマジで大事!
データで見る主婦パートの平均時給
主婦の方がパートとして働く際の平均時給は、職種や地域、また本人のスキルによって幅がありますが、全体的な傾向を把握することは可能です。
厚生労働省が公表している「毎月勤労統計調査」を参考にすると、パートタイム労働者全体の平均的な時給が明らかになります。
令和5年のデータでは、パートタイム労働者の月間総労働時間の平均が約79時間、月収が約10万円となっており、ここから時給を計算するとおおよそ1,200円台後半から1,300円前後という数字が見えてきます。
ただし、これはあくまで全体の平均値です。
主婦層に限定すると、この平均よりも時給が若干低くなる傾向があると考えられます。
なぜなら、パートタイム労働者には専門職や技術職といった高時給の職種も含まれる一方、主婦に人気の高い職種(販売、軽作業、飲食など)は時給が平均を下回るケースも少なくないからです。
また、都市部と地方では最低賃金の額が異なるため、時給にも地域差が生じます。
都市部では時給1,300円以上も珍しくありませんが、地方では1,000円前後ということもあります。
自身の希望する職種や地域の求人情報を確認し、具体的な時給の相場を把握することが大切です。
主婦パートの平均時間はどのくらいか

主婦のパートにおける平均的な労働時間は、扶養内で働きたいという意向が大きく影響します。
そのため、労働時間は比較的短くなる傾向が見られます。
前述の「毎月勤労統計調査」によると、パートタイム労働者全体の月間平均労働時間は約79時間、平均出勤日数は13.6日です。
これを基に1日あたりの労働時間を計算すると、約5.8時間となります。
週に3日~4日、1日に5~6時間程度働くというのが一つのモデルケースとして考えられます。
しかし、これもあくまで全体の平均です。
特に主婦の場合、「年収の壁」を意識して、年間の収入が一定額を超えないように労働時間を調整する方が非常に多いです。
例えば、年収103万円の壁を意識する場合、月収を約8万5千円に抑える必要があり、時給1,200円であれば月の労働時間は約70時間となります。
このように、家庭の事情や扶養の条件に合わせて柔軟に働き方を調整できるのがパートタイムの利点でもあります。
午前中だけ、あるいは子供が学校に行っている間だけといった、短時間勤務を選択する主婦の方も多く、一概に平均時間を示すのは難しい側面も持ち合わせています。
フルタイムパートの平均年収と比較
「フルタイムパート」という言葉に正式な定義はありませんが、一般的には正社員とほぼ同等の時間(週40時間程度)働く非正規雇用のパートタイマーを指します。
扶養の範囲を気にせず、しっかりと収入を得たいと考える方がこの働き方を選択します。
フルタイムパートの平均年収は、時給によって大きく変動します。
仮に時給1,300円で週40時間、月に4.3週働いたと仮定すると、月収は約22万3,600円となり、年収換算では約268万円に達します。
時給が1,500円であれば年収は約309万円です。
もちろん、これは社会保険料や税金が引かれる前の総支給額であり、手取り額はこれよりも少なくなります。
フルタイムで働く場合は年収130万円の壁を大幅に超えるため、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
扶養内で働くパートの平均年収が約122万円であることと比較すると、フルタイムパートの収入は倍以上になることが分かります。
社会保険に加入することで将来の年金受給額が増える、病気やケガの際に傷病手当金が受けられるといったメリットもあります。
家計の主軸として収入を確保したい場合や、キャリア形成を視野に入れる場合には、フルタイムでの働き方が有力な選択肢となるでしょう。
「年収の壁」とは?種類と違いを解説

主婦がパートで働く際に必ず耳にする「年収の壁」とは、収入が一定額を超えると税金の負担が発生したり、夫の扶養から外れて社会保険料を自分で支払う必要が生じたりするボーダーラインの俗称です。
この壁には複数の種類があり、それぞれ意味合いが異なるため、正しく理解しておくことが求められます。
年収の壁は、大きく分けて「税制上の壁」と「社会保険上の壁」の2種類に分類できます。
税制上の壁
これは主に、所得税や住民税、そして配偶者(特別)控除に関わる壁です。
代表的なものに「100万円の壁(住民税)」「103万円の壁(所得税)」「150万円の壁(配偶者特別控除)」があります。
これらの壁を超えると、自分自身に税金が課されたり、配偶者の税負担が増えたりします。
社会保険上の壁
これは、自分自身で社会保険料(健康保険・厚生年金)を支払う義務が生じるかどうかの壁です。
代表的なものに「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。
この壁を超えると、夫の社会保険の扶養から外れ、収入から社会保険料が天引きされるため、手取り額が大きく減少する可能性があります。
これらの壁を意識せずに働くと、「収入は増えたのに手取りが減ってしまった」という、いわゆる「働き損」の状態に陥ることがあります。
それぞれの壁が持つ意味と、自身の働き方がどの壁に影響されるのかを事前に把握し、計画的に働くことが賢い選択と言えます。
所得税がかかる103万円の壁
「103万円の壁」は、税制上の壁の中で最もよく知られているものの一つです。
パート年収が103万円を超えると、自分自身に所得税が課されるようになります。
なぜ103万円が基準になるかというと、所得税の計算に関わる「給与所得控除(最低55万円)」と「基礎控除(48万円)」の合計が103万円だからです。
つまり、年収が103万円以下であれば、これらの控除によって課税対象の所得がゼロになり、所得税がかからない仕組みになっています。
また、103万円は夫の税金に関わる「配偶者控除」が受けられるかどうかのボーダーラインでもあります。
妻の年収が103万円以下の場合、夫は38万円の配偶者控除を受けられ、その分、夫の所得税や住民税が安くなります。
さらに、多くの企業では、家族手当や扶養手当の支給条件を「配偶者の年収が103万円以下」と定めている場合があります。
この手当は月額1万円を超えることも珍しくなく、支給が停止されると世帯収入に直接影響します。勤務先の規定を事前に確認しておくことが非常に大切です。
なお、年収が103万円を少し超えた場合の所得税額自体は年間で数千円程度と、それほど大きな負担ではありません。
むしろ、配偶者手当の有無の方が家計へのインパクトは大きいと言えるでしょう。
社会保険に加入する106万円の壁

「106万円の壁」は、社会保険上の壁の一つです。
特定の条件を満たす場合、年収が106万円(月収8.8万円)を超えると、夫の扶養から外れて、自分自身で勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じます。
この壁の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
- 学生ではない
- 勤務先の従業員数が51人以上(※2024年10月~)
この壁の大きな特徴は、従業員数51人以上の比較的大きな企業で働くパートタイマーが対象となる点です。
小規模な個人商店などで働く場合は、この壁の対象にはなりません。
社会保険に加入すると、給与から保険料(年収の約14~15%)が天引きされるため、年収106万円を少し超えたあたりでは手取り額が減少します。
これが働き損と言われる所以です。
一方で、社会保険加入には大きなメリットもあります。
将来受け取れる国民年金に加えて厚生年金が上乗せされるため、老後の備えが手厚くなります。
また、病気やケガで長期間仕事を休んだ際には「傷病手当金」が、出産で休んだ際には「出産手当金」が支給されるなど、保障が充実します。
デメリットである手取りの減少だけでなく、これらの長期的なメリットも考慮して働き方を判断することが求められます。
-
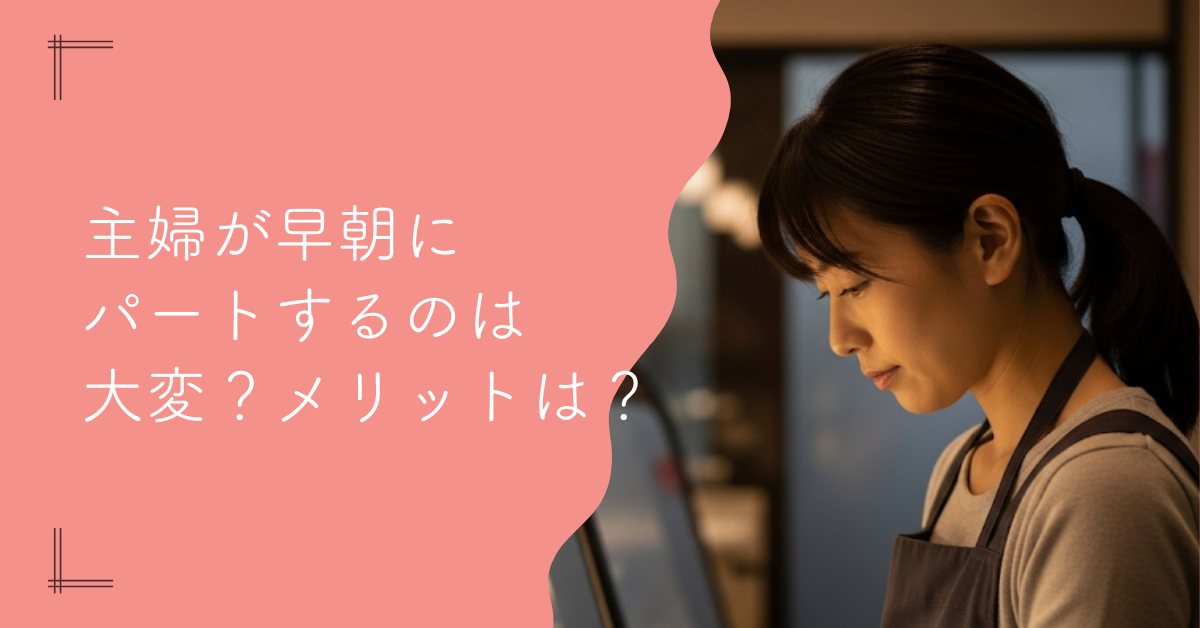
主婦の早朝パート探しから見つける理想の働き方とメリット
続きを見る
主婦パート必見!平均年収・月収と賢い働き方のコツ

- 扶養から外れる130万円の壁に注意
- パートは結局いくら稼ぐのが得なのか
- 2025年制度改正で壁はどう変わる?
- みんなパート代はどうしてる?使い道を調査
- 扶養者控除が減る150万円の壁

130〜150万くらいの中途半端なラインが一番「働き損」になるっていうのは、覚えておいた方がいいよ!
扶養から外れる130万円の壁に注意
「130万円の壁」は、もう一つの社会保険上の壁です。
これは、勤務先の企業規模に関わらず、すべてのパートタイマーが対象となります。
年収が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払う必要が出てきます。
106万円の壁との違いは、適用される条件の広さです。
106万円の壁は従業員数51人以上の企業で働く方などが対象ですが、130万円の壁にはそうした制約がありません。
個人経営のカフェや小規模なクリニックで働くパートタイマーであっても、年収が130万円を超えれば扶養を外れることになります。
扶養から外れた後の手続きは、働き方によって異なります。
勤務先の社会保険の加入要件(一般的に週の労働時間が正社員の4分の3以上など)を満たしていれば、その会社の社会保険に加入します。
要件を満たさない場合は、個人で市区町村の国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を自分で納付しなければなりません。
年収130万円を少し超えるあたりが、最も手取りの減少額が大きくなる「働き損」のゾーンです。
年収130万円の場合、社会保険料の負担は年間で約20万円以上になることもあり、手取り額は年収129万円の時よりも大幅に減ってしまいます。
この壁を超える場合は、手取りの減少分をカバーできるくらい、さらに収入を増やす覚悟が必要です。
パートは結局いくら稼ぐのが得なのか

結局のところ、パートでいくら稼ぐのが最も「得」なのかは、その人の価値観や家庭の状況によって異なります。
一概に「この年収が一番良い」と断言はできませんが、考えられる働き方のパターンは大きく3つに分けられます。
パターン1:扶養の範囲内で働く(~130万円未満)
税金や社会保険料の負担を最小限に抑え、効率よく手取りを確保したい場合は、年収130万円未満、あるいは106万円未満に調整するのが賢明です。
特に、年間100万円以下であれば住民税も所得税もかからず、社会保険の扶養からも外れないため、稼いだ分がほぼそのまま手取りに近い形になります。
お小遣いや家計の足しとして、無理のない範囲で働きたい方におすすめです。
パターン2:しっかり稼いで手取りを増やす(150万円以上)
社会保険料の負担を覚悟の上で、世帯収入を増やしたい場合は、年収150万円以上、できれば160万円以上を目指すのが一つの目安となります。
年収130万円を超えた直後の手取りの落ち込みをカバーし、扶養内で働いていた時よりも手取り額を増やすには、少なくともこのくらいの収入が必要になってきます。
将来の年金受給額を増やしたい、キャリアを築きたいという方にも向いています。
以下の表は、年収別の手取り額の目安をシミュレーションしたものです。
社会保険に加入すると手取りがどう変わるか、参考にしてください。
| 年間収入 | 所得税・住民税 | 社会保険料 | 手取り額(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 0円 | 100万円 | 扶養内 |
| 129万円 | 約3万円 | 0円 | 126万円 | 扶養内 |
| 130万円 | 約3万円 | 約20万円 | 107万円 | 手取り逆転(国民健康保険・国民年金に加入) |
| 150万円 | 約5万円 | 約22万円 | 123万円 | 手取りが扶養内129万円時点に近づく |
| 160万円 | 約6万円 | 約24万円 | 130万円 | 手取りが扶養内129万円時点を超える |
このように、中途半端に130万円を超えると手取りが減ってしまうため、「扶養内で働く」か「しっかり稼ぐ」か、どちらかを選択することが損をしないためのポイントです。
2025年制度改正で壁はどう変わる?
年収の壁を巡る状況は、年々変化しています。
特に、政府は人手不足解消や女性の活躍推進の観点から、壁を意識せずに働ける環境整備を進めています。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用
現在、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」として、いくつかの支援策を打ち出しています。
その中でも注目すべきは、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」です。
これは、従業員が新たに106万円の壁を超えて社会保険に加入する際に、事業主が手当の支給などで収入を増やす取り組みを行った場合、国が事業主に対して助成金を支給する制度です。
この制度を活用すれば、労働者は手取りの減少を気にすることなく社会保険に加入でき、企業側も人手不足の解消につなげることができます。
パート先がこの制度を導入しているか、あるいは導入を検討できないか相談してみる価値はあるでしょう。
今後の法改正の動向
2024年10月からは、社会保険の適用対象が「従業員数101人以上」から「従業員数51人以上」の企業へと拡大されました。
これにより、これまで対象外だった中小企業で働くパートタイマーも、106万円の壁を意識する必要が出てきています。
今後も、社会保険の適用はさらに拡大される可能性があります。
また、配偶者控除のあり方など、税制面での見直しも常に議論されています。
こうした制度改正のニュースにアンテナを張り、最新の情報をキャッチアップしていくことが、自身の働き方を考える上でますます大切になってきます。
不確定な情報に惑わされず、政府や自治体の発表する正確な情報を確認するように心がけましょう。
みんなパート代はどうしてる?使い道を調査

パートで得た収入の使い道は、家庭の状況や個人のライフプランによって実に様々です。
しかし、一般的にはいくつかの共通した傾向が見られます。
最も多い使い道は、やはり「生活費の補填」です。
食費や日用品、光熱費など、日々の家計の足しにするという方が大半を占めます。
物価高が続くいま、パート収入が家計の助けになっている家庭は少なくないでしょう。
次に多いのが、「子どものための費用」です。
塾や習い事といった教育費、学費、あるいは子どものためのお小遣いや衣類代などに充てるというケースです。
子どもの将来のために、あるいは豊かな経験をさせてあげたいという親心から、パートを始める方も多くいます。
また、「自身の貯蓄や投資」も重要な使い道の一つです。
老後の生活資金に不安を感じ、将来のために少しでも貯蓄を増やしたいという目的で働く方も増えています。
iDeCoやNISAなどを活用して、計画的に資産形成を行う主婦もいます。
もちろん、「自分のお小遣い」として、趣味や美容、友人との交際費などに使う方もいます。
パート収入があることで、精神的なゆとりや生活の潤いが生まれることも、働くことの大きなメリットと言えます。
これらの使い道を複合的に組み合わせている方がほとんどで、パート収入が家計と個人の生活の両方を豊かにしていることがうかがえます。
扶養者控除が減る150万円の壁
「150万円の壁」は、税制上の壁の一つで、夫(扶養者)の税負担に関わる「配偶者特別控除」の金額が変わり始めるボーダーラインです。
妻のパート年収が103万円を超えると、夫は「配偶者控除」を受けられなくなります。
しかし、それに代わって「配偶者特別控除」という制度が適用されます。
この配偶者特別控除は、妻の年収が150万円以下であれば、配偶者控除と同額の38万円(満額)が控除されます。
ところが、妻の年収が150万円を超えると、この配偶者特別控除の額が、収入に応じて段階的に減っていく仕組みになっています。
そして、年収が201.6万円以上になると、控除額はゼロになります。
| パート主婦の年収 | 配偶者特別控除額(夫の所得900万円以下の場合) |
|---|---|
| 150万円以下 | 38万円 |
| 150万円超~155万円以下 | 36万円 |
| 155万円超~160万円以下 | 31万円 |
| ...(段階的に減少) | ... |
| 201万円超~201.6万円未満 | 3万円 |
| 201.6万円以上 | 0円 |
「控除額が減るなら損をするのでは?」と心配になるかもしれませんが、心配は無用です。
確かに夫の税負担は少し増えますが、それ以上に妻自身の収入が増える額の方が圧倒的に大きいため、世帯全体の手取り収入は確実に増えます。
したがって、150万円の壁は、社会保険の壁のように「超えると手取りが逆転する」という類のものではありません。
扶養を外れてしっかり稼ぐと決めたのであれば、150万円という数字は通過点と考え、気にする必要はほとんどないと言えるでしょう。
-

午後からパート主婦の働き方と午前中を有効活用する秘訣
続きを見る
主婦パートの平均年収・月収を知り賢く働こう

この記事では、主婦のパートにおける平均収入から、働き方を左右する「年収の壁」まで、詳しく解説してきました。
最後に、今回の内容の重要なポイントをまとめます。
ま と め
- パート全体の平均月収は約10万円、年収換算で約122万円が目安
- 主婦のパートは扶養内調整で平均より低くなる傾向がある
- 年収の壁には税金に関する「税制上の壁」と社会保険に関する「社会保険上の壁」がある
- 100万円の壁は住民税の課税ライン
- 103万円の壁は所得税の課税ラインであり、配偶者控除の基準
- 106万円の壁は一定条件を満たす場合に社会保険へ加入する基準
- 130万円の壁は勤務先の規模に関わらず社会保険の扶養から外れる基準
- 130万円を超えた直後は社会保険料負担で手取りが減る「働き損」に注意
- 150万円の壁は配偶者特別控除が減り始めるが世帯手取りは増える
- 効率よく働くなら130万円未満、しっかり稼ぐなら150万円以上が目安
- 社会保険加入は手取りが減るが、将来の年金が増えるなどのメリットもある
- 国の「年収の壁・支援強化パッケージ」などの支援策も確認する
- 2024年10月から社会保険の適用対象が従業員51人以上の企業に拡大された
- パート代の使い道は生活費の補填、教育費、貯蓄、お小遣いなど様々
- 自身のライフプランや家庭の状況に合わせて最適な働き方を選ぶことが大切

