※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
「毎日仕事と家事に追われて、何のために結婚したんだろう…」
「共働きなのに、経済的な余裕も心の余裕も全くない」
このように感じ、共働きでの結婚にメリットがないのではないかと疑問を抱いている方は少なくないでしょう。
家事や育身の負担から、時には共働きであることがバカバカしいと感じられたり、いっそのこと共働きなら結婚しない方が自由でいられるのではないか、という考えが頭をよぎることもあるかもしれません。
この記事では、そうした悩みの背景にある共働き結婚のメリットやデメリットを客観的な視点から深掘りします。
さらに、多くの方が気になる共働きと結婚に関する税金の問題にも触れながら、現状を乗り越えるための具体的なヒントを解説していきます。
記事のポイント
- 共働きにメリットがないと感じる具体的な理由
- メリットとデメリットの客観的な比較
- 共働き夫婦が直面しがちな課題の解決策
- 税金や家計管理で損をしないための知識
共働きで結婚にメリットがないと感じる理由とは?

- 共働きのメリット・デメリットを改めて比較
- 家事育児の負担増で共働きがバカバカしい
- コミュニケーション不足で夫婦のすれ違い
- 自分の時間がなく精神的に疲弊してしまう
- 経済的な余裕を実感しにくいという現実
- 共働きなら結婚しないという考え方

何のために結婚したんだっけ…って虚しくなる瞬間、あるよねぇ…。
共働きのメリット・デメリットを改めて比較
共働きというスタイルが当たり前になった現代において、そのメリットとデメリットを冷静に比較検討することが、夫婦関係を見つめ直す第一歩となります。
まずメリットとして最も大きいのは、経済的な安定でしょう。
夫婦二人の収入源があるため世帯収入が増加し、貯蓄や投資、住宅ローンの選択肢が広がります。
どちらか一方が病気や失業で働けなくなった場合でも、もう一方の収入があるため、経済的なリスクを分散できる点は大きな強みです。
また、結婚や出産後もキャリアを継続しやすく、仕事を通じて自己実現を目指せることも精神的な充実につながります。
一方で、デメリットも決して少なくありません。
最大の課題は、仕事と家庭の両立の難しさです。
特に家事や育児の負担がどちらか一方に偏りやすく、心身の疲労が蓄積する原因となります。
夫婦ともに多忙なため、二人でゆっくり話す時間が確保できず、すれ違いが生じやすくなるのも典型的なパターンです。
さらに、外食や家事代行サービスの利用が増えることで支出がかさみ、思ったほど経済的な余裕を実感できないケースも見受けられます。
これらのデメリットが積み重なることで、「共働きなのに何故こんなに苦しいのか」という疑問につながっていくのです。
家事育児の負担増で共働きがバカバカしい

「自分も同じように働いているのに、なぜ家事や育児は私ばかりが担当しなければならないのか」という不満は、共働き夫婦の間で最も深刻な問題の一つです。
この不公平感が積み重なると、やがて「こんなに頑張っているのがバカバカしい」という感情に発展することがあります。
本来、共働きであれば家庭内の仕事も協力して分担するのが理想です。
しかし、実際には「家事・育児は女性の役割」という根強い意識が残っており、夫が非協力的であったり、指示待ちの状態であったりする家庭は少なくありません。
そうなると、妻は仕事の責任に加えて、家庭内のタスク管理という見えない労働まで背負うことになります。
食事の準備、子どもの世話、掃除、洗濯といった日々のタスクに追われ、自分の時間は全くない。
夫は仕事から帰ればソファでくつろいでいる。このような状況が続けば、パートナーへの愛情よりも不満や怒りが大きくなってしまうのは自然なことです。
そして、この「バカバカしい」という感情は、単なる疲れではなく、相手への尊敬の念が失われつつある危険なサインとも考えられます。
コミュニケーション不足で夫婦のすれ違い
共働き夫婦が直面する大きな壁の一つに、コミュニケーションの絶対的な不足が挙げられます。
朝は慌ただしく出勤し、夜は疲れ切って帰宅する毎日の中で、夫婦がゆっくりと向き合って話す時間を確保するのは至難の業です。
顔を合わせても会話の内容が子どもの予定や支払いの確認といった「業務連絡」ばかりになってしまうと、心の距離は徐々に開いていきます。
結婚前は楽しかった相手の一日の出来事を聞く余裕もなくなり、相手の話にただ相槌を打つだけになってしまうことも少なくありません。
休日も溜まった家事をこなすので精一杯で、気づけば同じ家にいながら別々の部屋でスマートフォンを眺めている、という状況は多くの夫婦が経験しています。
このような「同居人」のような状態が続くと、相手が何を考え、何に悩み、何に喜んでいるのかが分からなくなります。
人間関係は意識的に育まなければ衰えていくものであり、特に夫婦関係は日々の小さな心の交流の積み重ねで成り立っています。
その交流が途絶えてしまえば、関係がすれ違い、冷え込んでいくのは避けられないのかもしれません。
自分の時間がなく精神的に疲弊してしまう

仕事と家庭、二つの役割の間で常に走り続けていると、「自分自身」のための時間が完全になくなってしまうことがあります。
これは、共働き生活における深刻な精神的疲弊の原因です。
結婚前は当たり前だった、仕事帰りに友人と食事をしたり、休日に一人で趣味に没頭したりする時間。
そうした時間が奪われることで、人は知らず知らずのうちにストレスを溜め込み、自分らしさを見失っていきます。
わずかな自由時間を作ろうとしても、パートナーから「なぜ家のことをしないのか」という無言のプレッシャーを感じ、罪悪感を抱いてしまうことさえあります。
自分が何が好きで、何に情熱を傾けていたのかさえ忘れてしまうような日々が続けば、心のバランスが崩れてしまうのも無理はありません。
この自己犠牲の上に成り立つ生活に対して、「何のためにこんなに頑張っているのだろう」「この結婚は本当に自分を幸せにしているのか」という根本的な疑問が湧き上がってくるのです。
パートナー個人への不満というより、このライフスタイルそのものへの息苦しさが、結婚生活へのメリットを感じさせなくする大きな要因となります。
経済的な余裕を実感しにくいという現実
共働きの最大のメリットは「経済的な安定」のはずなのに、現実は「思ったほど楽にならない」と感じている夫婦は多いようです。
二人分の収入があるにもかかわらず、なぜか月末にはお金が残らない。この状況は「豊かな貧困」とも言え、精神的な不満につながる皮肉な現実です。
この背景には、共働きであるがゆえの支出の増加があります。
夫婦ともに多忙なため、自炊する時間がなく外食やデリバリーに頼ることが増えます。
また、家事の負担を軽減するために、食洗機や乾燥機付き洗濯機といった高機能な家電を導入したり、家事代行サービスを利用したりすることもあるでしょう。
子どものいる家庭では、保育料や習い事の費用もかかります。
これらの「時間を買うためのお金」は、必要経費とも言えますが、積み重なると大きな負担となります。
その結果、世帯年収は高くても、自由に使えるお金が少なく、貯蓄も思うように増えないという事態に陥りがちです。
収入が増えても生活水準が上がった実感がなく、ただ忙しいだけであれば、何のために働いているのか分からなくなり、結婚生活のメリットを見失ってしまうのです。
共働きなら結婚しないという考え方

経済的に自立した個人が増える中で、「共働きで大変な思いをするくらいなら、結婚しない方が合理的だ」という考え方も一つの選択肢として存在感を増しています。
結婚という制度に縛られず、自分の時間やお金を自由に使える独身生活の方が、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)が高いと感じる人がいるのは自然なことです。
結婚には、法的な保障や社会的な信用といった側面もありますが、同時に家事や育児、親戚付き合いなど、多くの責任や義務が伴います。
もし共働きをすることで、自由な時間が奪われ、家事の負担が増え、精神的に疲弊するデメリットの方が大きいと感じるなら、あえて結婚という形を選ぶ必要はない、と考えるのは論理的です。
特に、仕事にやりがいを感じ、キャリアを追求したい人にとっては、結婚が足かせになる可能性も否定できません。
お互いを高め合える理想的なパートナーシップを築けるのであれば話は別ですが、単なる「生活の共同経営者」になるだけであれば、一人でいる方が気楽だと考える人がいても不思議ではないでしょう。
このように、結婚そのものの価値を問い直す視点が生まれるのも、共働きが一般的になった現代ならではの傾向と言えます。
-

共働き夫婦の離婚率は?データから見る実態と回避策
続きを見る
「共働きで結婚にメリットがない」を解消する5つの秘訣

- 家事と育児の公平な分担ルールを決める
- コミュニケーションの質を高める工夫
- 共働き結婚の税金で損をしない知識
- 家計管理を協力して経済的メリットを出す
- お互いのキャリアや時間を尊重し合う

でも、そこからやっと本当の分担が始まった感じ。見える化、マジ大事!
家事と育児の公平な分担ルールを決める
「共働きがバカバカしい」と感じる最大の原因である家事・育児の不公平感を解消することが、関係改善の最も重要な一歩です。
そのためには、単に「手伝って」とお願いするのではなく、夫婦で具体的なルールを決める必要があります。
まず、家庭内に存在する全てのタスクを書き出して可視化することから始めましょう。
「名もなき家事」と呼ばれるような、トイレットペーパーの補充や子どもの提出物の管理なども含めてリストアップします。
そして、それらのタスクをお互いの得意・不得意や勤務時間に合わせて分担します。
例えば、「平日の夕食は夫担当、週末は妻担当」「ゴミ出しと風呂掃除は夫、洗濯と掃除機は妻」のように、責任の所在を明確にすることが鍵です。
重要なのは、どちらかが家事全体の「マネージャー」にならないことです。
担当になった家事については、スケジュールの管理から実行まで、その人が責任を持つという意識を共有します。
時には外部のサービス(家事代行や食材宅配など)を積極的に利用することも検討し、夫婦だけで抱え込まない体制を築くことが、長期的に良好な関係を維持する秘訣と考えられます。
コミュニケーションの質を高める工夫

多忙な共働き夫婦にとって、コミュニケーションは「量」よりも「質」を意識することが大切です。
短い時間でも、お互いの心を通わせるための工夫を取り入れてみましょう。
例えば、1日に10分でも良いので、「スマートフォンやテレビを消して、お互いの目を見て話す時間」を意識的に作ることが効果的です。
その日の出来事や感じたことを共有するだけでも、相手への関心を示すことにつながります。
会話の内容は、愚痴や不満だけでなく、感謝の気持ちや相手を褒める言葉など、ポジティブな話題を心がけると、より良い雰囲気を作ることができます。
また、定期的に「夫婦のデート」を計画するのもおすすめです。
月に一度でも、子どもを預けて二人きりで食事や映画に出かけることで、恋人だった頃の気持ちを思い出すきっかけになります。
こうした非日常の時間が、日々のすれ違いをリセットし、パートナーとしての絆を再確認させてくれるでしょう。
大切なのは、関係性を維持するためには意識的な努力が必要であると、夫婦双方が理解することです。
共働き結婚の税金で損をしない知識
共働き夫婦が経済的なメリットを最大限に享受するためには、税金の知識が不可欠です。
特に、パートタイムで働く場合は「年収の壁」を意識しないと、かえって世帯の手取りが減ってしまう可能性があります。
主な「年収の壁」とその影響を以下の表にまとめました。
| 年収の壁(目安) | 影響を受ける主な制度 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 103万円の壁 | 所得税・住民税 | これを超えると、配偶者控除が適用されなくなり、配偶者特別控除に切り替わる。本人にも所得税が発生し始める。 |
| 106万円の壁 | 社会保険 | 一定の条件(※)を満たすと、勤務先の社会保険への加入義務が発生。保険料負担で手取りが減るが、将来の年金は増える。 |
| 130万円の壁 | 社会保険 | 勤務先の条件に関わらず、配偶者の社会保険の扶養から外れる。自身で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要がある。 |
※106万円の壁の主な条件:従業員数51人以上の企業(2024年10月以降)、週の労働時間が20時間以上、月収8.8万円以上など。
これらの壁を中途半端に超えると、税金や社会保険料の負担が急に増え、「働き損」の状態になりかねません。
扶養内で働く場合は壁を意識してシフトを調整するか、もしくは壁を大きく超えて世帯収入の増加を目指すか、夫婦でライフプランを話し合って方針を決めることが大切です。
その他の節税対策
前述の壁以外にも、iDeCo(個人型確定拠出年金)やふるさと納税といった制度を活用することで、税負担を軽減できます。
iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となり、ふるさと納税は実質2,000円の負担で返礼品が受け取れるため、家計の助けになります。
これらの制度も夫婦それぞれが利用できるため、積極的に活用を検討しましょう。
家計管理を協力して経済的メリットを出す

「収入は増えたはずなのに、なぜかお金が貯まらない」という状況を脱するためには、夫婦が協力して家計を管理する仕組み作りが必要です。
夫婦それぞれが自分の収入を管理する「夫婦別財布」は、一見自立していて良いように見えますが、家計全体の収支が不透明になり、浪費につながりやすいという欠点があります。
そこでおすすめなのが、「共通口座」を活用する方法です。
毎月決まった額(例えば手取りの7割など)を夫婦それぞれが共通口座に入金し、家賃や光熱費、食費といった生活費はその口座から支払います。
残ったお金はそれぞれが自由なお小遣いとする、というルールにすれば、家計の透明性が保たれ、個人の自由も確保できます。
また、家計簿アプリなどを活用して収支を「見える化」することも有効です。
どちらか一方が管理するのではなく、夫婦二人がいつでも家計の状況を確認できるようにすることで、お金に対する共通認識が生まれます。
将来の目標(住宅購入、子どもの教育費など)を共有し、それに向かって協力して貯蓄計画を立てることが、共働きの経済的メリットを実感するための鍵となります。
お互いのキャリアや時間を尊重し合う
共働き生活を円滑に続けるためには、お互いを「生活の共同経営者」としてだけでなく、一人の人間として、そして「人生のパートナー」として尊重し合う姿勢が不可欠です。
相手が仕事に情熱を注ぎ、キャリアアップを目指している姿を応援し、その成長を共に喜べる関係性を築くことが理想です。
そのためには、相手の仕事内容に興味を持ち、大変な時には話を聞いて労うことが大切になります。
専門分野が違って深くは理解できなくても、「大変だったね」「頑張っているね」と共感を示すだけで、相手の心は軽くなるものです。
同様に、お互いの「個人の時間」を尊重することも重要です。
趣味に没頭する時間や、友人と過ごす時間は、心のリフレッシュのために欠かせません。
例えば、「土曜の午前中は夫の趣味の時間、日曜の午後は妻が友人と会う時間」といったように、お互いが気兼ねなく自分の時間を楽しめるルールを作ると良いでしょう。
自分自身の時間が確保され、心が満たされることで、パートナーに対しても寛容になれるものです。このような相互尊重の精神が、忙しい共働き生活を支える土台となります。
-
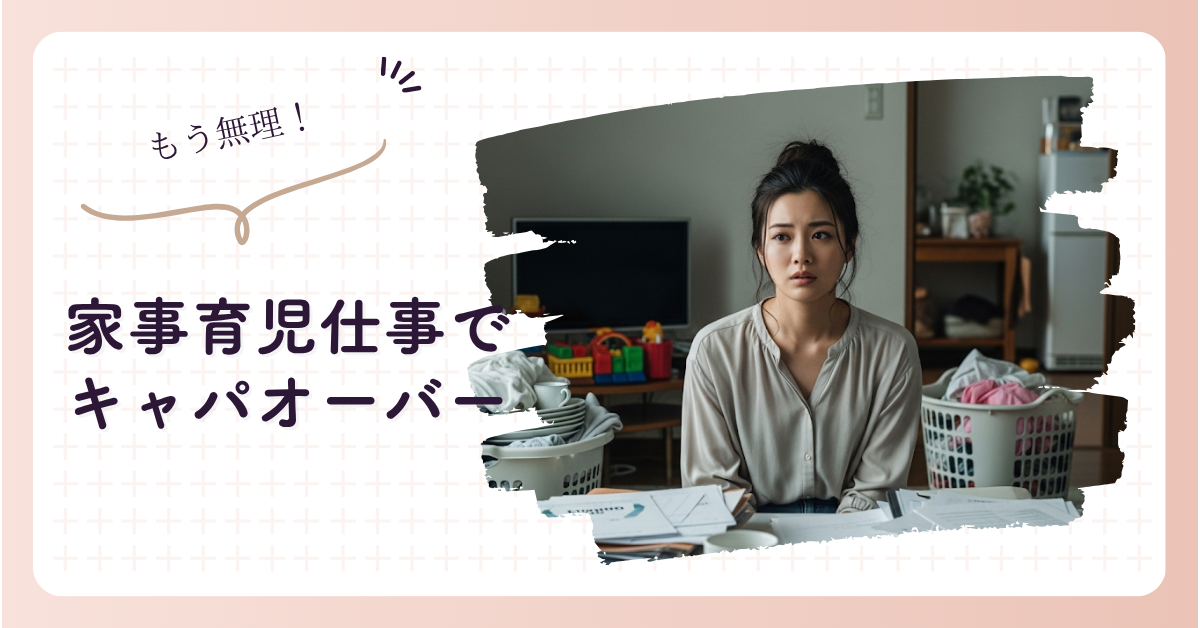
家事育児仕事でキャパオーバー!もう無理と感じたら
続きを見る
共働きで結婚にメリットがないと感じた時の対処法

これまで、共働き結婚のメリット・デメリットや、課題を乗り越えるための具体的な方法について解説してきました。
もし今、あなたが「共働きでの結婚にメリットがない」と感じているのであれば、それは関係性を見直すための重要なサインかもしれません。
最後に、この記事の要点をまとめます。
ま と め
- 共働きには経済的安定やキャリア継続というメリットがある
- 一方で家事負担やコミュニケーション不足などのデメリットも存在する
- 「メリットがない」と感じる背景には、多くの場合、不公平感や精神的疲弊がある
- 家事や育児の負担が一方に偏ると「バカバカしい」という感情につながりやすい
- 多忙によるコミュニケーション不足は、夫婦関係を「同居人」のようにしてしまう
- 自分の時間が失われると、結婚生活そのものに疑問を感じるようになる
- 収入が増えても支出も増え、経済的余裕を実感しにくいケースも多い
- 課題解決の第一歩は、家事・育児タスクの可視化と公平な分担ルールの設定
- コミュニケーションは量より質を重視し、二人だけの時間を意識的に作ることが大切
- 税金の「年収の壁」を理解しないと「働き損」になる可能性がある
- iDeCoやふるさと納税は共働き夫婦が活用すべき節税制度
- 共通口座の活用などで家計を「見える化」し、協力して管理する
- お互いのキャリアや時間を尊重し合う姿勢が関係の土台となる
- 外部サービスも積極的に利用し、夫婦だけで抱え込まない
- 現状に不満があるなら、諦めずにパートナーと話し合う機会を持つことが重要

