※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
ワーキングマザー(ワーママ)にとって、小学校の長期休みに伴う学童のお弁当作りは、大きな悩みの種ではないでしょうか。
毎日の献立を考え、朝の忙しい時間にお弁当を準備するのは、本当に大変なことです。
「正直、学童弁当作りがしんどい」「もっと上手に手抜きしたい」と感じたり、彩りや栄養バランスを考えてはため息をついたりする日もあるかもしれません。
中には、学童のお弁当にコンビニの商品を利用することに罪悪感を覚えたり、他の保護者のお弁当と比べてワーママである自分のお弁当を不十分だと感じ、自分自身を責めてしまったりすることもあるでしょう。
しかし、そのように感じる必要はまったくありません。少しの工夫と考え方で、お弁当作りの負担は大きく軽減できます。
この記事では、ワーママが学童のお弁当作りと上手に付き合い、無理なく、そして楽しく続けるための具体的な方法とヒントを、多角的な視点から詳しく解説していきます。
記事のポイント
- ワーママがお弁当作りを「しんどい」と感じる具体的な理由
- 罪悪感なくできる「手抜き」のコツと具体的なアイデア
- コンビニ商品や冷凍食品を賢く活用する方法と注意点
- 無理なく続けられる献立の考え方や時短テクニック
ワーママが悩む学童のお弁当、その理由とは

- 「学童弁当がしんどい」と感じる背景
- 毎日の学童弁当の献立を考える負担
- ワーママがお弁当で自分を責めないために
- 長期休みに特に気を付けたい衛生管理

毎日のことだから「正直しんどい!」って思う日もあるのが本音。
我が家はもう学童ではないけど、中学生と高校生が毎日お弁当…!
少しでも楽になるヒント、切実に知りたい〜!
「学童弁当がしんどい」と感じる背景
ワーママが学童のお弁当作りを「しんどい」と感じるのには、明確な理由が存在します。
これは単なる甘えや愚痴ではなく、多くのワーママが直面する構造的な課題から生じるものです。
最大の理由は、時間的な制約です。
朝は自分の身支度や子供の世話、朝食の準備など、ただでさえ分刻みのスケジュールで動いています。
その中で、お弁当のおかずを作り、冷まし、詰めるという工程を追加するのは、物理的にも精神的にも大きなプレッシャーとなります。
保育園時代は給食があったため、この負担がなかった分、小学校の長期休み期間にそのギャップを強く感じる方が多いようです。
また、栄養バランスや彩りといった「こうあるべき」という理想像が、無意識のうちに自分を追い詰めているケースも少なくありません。
子供の健やかな成長を願うからこそ、栄養面を手抜きしたくないという思いが強くなります。
その結果、献立を考える段階から精神的な疲労が蓄積していくのです。
このように、限られた時間の中で高いクオリティを求められる状況が、「しんどい」という感情の根本的な背景にあると考えられます。
毎日の学童弁当の献立を考える負担

お弁当作りにおける具体的な作業以上に、多くのワーママの頭を悩ませているのが「毎日の献立を考える」というタスクです。
これは、終わりが見えないクリエイティブな作業であり、精神的な負担が非常に大きい部分と言えます。
献立を考える上での悩みは、主に3つの点に集約されます。
第一に、栄養バランスへの配慮です。
肉や魚、野菜、炭水化物をどう組み合わせるか、毎日考え続けるのは簡単ではありません。
第二に、メニューのマンネリ化です。
どうしても作り慣れたおかずや子供が好きなものに偏りがちになり、「また同じメニューだ」と自己嫌悪に陥ることもあります。
そして第三に、子供の好き嫌いです。
せっかく作ったお弁当を残されてしまうと、徒労感は計り知れません。
子供が喜んで食べてくれるメニューを、栄養バランスや彩りを考慮しながら毎日考案し続けることは、想像以上にエネルギーを消耗する作業なのです。
この献立考案の負担をいかに軽減するかが、お弁当作りを継続する上での鍵となります。
ワーママがお弁当で自分を責めないために
学童のお弁当作りにおいて、ワーママが陥りがちなのが「自分を責めてしまう」という思考の罠です。
SNSなどで見る手の込んだお弁当と自分のお弁当を比べて落ち込んだり、市販品を使ったことに罪悪感を覚えたりする必要は全くありません。
まず、他の誰かと比べることをやめる意識が大切です。
家庭環境や仕事の状況、得意不得意は人それぞれ異なります。
大切なのは、他の家庭の基準に合わせることではなく、自分の家庭にとってのベストな形を見つけることです。
お弁当は愛情を伝える手段の一つであって、その価値は手間や見た目の華やかさだけで決まるものではありません。
また、完璧を目指さないことも肝心です。
ワーママが仕事と育児を両立していること自体が、すでに素晴らしいことです。
その上で毎日お弁当を用意しているのですから、自分を褒めるべきでしょう。
多少手抜きをしたとしても、子供が笑顔で食べてくれれば、それが最高のお弁当です。
自分に「よくやっている」と声をかけ、過度な理想や罪悪感から自身を解放してあげることが、精神的な負担を減らす第一歩となります。
-
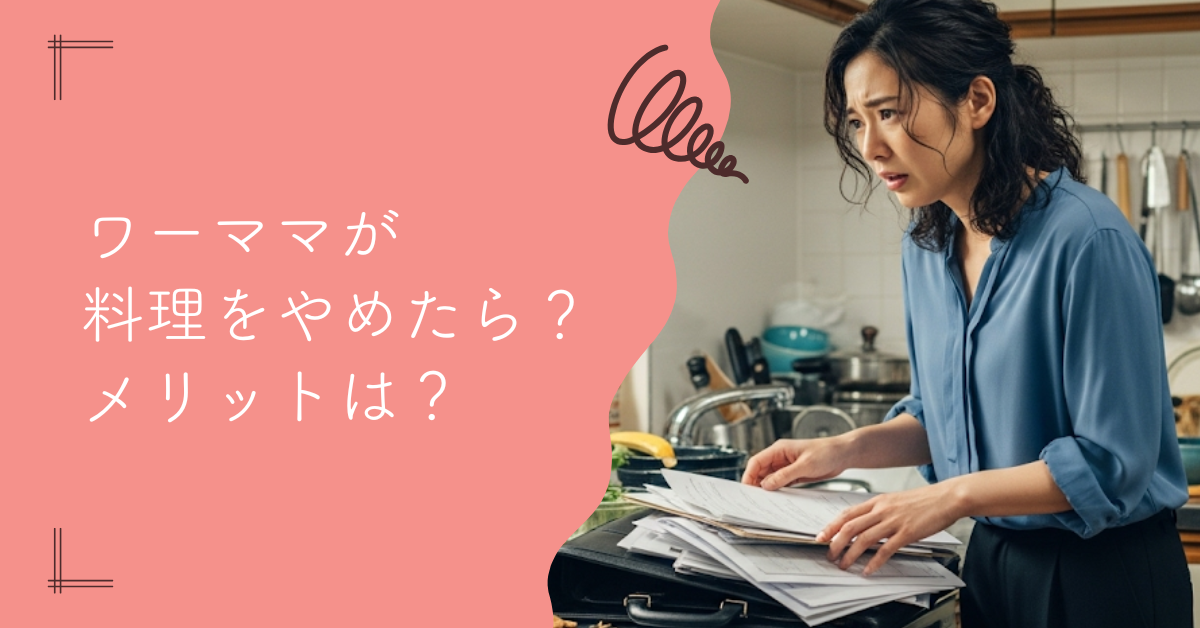
ワーママが料理をやめたら?メリット・デメリットと後悔しない方法
続きを見る
長期休みに特に気を付けたい衛生管理

特に夏休みのような気温と湿度が高い時期のお弁当作りでは、おいしさや栄養バランス以上に、食中毒を防ぐための衛生管理が最優先事項となります。
子供の健康を守るために、いくつかの重要なポイントを必ず押さえるようにしてください。
調理前・調理中の注意点
まず、調理を始める前には必ず石鹸で丁寧に手を洗いましょう。
調理器具、特にお弁当箱やまな板、包丁は清潔なものを使用します。
生肉や魚を切ったまな板で、そのまま野菜など他のおかずを調理するのは絶対に避けてください。
おかずはすべて、中心部までしっかりと加熱することが基本です。
卵焼きなども、半熟ではなく中まで火を通すようにします。
調理後のおかずは、お弁当箱に詰める前に必ず完全に冷ましてください。
温かいまま蓋をすると、内部に蒸気がこもって雑菌が繁殖しやすい温度(30~40℃)になってしまいます。
詰める時と持ち運びの工夫
おかずを詰める際は、素手で直接触らず、清潔な菜箸などを使用します。
ミニトマトのヘタは雑菌が付きやすいため、取り除いてからよく洗って入れるのがおすすめです。
そして、持ち運びの際には必ず保冷剤を活用しましょう。
お弁当箱の上に置くだけでなく、保冷効果のあるお弁当袋に入れるとさらに安心です。
傷みやすい食材を避ける
長期休みのお弁当では、以下のような傷みやすい食材は避けるのが賢明です。
| 避けた方が良い食材の例 | 理由 |
|---|---|
| 生野菜(レタス、きゅうりなど) | 水分が多く、雑菌が繁殖しやすい |
| マヨネーズやタルタルソースで和えたもの | 特に手作りのポテトサラダは傷みやすい |
| 炊き込みご飯、混ぜご飯 | 調理過程で菌が付きやすく、傷みやすい傾向がある |
| 半熟卵 | サルモネラ菌のリスクがあるため、固ゆでにする |
| 加工品のハムやかまぼこ | 加熱せずに使えるものも、夏場は一度加熱すると安心 |
これらの点を守ることで、食中毒のリスクを大幅に減らすことができます。
ワーママの学童のお弁当作りを楽にする工夫

- 学童お弁当は手抜きでも大丈夫な理由
- 時短に役立つ冷凍食品や作り置きのコツ
- 学童のお弁当にコンビニ商品を賢く活用
- 麺類や丼もので簡単!一品弁当アイデア
- 子供が喜ぶ栄養と彩りのポイント
- お弁当箱の選び方で後片付けも楽になる

上手に手抜きしながら、無理なく続けるのが一番よね!
学童お弁当は手抜きでも大丈夫な理由
毎日のお弁当作りにおいて、「手抜き」という言葉にネガティブなイメージを抱く必要はまったくありません。
むしろ、ワーママにとって上手な手抜きは、お弁当作りを無理なく継続するための「賢い戦略」と言えます。
手抜きをしても大丈夫な最大の理由は、ママの心の余裕が子供の心の安定に直結するからです。
お弁当作りのためにママが睡眠時間を削ったり、朝からイライラしたりしていては、その雰囲気は子供にも伝わってしまいます。
少し力を抜くことで生まれた心の余裕は、子供と穏やかに接する時間につながり、結果として家庭全体に良い影響をもたらします。
また、衛生面から見ても、市販の冷凍食品などを活用することはメリットがあります。
前述の通り、特に夏場は手作りの過程で雑菌が付着するリスクも考えられます。
品質管理された市販品を上手に取り入れることは、食中毒のリスクを低減させる一つの方法にもなり得るのです。
大切なのは、全てを手作りすることではなく、愛情がこもっていること。
子供が「おいしい」と感じてくれれば、それが一番のお弁当なのです。
時短に役立つ冷凍食品や作り置きのコツ

朝のお弁当作りにかかる時間を劇的に短縮してくれるのが、冷凍食品と週末の「作り置き」です。
これらを上手に活用することで、平日の朝は「詰めるだけ」の状態を作り出すことが可能になります。
冷凍食品の賢い選び方と使い方
最近の冷凍食品は、味も品質も格段に向上しています。
自然解凍OKのものは、そのままお弁当箱に入れるだけで保冷剤代わりにもなり、非常に便利です。
ただ、味が濃いものや添加物が気になる場合は、パッケージの裏面表示を確認する習慣をつけると良いでしょう。
ブロッコリーや枝豆、ほうれん草といった冷凍野菜は、彩りを加えたい時にさっと使えて重宝します。
週末の作り置きテクニック
週末など、比較的時間に余裕がある時に、お弁当用の副菜をいくつか作っておくと、平日の負担が大きく減ります。
きんぴらごぼう、ひじきの煮物、ほうれん草の胡麻和え、人参ナムルなどは作り置きに向いています。
作ったおかずは、お弁当用の小さなカップに一食分ずつ小分けにしてから冷凍するのがおすすめです。
こうしておけば、朝は凍ったままお弁当箱に入れるだけで済みます。
前日の夕食を作る際に、唐揚げやハンバーグなどのメインのおかずを少し多めに作って取り分けておき、冷凍ストックに加えるのも効果的な方法です。
学童のお弁当にコンビニ商品を賢く活用
「コンビニのおかずをお弁当に入れるのは、手抜きすぎるのでは…」と感じるかもしれませんが、近年のコンビニ商品は品質が非常に高く、ワーママの強力なサポーターになり得ます。
罪悪感を覚えることなく、賢く活用しましょう。
お弁当向きのコンビニ商品
コンビニには、お弁当のおかずに最適な商品がたくさんあります。
例えば、個包装された焼き魚や煮物、ミニハンバーグといったチルド惣菜は、温めるだけで一品が完成します。
また、袋入りのきんぴらごぼうやひじき煮なども、少量で使いやすく便利です。
意外な活用法としては、パンコーナーの商品を利用する方法があります。
ミニサイズのクリームパンやチョコレートパンは、ご飯の代わりにもなり、子供が喜ぶメニューになります。
おにぎりをそのまま持たせるのも、もちろん立派な選択肢です。
コンビニ商品を選ぶ際の注意点
コンビニ商品を利用する際は、いくつか注意したい点もあります。
一般的に、お弁当用のおかずとしては味が濃いめに作られていることが多いです。
塩分や糖分が気になる場合は、栄養成分表示を確認する習慣をつけましょう。
また、添加物が気になる方もいるかもしれません。
最近では、保存料や着色料を不使用とうたった商品も増えていますので、パッケージをよく見て選ぶのがおすすめです。
全ての品をコンビニ商品にするのではなく、「あと一品足りない時」や「メインのおかずだけ」というように、手作りと組み合わせてバランスを取るのが、賢い活用法の鍵となります。
麺類や丼もので簡単!一品弁当アイデア

毎日おかずを何品も詰めるのが大変だと感じたら、思い切って「一品弁当」の日を作ってみてはいかがでしょうか。
麺類や丼ものは、子供からの人気も高く、作る側の負担も少ないため、ワーママの強い味方になります。
代表的な一品弁当のメニューには、以下のようなものがあります。
- 焼きそば・焼きうどん: 前日の夕食に多めに作っておけば、朝は詰めるだけです。
- オムライス・チキンライス: 冷凍のチキンライスを活用すれば、卵を焼いて乗せるだけで完成します。
- タコライス: ご飯の上に、炒めたひき肉、刻んだレタス、チーズ、ミニトマトを乗せるだけ。彩りも豊かです。
- そうめん・冷やしうどん: 夏場に特に喜ばれるメニューです。麺は一口大に丸めておくと、子供が食べやすくなります。
- スープジャー活用: カレーやシチュー、ミネストローネなどをスープジャーに入れ、別容器でご飯やパンを持たせるのも良い方法です。
麺類をお弁当にする際は、固まったりくっついたりしないように、茹でた後にごま油などを少量絡めておくのがコツです。
また、そうめんなどのつけつゆは、液漏れしない専用の容器に入れるなど、持ち運びには工夫が必要です。
一品弁当を取り入れることで、献立のバリエーションが広がり、お弁当作りのマンネリ化も防げます。
子供が喜ぶ栄養と彩りのポイント
手早く作るお弁当でも、少しの工夫で子供が喜ぶ見た目と、成長に必要な栄養を確保することは可能です。
大切なのは、完璧を目指すのではなく、いくつかのポイントを押さえることです。
彩りを意識する
お弁当の蓋を開けた時の第一印象は、子供の食欲に大きく影響します。
難しく考えすぎず、「赤・黄・緑」の3色をお弁当に入れることを意識するだけで、見た目は格段に華やかになります。
- 赤: ミニトマト、パプリカ、カニカマ、人参
- 黄: 卵焼き、コーン、かぼちゃ、星形ポテト
- 緑: ブロッコリー、枝豆、ほうれん草、きゅうり
これらの食材を、メインのおかずの隙間に入れるだけで、ぐっと美味しそうに見えます。
キャラクターのかまぼこや、可愛い形のピックなどを活用するのも、手軽に特別感を演出できるテクニックです。
簡単な栄養バランスの考え方
毎食完璧な栄養バランスを考えるのは大変です。
お弁当では、「主食(ごはん・パン)」「主菜(肉・魚・卵)」「副菜(野菜)」の3つのグループが揃っているか、ざっくりと確認する程度で十分です。
例えば、「おにぎり(主食)」「唐揚げ(主菜)」「ブロッコリーとミニトマト(副菜)」といった組み合わせです。
これに果物をデザートとして加えれば、ビタミンの補給にもなります。
1週間単位でバランスが取れていれば良い、というくらいの気持ちでいると、精神的な負担も軽くなります。
お弁当箱の選び方で後片付けも楽になる

毎日のお弁当作りでは、調理だけでなく、帰宅後の「洗う」という作業も意外と負担になるものです。
お弁当箱の選び方を工夫することで、この後片付けの手間を軽減し、日々の家事を少しでも楽にすることができます。
洗いやすさを重視した形状と素材
お弁当箱を選ぶ際は、洗いやすさを最優先に考えましょう。
角が丸い形状のものは、四角いものに比べて汚れが隅に溜まりにくく、スポンジで洗いやすいです。
また、仕切りが一体成型されているタイプや、そもそも仕切りが少ないシンプルな構造のものを選ぶと、洗うパーツが減って楽になります。
パッキンは、カビや汚れが付きやすい部分です。
蓋とパッキンが一体になっているタイプを選ぶと、毎回取り外して洗う手間が省け、付け忘れによる汁漏れの心配もなくなるため、非常におすすめです。
素材は、汚れや匂いが付きにくいステンレス製や、食洗機対応のプラスチック製などが人気です。
子供の年齢に合ったサイズを選ぶ
お弁当箱の容量が子供の食べる量に合っていないと、食べきれずに残してしまったり、逆に足りなかったりすることがあります。
子供の成長に合わせた適切なサイズを選ぶことも大切です。
| 学年 | 容量の目安 |
|---|---|
| 小学校低学年(1~3年生) | 450ml ~ 600ml |
| 小学校高学年(4~6年生) | 600ml ~ 850ml |
これはあくまで一般的な目安です。お子さんの食欲や活動量に合わせて調整してください。
食べきれる量の美味しいお弁当と、後片付けが楽なお弁当箱は、ワーママのお弁当作りを支える両輪と言えるでしょう。
-
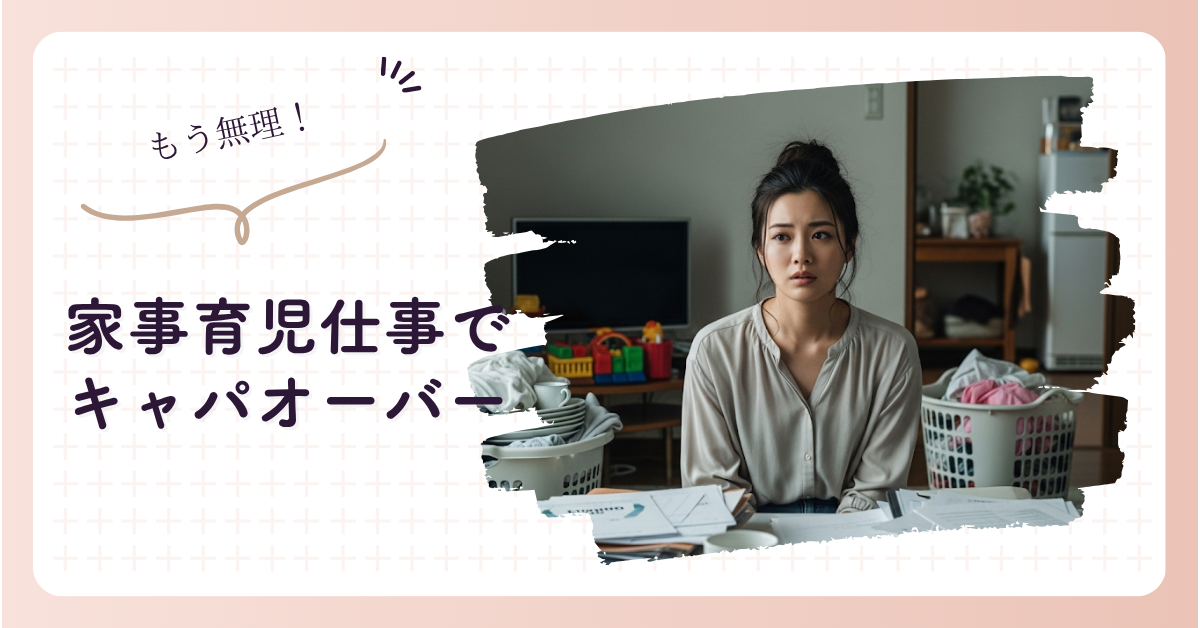
家事育児仕事でキャパオーバー!もう無理と感じたら
続きを見る
楽しく続けるワーママの学童のお弁当術

この記事で解説してきた、ワーママが学童のお弁当作りを無理なく、そして楽しく続けるためのポイントを以下にまとめます。
ま と め
- ワーママのお弁当作りがしんどいのは時間的・精神的プレッシャーが原因
- 完璧を目指さず自分を責めないことが最も大切
- 他の家庭のお弁当と自分のものを比較しない
- 手抜きは悪いことではなく賢い戦略と捉える
- ママの心の余裕が子供の安定につながる
- 夏場など長期休みは食中毒予防のための衛生管理を最優先する
- おかずは調理後に完全に冷ましてから詰める
- 保冷剤や保冷バッグを必ず活用する
- 傷みやすい生野菜や手作りマヨネーズ和えは避ける
- 週末の作り置きや冷凍ストックで平日の朝を楽にする
- 冷凍食品や市販の惣菜を罪悪感なく上手に活用する
- コンビニ商品はあと一品欲しい時の強い味方になる
- 焼きそばやオムライスなどの一品弁当を取り入れマンネリを防ぐ
- お弁当箱の選び方一つで帰宅後の後片付けが楽になる
- 洗いやすさを重視しパッキン一体型の弁当箱も検討する

