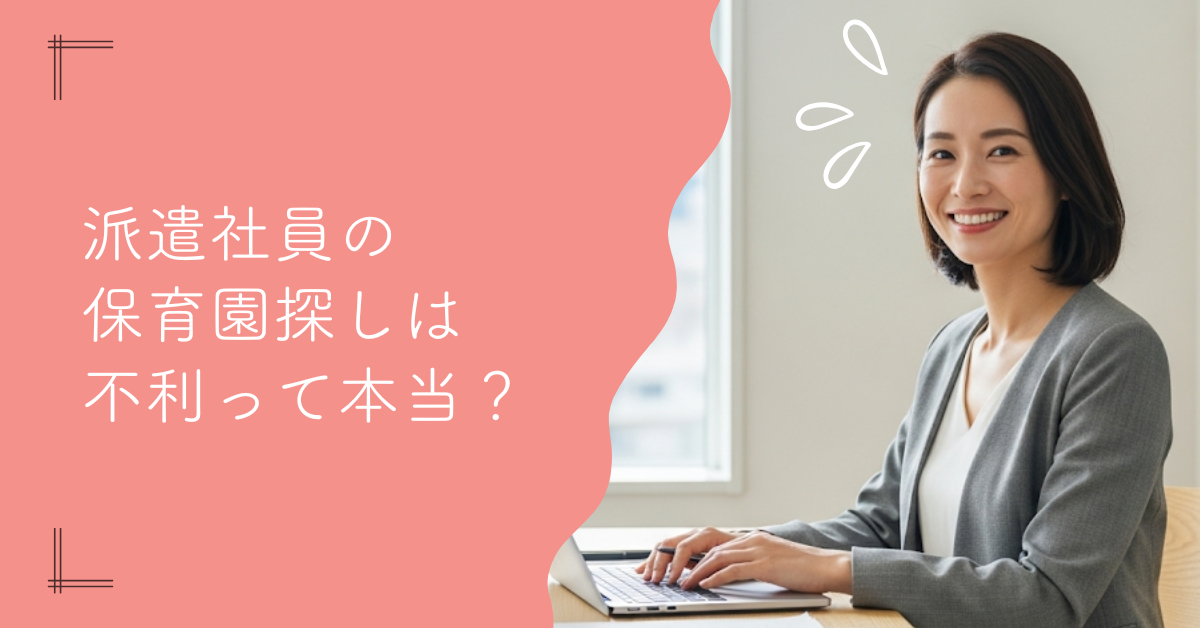※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
派遣社員として働きながらの子育てを考えたとき、「派遣社員の保育園利用は難しいのでは?」という不安を感じる方は少なくありません。
派遣社員の保育園探しが不利と言われることもありますが、正しい知識と準備があれば、入園は十分に可能です。
しかし、手続きの過程で提出する派遣社員の保育園用の就労証明書や、勤務先の書き方で迷う場面も出てきます。
また、入園後に考えられる保育園からの急な呼び出しへの対応、さらには契約更新のタイミングによっては保育園を退園になるリスクなど、特有の課題があるのも事実です。
この記事では、派遣社員として保育園の入園を目指す方が抱える疑問や不安を解消し、保活を成功させるための具体的な方法を網羅的に解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
記事のポイント
- 派遣社員が保育園探しで不利と言われる本当の理由
- 就労証明書の正しい依頼方法と記入時の注意点
- 入園後に発生しうる問題とその具体的な対処法
- 保活を成功に導くための実践的なポイント
派遣社員の保育園入園を成功させる方法

- 派遣社員の保育園利用は就労証明書から
- 派遣社員の保育園申請での勤務先の書き方
- 派遣社員の保育園探しが不利と言われる理由
- 保育園入園までの基本的な流れ
- 保活を成功させるためのポイント

点数が足りなくて泣きそうになったり、就労証明書もらうのに気を使ったり…。
この記事、当時の自分に読ませてあげたいくらい的確だわ。
ほんと、ワーママは毎日が戦いだよね!
派遣社員の保育園利用は就労証明書から
派遣社員が保育園の申し込みをする上で、絶対に必要となる書類が就労証明書です。
これは、保護者が就労していることにより家庭での保育が困難であることを証明するための公的な書類で、自治体が保育の必要性を判断する際の重要な基準となります。
就労証明書の役割と重要性
就労証明書には、勤務日数、勤務時間、契約期間、職種といった具体的な就労状況が記載されます。
自治体は、この情報をもとに各家庭の状況を点数化(指数化)し、点数の高い世帯から優先的に入園を決定します。
つまり、就労証明書の内容が、保育園の選考結果を大きく左右すると言っても過言ではありません。
発行元は派遣先ではなく「派遣元」
ここで最も注意すべき点は、就労証明書の発行を依頼する相手です。
派遣社員の場合、実際に働いている職場(派遣先企業)ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社(派遣元)に発行を依頼します。
派遣先企業に直接お願いしても発行はしてもらえないため、必ずご自身の登録している派遣会社の担当部署、多くは人事部や労務部に連絡を取りましょう。
発行を依頼するタイミング
就労証明書は、派遣会社に登録しただけの状態では発行できません。
派遣先が決定し、雇用契約が結ばれた後でなければ、具体的な就労条件を記載できないためです。
保育園の申込期間から逆算し、早めに派遣先を決定させ、すぐに発行依頼ができるように準備を進めることが大切です。
発行には数日から1週間程度かかることもあるため、自治体の提出期限に間に合わなくなることがないよう、余裕を持ったスケジュールを心がけてください。
派遣社員の保育園申請での勤務先の書き方
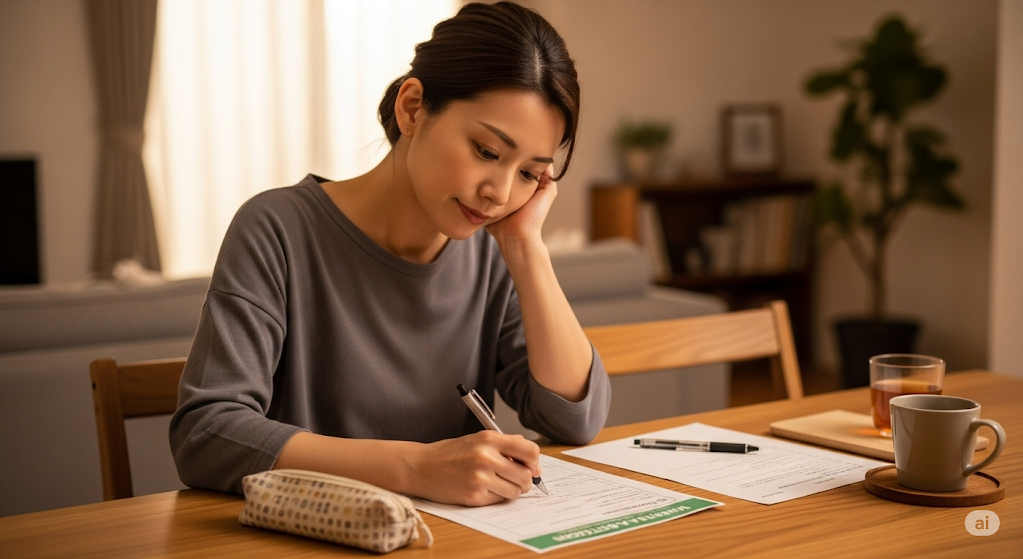
保育園の申込書類や関連書類で「勤務先」を記入する欄が出てきた際、派遣社員は「派遣元」と「派遣先」のどちらを書けばよいのか迷うことがよくあります。
これは非常に重要なポイントであり、間違えると手続きが滞る可能性もあるため、正しく理解しておく必要があります。
書類上の雇用主は「派遣元」
原則として、法的な雇用主は派遣会社(派遣元)です。
給与の支払いや社会保険の手続きはすべて派遣元が行っています。
そのため、保育園の入園申込時に提出する就労証明書に記載される勤務先(事業主)は、派遣元の情報となります。
自治体への正式な申請書類においても、勤務先としては派遣元の会社名、住所、電話番号を記入するのが基本です。
緊急連絡先は「派遣先」が望ましい
一方で、子どもが保育園で体調を崩したり、怪我をしたりした場合の緊急連絡先については、事情が異なります。
この場合、連絡がいくのは実際に保護者が働いている場所であるべきです。
そのため、緊急連絡先として保育園に伝えるのは、派遣先企業の電話番号が適切です。
ただし、派遣先によっては、個人の事情に関する外部からの電話を取り次がない方針の企業もあります。
このような事態を避けるため、事前に派遣元の担当者と派遣先の責任者に相談し、「保育園からの緊急連絡があるかもしれない」という点を伝え、スムーズな連絡が可能かを確認しておくと、いざという時に安心です。
この確認と情報共有が、円滑な保育園生活の鍵となります。
派遣社員の保育園探しが不利と言われる理由
「派遣社員の保活は不利」という声を耳にすることがありますが、これは雇用形態そのものではなく、派遣社員という働き方の特性に起因する部分が大きいです。
不利とされる主な理由は、保育園の入園選考で用いられる「指数(点数)」が上がりにくい傾向にあるためです。
指数が低くなりやすい傾向
多くの自治体では、保護者の就労状況を点数化して入園の優先順位を決定します。
その際、勤務時間や日数が重要な評価項目となります。
| 就労状況の例(東京都練馬区の場合) | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上・1日あたり8時間以上の就労 | 40点 |
| 月16日以上19日以下・1日あたり8時間以上の就労 | 37点 |
上記は一例ですが、このようにフルタイム勤務が最も高い点数に設定されていることが一般的です。
派遣社員の場合、希望する働き方や紹介される仕事によっては勤務時間が短くなるケースがあり、結果として正社員のフルタイム勤務者と比較して指数が低くなってしまうことがあります。
雇用の継続性が評価されにくい
また、派遣契約は数ヶ月単位での更新が多いため、「雇用の継続性・安定性」という観点でも評価が伸び悩むことがあります。
育児休業からの復帰を予定している場合でも、復帰先の派遣先がまだ決まっていないと「求職中」と同じ扱いになり、指数が大幅に下がってしまうリスクも考えられます。
自治体によっては、内定が出ていても、入園月までに復職先が決まらないと内定が取り消される場合もあるため、注意が必要です。
-
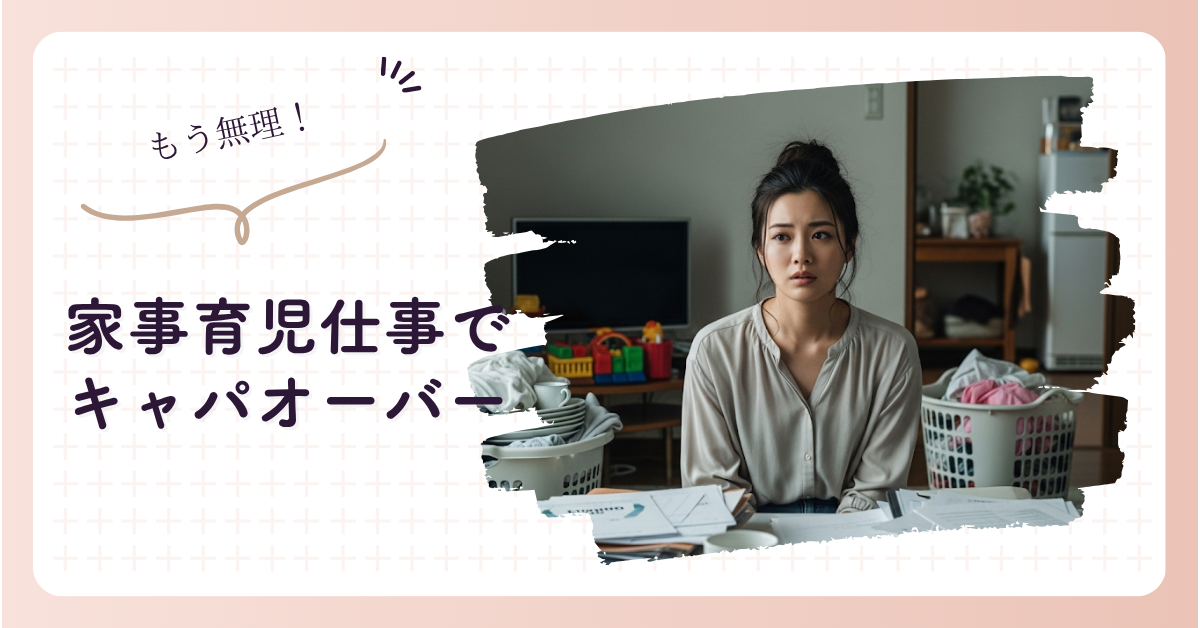
家事育児仕事でキャパオーバー!もう無理と感じたら
続きを見る
保育園入園までの基本的な流れ

派遣社員が保育園の入園を目指す際の基本的な流れを理解し、計画的に進めることが成功への近道です。
全体のプロセスを把握しておきましょう。
- 情報収集と派遣会社への登録 まずは、お住まいの自治体の保育園の利用案内や申込時期、必要書類などを徹底的に情報収集します。同時に、複数の派遣会社に登録し、子育てと両立しやすい仕事の希望条件を伝えておきます。
- 派遣先の決定と雇用契約 派遣会社から仕事の紹介を受け、派遣先を決定します。保育園の申込に間に合わせるためには、このステップを早めに完了させることが肝心です。派遣先が決まったら、派遣元と雇用契約を結びます。
- 就労証明書の取得 雇用契約が完了したら、速やかに派遣元に就労証明書の発行を依頼します。自治体指定の様式がある場合は、自分で様式を準備し、保護者記入欄を埋めてから依頼するとスムーズです。
- 保育園への申し込み 就労証明書をはじめ、住民票や所得証明書など、自治体から求められる全ての書類を揃え、申込期間内に提出します。希望する保育園は、通える範囲でできるだけ多く記入するのが一般的です。
- 選考結果の通知 自治体による選考が行われ、結果が通知されます。内定した場合は、その後の手続き(面談や健康診断など)に進みます。
- 入園決定と契約 すべての手続きが完了したら、保育園と正式な入園契約を結びます。入園後は、慣らし保育を経て、本格的な通園が始まります。
保活を成功させるためのポイント
指数が上がりにくいとされる派遣社員でも、いくつかのポイントを押さえることで、保育園入園の可能性を高めることができます。
戦略的に保活を進めましょう。
選択肢を最大限に広げる
希望する保育園を自宅の近くだけに絞ってしまうと、競争率が高く入園が難しくなることがあります。
自宅からの距離だけでなく、通勤経路の途中にある駅の周辺など、少し視野を広げて通える範囲の保育園をリストアップすることが大切です。
認可保育園だけでなく、認可外保育園や小規模保育園、新設の保育園も選択肢に含めることで、入園のチャンスは格段に広がります。
認可外保育園の活用と補助金制度
認可外保育園は、認可保育園に比べて保育料が高いイメージがありますが、自治体によっては補助金制度が設けられています。
この制度を活用すれば、実質的な負担額を認可保育園と同程度に抑えられる場合もあります。
まずは認可保育園の選考結果を待つ間の「滑り止め」として申し込み、もし入園できれば、認可園への転園を目指しながら働き始めるという選択も可能です。
ベビーシッターサービスの利用による加点
一部の自治体では、ベビーシッターサービスを定期的に利用している実績があると、選考の際の指数に「調整指数」として加点される場合があります。
「月48時間以上の利用」など条件はありますが、どうしても指数が足りない場合には、このような制度の活用も一つの有効な手段と考えられます。
希望する保育園を自宅の近くだけに絞ってしまうと、競争率が高く入園が難しくなることがあります。
自宅からの距離だけでなく、通勤経路の途中にある駅の周辺など、少し視野を広げて通える範囲の保育園をリストアップすることが大切です。
認可保育園だけでなく、認可外保育園や小規模保育園、新設の保育園も選択肢に含めることで、入園のチャンスは格段に広がります。
具体的な施設は、公的な情報検索サイト「ここdeサーチ」で探すことができます。
派遣社員が保育園入園後に知るべき注意点

- 派遣先が変わった場合の手続き
- 定期的な就労状況の確認と提出書類
- 派遣社員への保育園からの緊急連絡先は?
- 保育園は派遣社員だと退園になるケースも
- 派遣社員でも保育園のポイントを押さえよう

せっかく保育園入れても、派遣だと契約更新の時期はいつも「退園になったらどうしよう」って不安だった。
本当に生きた心地がしなかったな…。
入園後も気が抜けないのが派遣ワーママの辛いとこだよね。
派遣先が変わった場合の手続き
派遣社員は契約期間ごとに派遣先が変わる可能性があるため、保育園入園後も勤務先に関する手続きが必要になる場面が出てきます。
これらの手続きを怠ると、最悪の場合、退園につながることもあるため、迅速な対応が求められます。
派遣先が変更になった場合、まずはお住まいの自治体の保育課などに連絡し、勤務先が変更になった旨を届け出る必要があります。
多くの場合、「変更届」といった書類の提出を求められます。
同時に、新しい派遣先の就労条件を記載した就労証明書を、改めて派遣元に発行してもらい、提出し直さなければなりません。
また、前述の通り、保育園には緊急連絡先として派遣先の情報を伝えているはずです。
派遣先が変われば当然、その情報も更新する必要があります。
新しい職場の住所や電話番号、直通の内線番号などを速やかに保育園の担任の先生や事務室に伝え、常に最新の状態にしておくことを心がけてください。
定期的な就労状況の確認と提出書類

保育園の在園資格を維持するためには、「継続して保育の必要性があること」を証明し続けなければなりません。
このため、多くの自治体では、年に1回から2回(半年に一度など)の頻度で、全在園児の保護者を対象に就労状況の確認(現況確認)を実施しています。
この現況確認の際には、入園申込時と同様に、最新の就労状況を記載した就労証明書の提出が求められます。
派遣社員の場合も、このタイミングで派遣元に就労証明書の発行を依頼し、期日までに必ず提出する必要があります。
もし、この書類を提出しなかったり、提出した書類の内容が在園基準(例:月間の最低就労時間など)を満たしていなかったりすると、保育の必要性が認められないと判断され、退園勧告を受ける可能性があります。
派遣の契約更新のタイミングと現況確認の時期が重なる場合は、特に注意が必要です。
派遣社員への保育園からの緊急連絡先は?
子どもは保育園で過ごす中で、急に熱を出したり、思いがけない怪我をしたりすることがあります。
そのような緊急時に、保育園から保護者へ速やかに連絡が取れる体制を整えておくことは、非常に大切です。
連絡先は「派遣先」を伝えるのが基本
前述の通り、保育園に伝える緊急連絡先は、実際に日中働いている場所である「派遣先」の電話番号が最も適切です。
派遣元の電話番号を伝えても、担当者不在などで連絡がスムーズにつかず、対応が遅れてしまう可能性があるからです。
事前の情報共有が鍵
ただし、派遣先企業によっては、セキュリティの観点から私用の電話の取り次ぎを禁止している場合もあります。
そのため、入園時や派遣先が変わった際には、必ず派遣先の直属の上司や部署の責任者に「子どもを保育園に預けており、緊急時には保育園から職場に連絡が入る可能性がある」ということを事前に伝えておきましょう。
こうして事前に共有しておくことで、万が一の際にも周囲の理解と協力を得やすくなり、スムーズな対応が可能になります。
派遣元の担当者にも、この点を伝えておくとさらに安心です。
保育園は派遣社員だと退園になるケースも
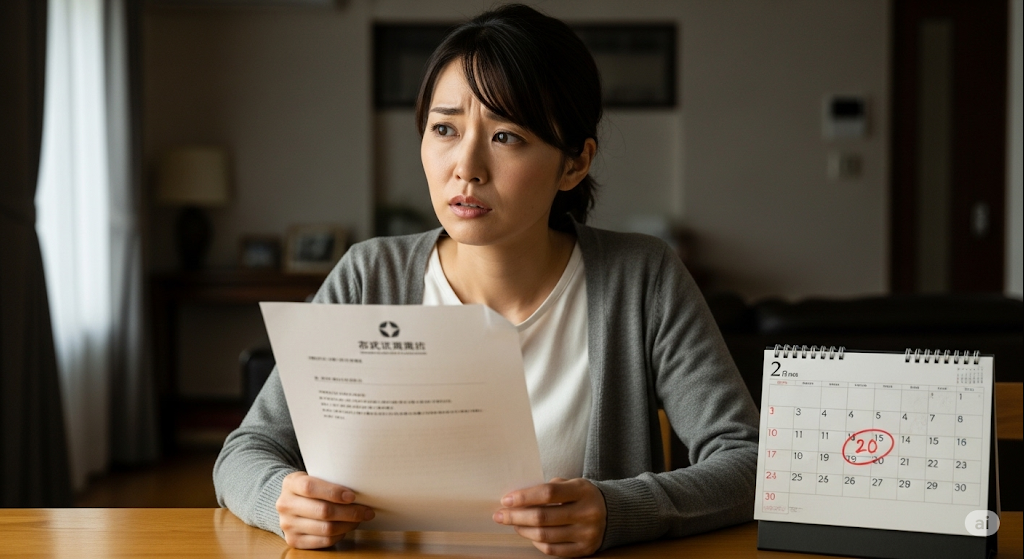
派遣社員という働き方は、契約期間が定められているため、正社員と比較して雇用の安定性という面で課題を抱えることがあります。
この特性が、保育園の在園資格に影響を与える可能性を理解しておくことが不可欠です。
契約終了と「求職期間」
派遣契約が満了し、次の派遣先がすぐに決まらない場合、保護者は一時的に「無職」または「求職中」の状態になります。
保育の必要性の根拠である「就労」の事実がなくなってしまうため、原則としては退園の対象となります。
しかし、多くの自治体では、すぐに退園を求めるのではなく、再就職のための猶予期間を設けています。
この期間は自治体によって異なりますが、おおむね「3ヶ月」とされることが一般的です。
この猶予期間内に新しい仕事を見つけ、就労を開始したことを証明できれば、継続して保育園を利用することができます。
猶予期間内に次の仕事を見つける重要性
この3ヶ月という期間は、決して長くはありません。
そのため、現在の契約が満了に近づいてきたら、早めに派遣元の担当者に次の仕事を探している旨を伝え、積極的に仕事の紹介を依頼することが重要です。
契約が終了してから探し始めるのではなく、終了前から次の仕事を見据えて動く計画性が、子どもの保育環境を守ることにつながります。
もし期間内に就職が決まらなければ、退園せざるを得なくなるため、この点は強く意識しておく必要があります。
-

共働き子育ては無理ゲー?その現実と乗り越えるヒント
続きを見る
派遣社員でも保育園のポイントを押さえよう

これまで解説してきたように、派遣社員の保育園利用には特有の注意点がありますが、制度を正しく理解し、計画的に行動することで、多くの課題は乗り越えられます。
最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
ま と め
- 派遣社員でも就労実態があれば保育園の利用は可能
- 保育園の申請に必須の就労証明書は派遣元(派遣会社)に依頼する
- 就労証明書は派遣先が決まり雇用契約を結んでから発行される
- 発行には時間がかかるため早めに依頼することが大切
- 申込書類の勤務先欄には原則として派遣元の情報を記入する
- 保育園への緊急連絡先は実際に働く派遣先の情報を伝える
- 派遣社員の保活が不利と言われるのは選考の指数が低くなりやすいため
- 勤務時間の短さや契約の不安定さが指数の低下につながることがある
- 保活成功には通える範囲で希望園の選択肢を広げることが鍵
- 認可外保育園や小規模保育園も併願して検討する
- 自治体の認可外保育園への補助金制度も確認する
- 入園後に派遣先が変わった場合は自治体と保育園の両方に届出が必要
- 年に数回、就労状況を確認するための就労証明書の再提出が求められる
- 契約が終了し無職になると退園のリスクがある
- 多くの自治体では再就職のために3ヶ月程度の猶予期間が設けられている