※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
「産後すぐ働きたい」と考えているものの、具体的に産後、最短でいつから働けるのか、出産後、仕事復帰がきついのではないか、仕事復帰と母乳育児の両立は可能なのかといった疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、出産後、仕事復帰を自営業で行う場合の注意点や、出産前に準備すること、子どもの預け先、産後に受けられる支援について知りたいという方もいるかもしれません。
出産後、仕事復帰の平均期間も気になるところです。
この記事では、そのようなあなたの疑問に寄り添い、産後の仕事復帰に関する不安を解消できるよう、網羅的に解説していきます。
記事のポイント
- 産後の仕事復帰の時期と条件がわかる
- 仕事と育児の両立における課題と対策がわかる
- 産後の働き方の選択肢と準備がわかる
- 利用できる支援や制度について理解できる
目次
産後すぐ働きたいあなたへ:最短での仕事復帰を解説

- 産後、最短でいつから働ける?
- 出産後、仕事復帰がきついと感じるとき
- 出産後、仕事復帰と母乳育児の両立
- 出産後、仕事復帰における自営業のケース

私なんて一番下の子の時でも、しばらくは自分の体調を戻すので精一杯だったもん。
今の時代は働き方も多様化してるんだろうけど、体力も気力も尊敬しかないわ…。
産後、最短でいつから働ける?
産後、女性が法的に就業できる最短の期間は、出産後6週間を経過した時点からと言えます。
これは労働基準法によって定められており、出産後8週間は原則として就業が制限されています。
ただし、産後6週間を経過した場合、本人が希望し、かつ医師が就業可能と認めた場合に限り、例外的に働くことが可能になります。
この制度は、母体の回復を促すために設けられています。
特に、出産直後は体力的な消耗が大きく、ホルモンバランスも大きく変化するため、無理な労働は母体に大きな負担をかける可能性があります。
そのため、たとえ本人が早く働きたいと望んだとしても、医師の許可がなければ就業できない仕組みになっているのです。
企業に所属している場合、産前産後休業という制度が適用されますが、個人事業主やフリーランスとして働いている場合は、これらの法律上の制約が直接的に適用されないため、自身の体調と相談しながら就業時期を決定することになります。
いずれにしても、母子の健康を最優先に考え、慎重に復帰時期を検討することが大切です。
出産後、仕事復帰がきついと感じるとき

出産後の仕事復帰は、多くの女性にとって精神的、肉体的に大きな負担となる場合があります。
特に、産後6週間を経過してすぐに仕事に復帰する選択をした場合、その負担はさらに大きくなる傾向が見られます。
具体的には、子どもの体調不良への対応、夜泣きによる慢性的な寝不足、そして母乳育児を継続している場合の胸の張りや授乳時間の確保といった課題が挙げられます。
これまでの生活が一変し、育児と仕事の両立に慣れるまでは、心身の不調を感じやすい時期と言えるでしょう。
例えば、子どもの急な発熱で仕事を休まなければならなかったり、夜間の授乳で十分な睡眠が取れなかったりすることで、仕事への集中力が低下する可能性もあります。
また、母乳育児を継続している場合は、職場での搾乳場所の確保や、搾乳時間の調整が必要となり、これもまたストレスの原因になることがあります。
これらの状況は、仕事へのモチベーションを低下させたり、疲労の蓄積により体調を崩しやすくなる原因となることが考えられます。
そのため、復帰時期を決定する際には、自身の体調や子どもの状況を考慮し、パートナーや職場と十分に話し合うことが大切です。
無理をして早期に復帰することよりも、長期的に安定して働き続けられる環境を整えることに重きを置くべきでしょう。
出産後、仕事復帰と母乳育児の両立
出産後、仕事復帰と母乳育児の両立は、事前の準備と周囲の協力が不可欠です。
職場復帰後も母乳育児を継続するためには、いくつかの工夫が必要となります。
まず、職場との連携が挙げられます。搾乳の許可を得ることはもちろん、搾乳場所の確保や休憩時間の調整などについて、事前に相談し、協力体制を築くことが求められます。
職場によっては、休憩室や空き会議室などを搾乳場所として提供してくれる場合もありますが、トイレの個室で搾乳する場合は、清潔を保つための工夫を凝らすことが大切です。
次に、保育園との連携も欠かせません。搾乳した母乳を預かってもらえるか、冷凍保存が可能かなどを確認することが重要です。
哺乳瓶やミルクに慣れていない赤ちゃんの場合、仕事復帰の1〜2ヶ月前から哺乳瓶やミルクに慣れる練習を始めると良いでしょう。
保育園での授乳方法についても、事前に確認しておく必要があります。
搾乳と保存に関して言えば、職場では1〜2回搾乳できるのが理想とされます。
搾乳方法には手絞り、手動搾乳器、電動搾乳器などがあり、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
搾乳した母乳は滅菌冷凍パックに入れ、冷凍庫で保存します。
持ち運びの際は、保冷バッグに保冷剤を入れて、カチカチに凍らせた状態で運ぶことで、品質を維持できます。
母乳育児を継続する上での注意点としては、乳房の張りや痛み、そして乳腺炎のリスクがあります。
搾乳が追いつかないと乳房が張ったり、痛みが生じたりすることがあるため、搾乳のタイミングや頻度を調整し、必要に応じて冷やすなどの対処をすることをおすすめします。
乳腺炎を予防するためには、清潔な環境で搾乳し、乳房を清潔に保つことが非常に大切です。
冷凍保存した母乳は、解凍後は早めに使い切り、再冷凍は避けるようにしてください。
母乳の分泌量や授乳頻度、労働時間によって継続方法は異なりますので、困ったことがあれば助産師に相談することも検討してください。
出産後、仕事復帰における自営業のケース

出産後、自営業として仕事復帰する場合、会社員とは異なる特性と注意点があります。
会社員の場合、労働基準法により産後6週間の就業制限があり、原則として産後8週間は就業が制限される一方で、自営業やフリーランスはこれらの法的な制約が直接的に適用されません。
そのため、自身の体調や事業の状況に合わせて、比較的柔軟に復帰時期を調整できるというメリットがあります。
しかしながら、これは同時に、自身の体調管理や育児との両立において、より一層の自己管理が求められることを意味します。
例えば、体調が完全に回復しないうちに無理をして働くことで、体調を崩してしまうリスクも考えられます。
また、事業の性質によっては、クライアントとの調整や納期管理など、産前と変わらない業務量をこなすことが求められる場合もあります。
自営業として復帰を検討する際は、まずご自身の身体的な回復状況を最優先に考え、医師や助産師の意見も参考にしながら慎重に判断することが大切です。
また、育児の協力体制を事前に構築しておくことも非常に重要です。
パートナーとの役割分担を明確にし、必要であればベビーシッターや一時保育の利用も視野に入れるべきでしょう。
さらに、事業の性質上、急な対応が必要となる場合に備え、あらかじめ緊急時の対応フローを確立しておくことも役立ちます。
例えば、連絡が取りにくい時間帯があることをクライアントに事前に伝えておく、あるいは信頼できる代行者を見つけておくなどの準備が考えられます。
このように、自営業での復帰は自由度が高い反面、自己責任で準備と対策を進める必要があると言えます。
-

妊娠中も暇を持て余さず働きたい!安全な仕事選びガイド
続きを見る
産後すぐ働きたい女性が知るべき復帰準備と支援
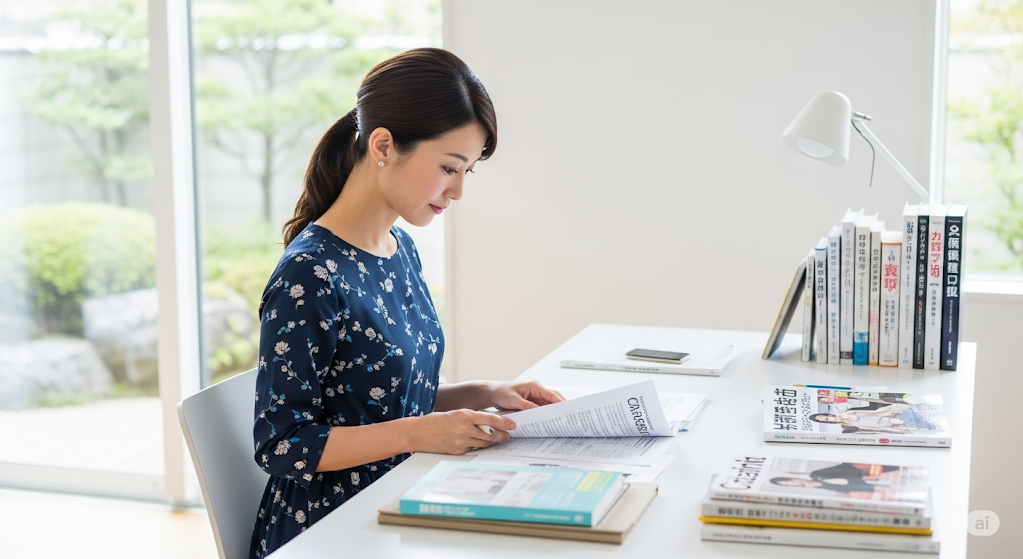
- 出産前に準備すること
- 子どもの預け先を確保するポイント
- 産後に受けられる支援制度
- 出産後、仕事復帰の平均期間
- 産後に働きやすい仕事スタイル
- パートナーと協力し準備を

特に夫との協力体制はマジで大事!
うちは夫が協力的だったから3人育てられたけど、産後はこっちもホルモンバランスで不安定になるし、事前に色々話し合っておかないと絶対ケンカになる(笑)
制度も大事だけど、まずは夫婦のチーム作りからだよね。
出産前に準備すること
出産後にスムーズに仕事復帰できるよう、出産前にいくつかの準備をしておくことが非常に重要です。
まず、パートナーとのライフプランを具体的に立てることが挙げられます。
産後すぐに働きたいと考えている場合、家事や育児の分担は不可欠であり、これらをパートナーと十分に話し合い、協力体制を築いておくことで、産後のストレスや疲労による体調不良を防ぐことにつながります。
なぜ早く仕事に復帰したいのか、どのような生活を送りたいのかを明確にし、復帰後の役割分担を事前に決めておくことは、どちらか一方に負担が偏るのを防ぐ上で大切です。
また、パートナーが育児休業を取得可能であれば、日中の子どもの面倒を見てもらえるため、産後すぐでも働きやすくなるでしょう。
次に、産後の働き方について、産休に入る前に上司と話し合いをしておくことも重要です。
企業によって産後に利用できる制度や福利厚生が異なるため、時短勤務やリモートワーク、フレックスタイム制などの利用が可能かを確認し、ライフプランに合わせて申請しておくと良いでしょう。
産後すぐに仕事復帰したいという意思を伝えておくことで、産休明けの配属先について考慮してもらえる可能性もあります。
出産後は産前と同じような働き方が難しくなることが多いため、どのようなキャリアを築きたいのかを上司に伝えておくことは、自身のキャリアプランを進める上で重要なステップとなります。
さらに、産後に受けられる支援を事前にリサーチしておくことも欠かせません。
公的な支援、民間の支援、そして身内からの支援など、多岐にわたる選択肢があります。
例えば、子どもが病気の際に利用できる病児保育やベビーシッターサービス、これらの一部を補助してくれる自治体の制度などです。
両親や兄弟など、子どもの急な体調不良などで出勤ができない場合に頼れる親族がいるのであれば、事前に相談しておくと安心です。
これらの支援を事前に把握し、利用する可能性のあるものについては準備を進めておくことで、産後の仕事復帰をよりスムーズに進めることができるでしょう。
子どもの預け先を確保するポイント

産後すぐに働くことを考えている場合、子どもの預け先を妊娠中から確保しておくことが極めて重要になります。
労働基準法により産前産後休暇が義務付けられていることから、多くの保育園では生後2ヶ月(生後57日)から入園が可能となっています。
しかし、出産後6週間以内に仕事復帰を考えている場合は、その間の2週間ほどは保育園以外の預け先を探す必要がありますので、この点も踏まえて準備を進めることが大切です。
保育園に子どもを預けることを検討している場合、出産前に0歳クラスの空き状況を自治体に問い合わせておくのが賢明です。
地域によっては待機児童問題が深刻な場合もあり、希望する時期に希望する保育園に入園できるとは限りません。
そのため、複数の候補を検討したり、認可外保育施設やベビーシッターサービスも視野に入れるなど、多角的に情報収集を行うことが大切です。
預け先を検討する際には、以下の点に注目すると良いでしょう。
| 項目 | 確認すべき点 |
|---|---|
| 開園時間 | 仕事の勤務時間と送迎時間を考慮した開園時間か |
| 延長保育 | 残業や急な用事に対応できる延長保育があるか |
| 土日祝の預かり | 平日以外の預かりが必要な場合に利用できるか |
| 病児保育 | 子どもが体調を崩した際に預かってもらえる制度があるか |
| 費用 | 毎月の保育料や延長料金、その他費用が予算内か |
| 立地 | 自宅や職場からのアクセスが良いか |
| 園の雰囲気 | 園の教育方針や保育士の対応が希望と合っているか |
これらの点を考慮し、見学や説明会に参加して、実際に施設の雰囲気や保育内容を確認することも大切です。
また、子どもの入園準備には時間と手間がかかるため、早めに情報収集と手続きを始めることを強くお勧めします。
産後に受けられる支援制度
産後に仕事復帰を考える際、利用できる支援制度を事前に知っておくことは非常に役立ちます。
これらの支援は、仕事と育児の両立をスムーズに進める上で大きな助けとなるでしょう。
公的な支援としては、育児休業給付金が挙げられます。
これは、育児休業中に収入の一部を補償してくれる制度であり、生活の安定に寄与します。
また、育児休業期間中の社会保険料が免除される制度もあります。
これらの制度は、経済的な不安を軽減し、育児に専念できる期間を確保する上で重要です。
自治体によっては、独自の支援制度を設けている場合もあります。
例えば、ベビーシッターの利用料金の一部を補助してくれる制度や、一時預かり事業、病児保育の利用支援などです。
これらの情報は、お住まいの市区町村の窓口やウェブサイトで確認することができます。
積極的に情報収集を行い、利用可能な制度を把握しておくことが推奨されます。
民間の支援サービスも多様化しています。
病児保育サービスやベビーシッターサービスは、子どもの急な発熱や体調不良で保育園に預けられない場合に非常に心強い存在となります。
また、家事代行サービスを利用することで、家事の負担を軽減し、育児や仕事に集中できる時間を増やすことも可能です。
これらのサービスは有料ですが、その費用を上回るメリットが得られることも少なくありません。
さらに、身内の支援も忘れてはなりません。
両親や兄弟など、子どもの急な体調不良時や、仕事が忙しい時に手助けしてくれる親族がいる場合は、事前に協力をお願いしておくことが大切です。
このように、公的、民間、そして身内からの支援を多角的にリサーチし、利用できるものは積極的に活用することで、産後の仕事復帰をより円滑に進め、心身の負担を軽減することができるでしょう。
出産後、仕事復帰の平均期間

出産後、女性が仕事復帰するまでの平均期間は、一般的に1年~1年半程度が目安とされています。
これは、多くの女性が産後休暇に加えて育児休業制度を利用するためです。
特に、厚生労働省の調査結果からも、この傾向が明らかになっています。
具体的に見ていくと、出産後8週間の産後休暇を経て、子どもが1歳になるまで育児休業を取得し、そのタイミングで復帰するケースが多いと言えます。
保育園に入れないなどの事情がある場合は、最長で2歳まで育児休業を延長できるため、復帰時期は個々の状況によって変動する可能性も考えられます。
正社員として勤務していた女性の場合、第一子出産後も育児休業を利用して正社員としての就業を継続している人は約7割に上ります。
これは、育児休業制度が女性のキャリア継続を支える上で重要な役割を果たしていることを示しています。
女性の育児休業取得期間で最も多いのは12~18ヶ月未満で、全体の約3割を占めています。
この期間は、子どもの成長を間近で見守りながら、仕事復帰に向けて準備を進める上で適切な期間であると考える人も少なくありません。
もちろん、職場環境や家庭状況によっては、生後6ヶ月で復帰する人もいれば、さらに長く育児休業を取得する人もいます。
復帰時期を決定する際には、育児休業給付金や社会保険料の扱い、そして何よりも子どもの預け先が確保できるかなど、様々な要素を総合的に考慮することが大切です。
復帰後は、仕事と育児の両立に慣れるまで時間がかかることもありますので、周囲のサポートや利用可能な制度を積極的に活用していくことが成功の鍵となります。
産後に働きやすい仕事スタイル
産後に働きやすい仕事スタイルは多岐にわたりますが、自身の状況や希望に合わせて選択することが大切です。
まず、在宅ワークが挙げられます。
自宅で仕事ができるため、子どもの急な体調不良などにも対応しやすく、育児中の女性にとって非常に働きやすいスタイルと言えます。
WebデザイナーやWebライター、Webエンジニア、カスタマーサポートなど、様々な職種で在宅ワークが可能です。
次に、フレックスタイム制の利用も有効な選択肢です。
これは、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、始業・終業時刻や労働時間を労働者自身が決定できる制度です。
子どもの送迎時間に追われる心配が少なく、急な発熱などにも対応しやすいため、ワークライフバランスを整えやすいというメリットがあります。
また、事業所内に保育施設がある企業への転職も、産後に働きやすい環境を構築する一つの手段です。
子どもが近くにいるため安心して働くことができ、急な体調不良にもすぐに対応できるほか、就業中に母乳を飲ませるといったことも可能になります。
資生堂などの大手企業が事業所内保育所を設けている事例は、この働き方の利便性を示しています。
さらに、有給休暇の時間単位取得や子どもの看護休暇制度など、福利厚生が充実している企業を選ぶことも重要です。
これらの制度が利用できることで、予期せぬ育児トラブルにも対処しながら仕事を継続できます。
育児・介護休業法では、子どもが3歳に満たない子を養育する労働者が短時間勤務を利用できると定められていますが、会社によってはこれを延長できる制度もあります。
学校行事や子どもの誕生日などに休める特別休暇制度を設けている会社もあります。
育児中の従業員への理解がある社風も、働きやすさに大きく影響します。
いくら制度が充実していても、周囲の理解がなければ制度を使いづらい場合があります。
先輩社員に育児をしながら働いている人が多い、あるいは管理職や経営層に育児経験者がいる会社は、社風としても産後に働きやすいと言えるでしょう。
最後に、復職支援プログラムがある仕事も産後に働きやすい選択肢です。
育児休暇からの復職は、配置転換やしばらく離れていた仕事への復帰など、困難を伴うことも少なくありません。
段階的な職場復帰プランの支援や、育休取得者・復職者向けの研修、メンター制度、上司や人事との面談・相談ができる制度などは、スムーズな復職を助け、働き続ける上で大きな支えとなります。
これらの多様な働き方を検討し、自身の状況に最も適したスタイルを見つけることが、産後の仕事復帰を成功させる鍵となります。
パートナーと協力し準備を

産後すぐの仕事復帰を円滑に進めるためには、パートナーとの密な協力体制の構築が非常に重要です。
家事や育児は、出産後から一気にその量が増大するため、どちらか一方に負担が偏ってしまうと、心身のバランスを崩す原因になりかねません。
そのため、出産前に具体的なライフプランを共有し、お互いの役割分担についてじっくり話し合う時間を持つことをおすすめします。
たとえば、平日の朝の支度、保育園への送迎、夕食の準備、入浴、寝かしつけなど、日々のルーティンにおいて誰がどの役割を担うのかを明確にしておくことが大切です。
休日についても、家事や育児を分担し、お互いがリフレッシュできる時間を確保できるよう計画を立てると良いでしょう。
このように事前に話し合い、具体的な分担を決めておくことで、復帰後に発生しうるストレスや摩擦を軽減することが期待できます。
また、パートナーが育児休業を取得できる場合は、その可能性も積極的に検討してください。
パートナーが育児休業を取得することで、特に産後間もない時期の育児負担が軽減され、母親の身体的な回復を促し、精神的な安定にもつながります。
男性の育児休業取得は、近年増加傾向にあり、職場での理解も進みつつあります。
夫婦で協力して育児に取り組む姿勢は、子どもにとっても良い影響を与えるでしょう。
さらに、家事や育児の「手抜き」も視野に入れることも大切です。
完璧を目指すのではなく、時短家電の導入や、時には外部サービス(家事代行、ミールキットなど)の利用も検討することで、心と体にゆとりが生まれます。
育児も家事も、そして仕事も、すべてを一人で抱え込まず、パートナーや周囲の人々、そしてサービスを頼ることで、無理なく継続できる環境を整えていくことが、夫婦双方にとってより良い働き方を見つけることにつながるでしょう。
-

共働き子育ては無理ゲー?その現実と乗り越えるヒント
続きを見る
産後すぐ働きたいを叶えるために

産後すぐ働きたいという思いを叶えるためには、多角的な準備と、利用可能なあらゆる支援の活用が鍵となります。
出産後、女性が働くことができる最短期間は出産後6週間と定められていますが、この時期での仕事復帰は心身に大きな負担をかける可能性も伴います。
しかし、適切な準備と周囲のサポートがあれば、早期復帰も十分に実現可能です。
ま と め
- 産後最短で働けるのは出産後6週間経過時点であること
- 医師の許可と本人の希望があれば就業可能であること
- 出産後の仕事復帰は心身の負担が大きい可能性があること
- 子どもの体調不良や夜泣き、母乳育児が主な負担となること
- 母乳育児継続には職場や保育園との事前連携が不可欠であること
- 搾乳場所の確保や搾乳した母乳の保存方法を計画すること
- 自営業の場合、法的な就業制限はないが自己管理がより重要であること
- パートナーとのライフプランの共有と役割分担が重要であること
- 妊娠中から子どもの預け先確保の保活を始めること
- 会社員の場合、産休前に上司と働き方について話し合うこと
- 産後に受けられる公的・民間の支援制度を事前にリサーチすること
- 育児休業給付金や社会保険料免除などの公的支援があること
- ベビーシッターや病児保育など民間サービスも活用できること
- 平均的な仕事復帰期間は1年~1年半程度であること
- 在宅ワークやフレックスタイム制など柔軟な働き方を検討すること
- 事業所内保育施設や福利厚生が充実した企業も選択肢に入れること
- 育児中の従業員に理解のある社風かどうかも確認すること

