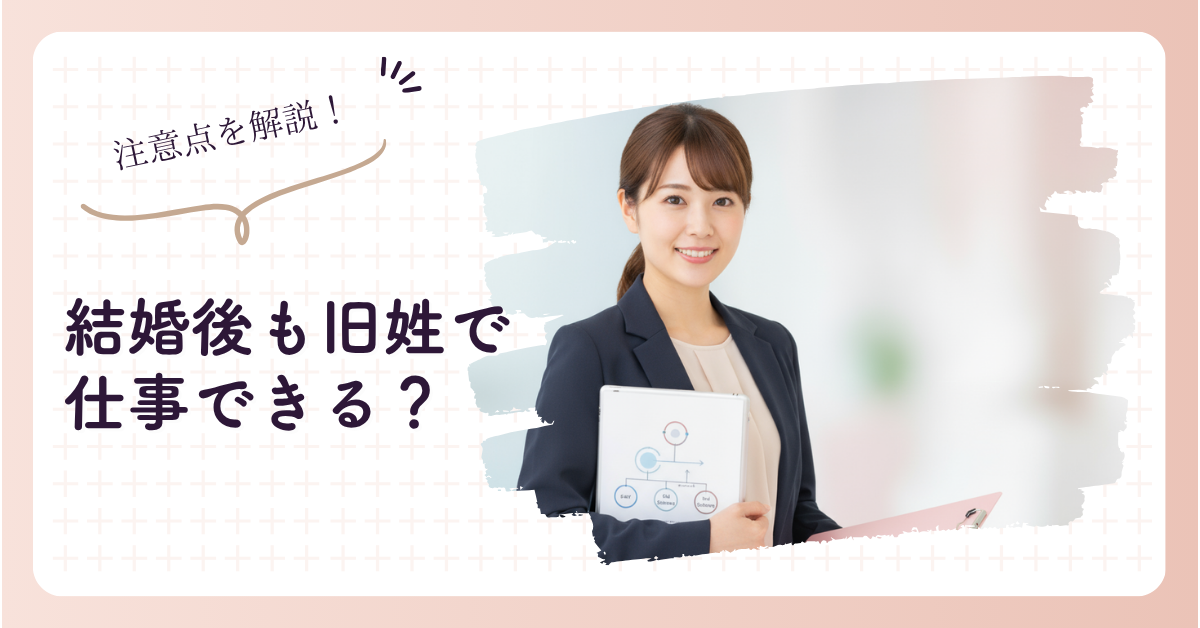※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
結婚を機に姓が変わるけれど、仕事では慣れ親しんだ名前を使い続けたい、と考える方は少なくありません。
結婚後も旧姓のまま仕事を続けるという選択は、多くの職場で可能になっています。
しかし、実際に旧姓を使い続けるにあたり、どのような手続きが必要なのか、メリット・デメリットは何か、といった疑問も生じるでしょう。
職場での旧姓使用の割合は年々増加傾向にありますが、一方で、会社によっては旧姓使用を認めないケースも存在します。
また、周囲に迷惑をかけてしまわないか、あるいは旧姓使用が今後の後悔に繋がらないか、といった不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、結婚後も旧姓で仕事を続ける際の基本情報から、具体的な手続き、そして後悔しないための注意点まで、網羅的に解説していきます。
記事のポイント
- 結婚後も旧姓で働くメリットとデメリット
- 旧姓使用が認められる範囲と必要な手続き
- 会社や同僚との間で起こりうるトラブルと対策
- 後悔しないための姓の選び方と注意点
結婚後も旧姓のまま仕事をする現状と基本
- 職場での旧姓使用の割合はどれくらい?
- 旧姓使用のメリット・デメリットを比較
- 旧姓使用のための社内での手続き方法
- 職場への配慮は?旧姓使用は迷惑?
- 「旧姓使用は後悔した」という声も

でも、公的な書類は新しい名前で、社内では旧姓って…うーん、事務やってるからわかるけど、管理する側も本人も、慣れるまでちょっと大変そう(笑)
どっちも一長一短って感じだね!
職場での旧姓使用の割合はどれくらい?
結婚後も職場で旧姓を使い続けることは、もはや珍しい選択ではなくなっています。
労務行政研究所が2018年に実施した調査によると、職場で旧姓使用を認めている企業は全体の67.5%にのぼります。
これは、同研究所が2001年に行った調査結果から2倍以上に増加しており、女性の社会進出を背景に、旧姓使用が社会的に浸透してきていることがうかがえます。
企業規模別に見ると、規模が大きい企業ほど旧姓使用を認める割合が高い傾向にあります。
| 企業規模 | 旧姓使用を認めている割合 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 79.5% |
| 300~999人 | 64.9% |
| 299人以下 | 52.8% |
また、あるアンケート調査では、旧姓を使い続けることを選んだ人と新姓に変更した人の割合は、ほぼ半々という結果も出ています。
これらのデータから、多くの企業が従業員の希望に柔軟に対応する姿勢を見せていると考えられます。
言ってしまえば、職場での旧姓使用は、個人の意思で選択できる一つの働き方として定着しつつあるのです。
このように職場での旧姓使用が広がっている背景には、女性の社会進出だけでなく、結婚後の氏(姓)のあり方に対する社会的な関心の高まりもあります。
法務省の調査でも、夫婦の姓に関する様々な意識が見て取れます。
旧姓使用のメリット・デメリットを比較
職場で旧姓を使い続けることには、業務の円滑化やプライバシー保護といった利点がある一方で、書類管理の複雑化などの課題も存在します。
ここでは、旧姓使用のメリットとデメリットを比較し、多角的に見ていきましょう。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 業務効率 | ・名刺やメールアドレスの変更が不要 ・顧客や取引先に混乱を与えず、関係性を維持できる ・社内システム等の変更手続きが不要 | ・公的書類と社内通称の使い分けが必要 ・人事や経理担当者の管理業務が煩雑になる |
| キャリア | ・過去の実績や築き上げた人脈が分断されない ・新人と誤解されることなく、キャリアを継続できる | ・転職時に経歴の照会で手間取る可能性がある |
| 人間関係・心理面 | ・公私の切り替えがしやすくなる ・結婚の事実を周囲に知らせずに済む ・社内結婚の場合、同姓による混乱を避けられる | ・新姓に慣れるまでに時間がかかる ・社内で呼び名が統一されず、混乱を招くことがある |
このように、旧姓使用はこれまで通りの環境で仕事を続けられる安心感がある一方で、二つの姓を管理・使用することによる手間が主なデメリットとなります。
ご自身の職種や仕事環境、そしてどのような働き方を望むかを踏まえて、どちらの側面がより大きいかを検討することが大切です。
旧姓使用のための社内での手続き方法
職場で旧姓の使用を希望する場合、まずは会社のルールを確認し、適切な手続きを踏むことが求められます。
特別な法的手続きは不要ですが、社内での円滑な運用にはいくつかのステップがあります。
就業規則や社内規定の確認
最初に、自社の就業規則や通称使用に関する規定を確認します。
旧姓使用の可否や申請方法、使用できる範囲(名刺、メール、社員証など)が定められている場合があります。
不明な点は、総務部や人事部に直接問い合わせるのが最も確実です。
上司への相談と報告
規定を確認した後、直属の上司に結婚の報告と共に、仕事で旧姓を使用したい旨を相談します。
業務への影響(特にお客様対応など)も考慮し、事前に理解を得ておくことで、その後の手続きや周囲への周知がスムーズに進みます。
旧姓使用届の提出
会社によっては、「旧姓使用届」や「通称使用申請書」といった書類の提出が必要になることがあります。
人事部などから所定のフォーマットを受け取り、必要事項を記入して提出します。
このとき、戸籍上の氏名(新姓)と、通称として使用する旧姓を明確に届け出ます。
これらの手続きを進めることで、会社として正式に旧姓使用が認められ、給与明細や社員名簿などで新姓と旧姓が併記されるなど、管理上の対応が行われます。
職場への配慮は?旧姓使用は迷惑?
旧姓で仕事を続けることが、周囲にとって「迷惑」になるのではないかと心配する方もいます。
確かに、状況によっては事務的な混乱を招く可能性は否定できません。
迷惑だと思われかねない主な理由は、人事や経理担当者の事務手続きが複雑になる点です。
給与振込や社会保険、税金関連の手続きはすべて戸籍名(新姓)で行う必要があります。
そのため、担当者は旧姓と戸籍名の両方を正確に把握し、書類ごとに使い分ける必要があり、管理の負担が増えたり、ミスが発生しやすくなったりします。
また、社内外でのコミュニケーションにおいても混乱が生じることがあります。
例えば、他部署の社員や社外から戸籍名で電話がかかってきた際に、電話を受けた人が本人を特定できず、「そのような者はいません」と返答してしまうケースも考えられます。
しかし、これらの問題は適切な対策を講じることで十分に回避可能です。
大切なのは、旧姓を使用するという事実を関係者に明確に周知することです。
人事や経理の担当者には事前に事情を説明し、部署内や関係の深い取引先にも、「仕事では引き続き旧姓の〇〇と名乗ります」と伝えておくことで、無用な混乱を防げます。
つまり、旧姓使用そのものが迷惑なのではなく、周知や連携が不足している状態が問題を引き起こすのです。
本人と会社双方が協力し、円滑な運用体制を築くことが鍵となります。
「旧姓使用は後悔した」という声も
旧姓使用はメリットが多い一方で、実際に選択した人の中には「後悔した」「面倒だった」と感じるケースもあります。
後悔に繋がる主な理由を理解しておくことで、事前に対策を立てることができます。
最も多く聞かれるのが、書類手続きの煩雑さに関する後悔です。
前述の通り、社会保険や年末調整などの公的書類は戸籍名で記入する必要があります。
この使い分けに慣れるまでは、うっかり旧姓で書いてしまい、書類の訂正や再提出を求められることが少なくありません。
特に、新姓の印鑑を忘れて手続きが滞ってしまうといった失敗談も見られます。
次に、プライベートと仕事での姓の不一致による違和感や混乱が挙げられます。
例えば、病院で新姓で呼ばれても自分だと気づかなかったり、クレジットカードのサインで無意識に旧姓を書いてしまったりすることがあります。
特に、海外渡航の際にパスポート(新姓)と航空券(旧姓)の名前が異なり、搭乗できなかったという致命的なトラブルに発展するリスクもゼロではありません。
また、周囲の認識が統一されず、コミュニケーションで苦労したという声もあります。
結婚したことを知らない取引先から、妊娠・出産を機に「いつの間に結婚を?」と驚かれたり、職場の人からの年賀状が旧姓宛で届かなかったりするなど、二つの名前を持つことでの不便さを感じる場面があるようです。
これらの後悔を避けるためには、公的書類での名前の使い分けを常に意識し、パスポートなど重要な身分証の名前は絶対に間違えないように徹底することが大切です。
-

共働きで結婚にメリットがない?理由と解消法を徹底解説
続きを見る
結婚後も旧姓のまま仕事を進める注意点
- 会社が旧姓使用を認めない理由とは
- 公的書類では戸籍名の使用が必須
- 社内での円滑な情報共有のポイント
- 旧姓使用で起こりうるトラブルと対策
- 新姓へ変更する場合の適切なタイミング

特にパスポートと航空券の名前が違うやつ!これはマジで怖いね…。
せっかくの海外出張が台無しになっちゃうじゃん!
会社が旧姓使用を認めない理由とは
旧姓使用を認める企業が増えている一方で、現在でも旧姓使用を認めていない、あるいは推奨していない企業も存在します。
その背景には、企業側の管理上の都合や方針が大きく関わっています。
会社が旧姓使用を認めない最も大きな理由は、人事・労務管理が煩雑になることです。
一人の従業員に対して戸籍名と通称(旧姓)の二つの名前を管理する必要が生じます。
特に、給与計算、社会保険、年末調整といった公的な手続きは戸籍名が必須であるため、これらの情報を扱う人事や経理部門でミスを誘発するリスクが高まります。
また、社内の情報システムが二つの名前の管理に対応していないケースもあります。
社員データベースや勤怠管理システムなどが一つの氏名しか登録できない仕様の場合、システム改修にはコストがかかるため、旧姓使用を認めないという判断に至ることがあります。
さらに、企業文化や方針として、全社員の氏名を戸籍名で統一することを重視している場合もあります。
これは、社内外のコミュニケーションにおける混乱を避け、組織としての一貫性を保つため、という考え方に基づいています。
このように、会社が旧姓使用を認めないのは、単に伝統や慣習に固執しているからではなく、管理上のリスクやコスト、組織運営上の方針といった合理的な理由がある場合がほとんどです。
会社が作成を義務付けられている「労働者名簿」には、労働基準法施行規則により戸籍上の氏名を記載する必要があります。
このように、法律で定められた書類の管理が、会社が旧姓使用に慎重になる一因ともいえます。
公的書類では戸籍名の使用が必須
職場で旧姓使用が認められている場合でも、全ての場面で旧姓が使えるわけではありません。
法律に基づき、公的な効力を持つ書類や手続きにおいては、必ず戸籍上の氏名(新姓)を使用する必要があります。
この線引きを正しく理解しておくことは、トラブルを避ける上で非常に大切です。
戸籍名での手続きが必須な書類の例
以下に挙げるものは、代表的な戸籍名が必須となる書類や手続きです。
これらの手続きを会社が行う場合、人事部などには戸籍名を正確に届け出る必要があります。
- 健康保険証
- 年金手帳、年金関連の手続き
- 雇用保険関連の手続き(被保険者証など)
- 源泉徴収票
- 給与支払報告書
- 賃金台帳
- 労働者名簿
旧姓(通称)が使用できることが多いもの
一方で、以下のような社内的な書類やツールについては、会社の規定の範囲内で旧姓の使用が認められることが一般的です。
- 名刺
- 社用のメールアドレス、署名
- 社員証、名札
- 社内システムの表示名
- 座席表、社内報
- 業務上の契約書(※ただし、契約の重要度や相手方の規定による)
要するに、「国や地方自治体が関わる法的な手続き」は戸籍名、「社内や業務上のコミュニケーション」は会社の裁量で旧姓使用が可能、と大別できます。
この区別を常に意識し、書類を記入する際はどちらの名前を使うべきかを確認する習慣をつけることが求められます。
ちなみに、2019年11月5日からは、住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓を併記できるようになりました。
これにより、公的な本人確認書類でも旧姓を証明しやすくなっています。
詳しくは法務省の公式サイトをご確認ください。
社内での円滑な情報共有のポイント
旧姓使用をスムーズに運用し、本人や周囲の混乱を避けるためには、社内での情報共有の仕組みを整えることが鍵となります。
これは本人だけの努力ではなく、会社側の協力も不可欠です。
まず、本人が行うべき最も重要なことは、関係者への明確な意思表示です。
結婚報告の際に、上司や同僚、特に関わりの深い他部署の担当者に対して、「業務上はこれまで通り旧姓の〇〇でお願いします」とはっきりと伝えましょう。
曖昧なままにすると、新姓で呼ぶべきか旧姓で呼ぶべきか、周囲が迷ってしまいます。
次に、会社側が取り組むべきポイントとして、社員情報の管理方法が挙げられます。
人事システムや社員名簿において、戸籍名と通称(旧姓)を併記して管理することが理想的です。
こうすることで、人事や経理担当者が公的書類を作成する際も、電話の取り次ぎの際も、どちらの名前でも本人を特定できます。
社員番号と紐づけて情報を一元管理できるシステムを導入するのも有効な手段です。
また、旧姓使用者がいるという事実を、社内でオープンにしておくことも大切です。
例えば、社内イントラネットの名簿に「戸籍名:鈴木花子(旧姓:田中)」のように表示されていれば、全社員が状況を把握しやすくなります。
このように、本人の明確な伝達と、会社側の管理体制の整備が両輪となって初めて、円滑な旧姓使用が実現します。
旧姓使用で起こりうるトラブルと対策
旧姓使用は便利ですが、二つの名前を使い分けることによる特有のトラブルが発生する可能性があります。
ここでは、よくある失敗例とその対策について具体的に見ていきます。
印鑑の押し間違い
年末調整や各種申請書など、戸籍名での署名・捺印が必要な書類に、誤って旧姓の印鑑を押してしまうケースです。
対策: 常に新姓と旧姓の両方の印鑑を携帯するか、デスクに常備しておくと安心です。
書類に捺印する前には、どちらの名前での手続きかを必ず確認する癖をつけましょう。
郵便物や年賀状が届かない
自宅の表札や郵便受けに新姓しか記載していない場合、職場の同僚が旧姓宛に送った年賀状などが「宛名不明」で返送されてしまうことがあります。
対策: 郵便局に「転居届」を提出する際に、旧姓宛の郵便物も新姓の住所に届けてもらうよう登録することができます。
また、職場の住所録には戸籍名と旧姓を併記してもらうようお願いするのも一つの手です。
航空券の予約ミス
最も深刻なトラブルの一つが、国際線の航空券予約です。
パスポートは戸籍名(新姓)で発行されているにもかかわらず、会社の担当者が出張手配の際に、慣れている旧姓で航空券を予約してしまうと、氏名が不一致となり搭乗を拒否されてしまいます。
対策: 海外出張などパスポートが必要な手続きが発生する場合は、予約担当者に「航空券の予約は、必ずパスポート記載の戸籍名(新姓)でお願いします」と、念を押して伝えることが不可欠です。
これらのトラブルは、少しの注意で防ぐことができます。二つの名前を管理しているという意識を常に持ち、特に重要な手続きの際には入念な確認を行うことが大切です。
新姓へ変更する場合の適切なタイミング
旧姓を使い続けるか、新姓に切り替えるか迷った場合、あるいは一度は旧姓使用を選んだものの、やはり新姓に統一したいと考えることもあるでしょう。
その場合、どのタイミングで変更するのが最もスムーズでしょうか。
一般的に、周囲への影響を最小限に抑えられるのは、仕事上の区切りの良い時期です。
最も推奨されるタイミングの一つが、年度の切り替わりである4月です。
特に、教職員や保育士など、年度ごとに担当する生徒や園児が変わる職種の場合、新年度のスタートと同時に新姓に切り替えることで、子どもや保護者の混乱を最小限にできます。
これは、他の職種においても、組織変更や人事異動が多い時期であるため、名前の変更を周知しやすいという利点があります。
また、部署異動や転勤、昇進といったキャリア上の変化も、新姓に切り替える絶好の機会です。
新しい環境で新しい人間関係を築き始めるタイミングであれば、最初から新姓で自己紹介することで、自然に名前を浸透させることができます。
一方で、プロジェクトの途中や繁忙期の真っ只中に名前を変更するのは、取引先やチーム内に混乱を招く可能性があるため、避けた方が賢明です。
「いつでも新姓には変えられるが、一度変えたら旧姓には戻しにくい」という意見もあります。
もし迷っているのであれば、まずは旧姓使用を続け、仕事や生活の状況を見ながら、最適なタイミングで新姓への切り替えを検討するというのも一つの賢い選択です。
-

主婦の正社員はきつい?理由とパートとの比較・後悔しない選択
続きを見る
まとめ:結婚後も旧姓のまま仕事をするには
この記事で解説した重要なポイントを以下にまとめます。
ま と め
- 旧姓使用を認める企業は増加傾向にあり全体の半数を超える
- 旧姓を使い続ける人と新姓に変更する人の割合はほぼ半々
- 旧姓使用のメリットはキャリアの継続性や取引先との関係維持
- 名刺やメールアドレスの変更が不要で業務が円滑に進む
- デメリットは公的書類と通称を使い分ける煩雑さ
- 人事や経理など管理部門の負担が増える可能性がある
- 旧姓使用を希望する場合はまず会社の就業規則を確認する
- 上司や人事部に相談し所定の手続きを行う
- 旧姓使用を認めていない企業も存在しその理由は管理の複雑さ
- 健康保険や年金、税金関連の書類は必ず戸籍名(新姓)で手続きする
- 社内での混乱を避けるため関係者への周知徹底が重要
- パスポートと航空券の名前が異なると搭乗できないリスクがある
- 印鑑の使い分けや郵便物の宛名など日常的な注意も必要
- もし新姓に変えるなら年度替わりや異動のタイミングがスムーズ
- 自分にとってストレスの少ない方法を選ぶことが最も大切