※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
育児と仕事の両立に奮闘する中で、職場でワーママハラスメントに悩んでいませんか。
時短勤務を理由とした時短ママハラスメントや、「育休早く復帰しろ」と言わんばかりの無言の圧力は、決して他人事ではありません。
一方で、周囲からは「ワーママ優遇されすぎ」という誤解を受け、板挟みになってしまうこともあります。
ワーママの大変な事が十分に理解されない職場環境は、心身を疲弊させ、最終的にワーママが退職する理由にも繋がりかねません。
この記事では、そうした複雑な悩みを抱える方のために、ハラスメントの具体的な事例から、いざという時の対処法、そして利用できる相談窓口までを網羅的に解説します。
記事のポイント
- ワーママハラスメントの具体的な種類や事例がわかる
- ハラスメントが発生する背景や原因を理解できる
- 被害に遭った際の具体的な対処法や相談先がわかる
- 法律や会社の制度に基づいた対策を知ることができる
増加するワーママハラスメントの種類と実態

ここでは、ワーママハラスメントの具体的な種類と、その背景にある複雑な実態について掘り下げていきます。
- ワーママハラスメントの定義とは
- 時短ママハラスメントと呼ばれる不当な扱い
- 育休早く復帰しろハラスメントは許される?
- ワーママ優遇されすぎという周囲の誤解
- ワーママの大変な事が理解されない職場環境

こっちも残業してる人には「すみません!」って思いながら帰ってるのに、嫌味を言われるとね…。
しかも「配慮」って名目で、やりがいのある仕事から外されるのが一番こたえる。
「いや、できますけど?」って喉まで出かかるわ(笑)
ワーママハラスメントの定義とは
ワーママハラスメントとは、職場において妊娠、出産、育児などを理由として、働く女性が精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、解雇や降格といった不利益な扱いをされたりして、就業環境が害されることを指します。
これは、妊娠・出産に関するハラスメント全般を指す「マタニティハラスメント(マタハラ)」の一種と位置づけられています。
これらの行為は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法によって明確に禁止されている違法行為です。
具体的には、以下のようなケースがワーママハラスメントに該当する可能性があります。
チェック
- 妊娠の報告をしたら、退職を促された
- 育児休業の取得を相談したら、嫌な顔をされたり、非協力的な態度を取られたりした
- 育休からの復帰後、本人の意に反して責任の軽い業務に配置転換された
- 子どもの急な発熱で休むたびに、上司や同僚から嫌味を言われる
- 「時短勤務なのだから」という理由で、重要な会議に参加させてもらえない
このように、ワーママハラスメントは、働く母親の尊厳を傷つけるだけでなく、キャリア形成の機会を奪い、経済的な安定を脅かす深刻な問題と言えます。
時短ママハラスメントと呼ばれる不当な扱い

時短ママハラスメントは、育児などを理由に短時間勤務制度を利用している従業員に対して行われる嫌がらせや不当な扱いを指します。
ワーママハラスメントの中でも特に発生しやすい形態の一つです。
このハラスメントが起きる背景には、「時短勤務者は仕事への意欲が低い」「限られた時間しか働かないのだから、重要な仕事は任せられない」といった、職場に根強く残る固定観念や偏見があります。
また、残業削減だけを目的とした「働き方改革」の誤った運用が、結果的に時短勤務者に業務のしわ寄せがいく、という事態を招いているケースも見受けられます。
具体的には、以下のような行為が時短ママハラスメントに該当する可能性があります。
チェック
- 能力や経験に見合わない補助的な業務しか与えられない
- 時短勤務を理由に、不当に低い人事評価をされる
- 他のフルタイム従業員と同じ業務量を、短い時間でこなすよう要求される
- 「早く帰れていいね」といった嫌味や、陰口を言われる
- 時短勤務中にもかかわらず、恒常的に残業を強要される
したがって、時短勤務という働き方の選択が、キャリアアップの機会を不当に奪ったり、精神的な苦痛を強いたりする状況は、明確なハラスメントであり、働く人の権利を侵害する行為なのです。
育休早く復帰しろハラスメントは許される?
育児休業からの早期復帰を強要したり、それを促す言動で本人にプレッシャーを与えたりする行為は、ハラスメントに該当する可能性が非常に高く、決して許されるものではありません。
なぜなら、育児休業は育児・介護休業法で保障された労働者の正当な権利だからです。
本人の意思に反して、会社側が一方的に復帰時期を早めるよう強要することは、この権利を侵害する行為とみなされます。
もちろん、会社の状況を説明し、本人の意向を確認した上で復帰時期を相談すること自体が、直ちにハラスメントになるわけではありません。
しかし、その言動が以下のようなケースに当てはまる場合は、問題となる可能性が高まります。
チェック
- 繰り返し早期復帰を迫り、精神的なプレッシャーを与える
- 「君がいないと部署が回らない」などと、罪悪感を抱かせるような言い方をする
- 早期復帰に応じないことを理由に、復帰後の降格や不利益な配置転換を示唆する
- 他の従業員の前で、育休取得を非難するような言動を取る
もし、育休からの復帰に関して少しでも強要されていると感じたり、不利益な扱いを示唆されたりした場合は、それは正当な業務調整の範囲を超えたハラスメントである可能性を疑う必要があります。
ワーママ優遇されすぎという周囲の誤解

ワーママハラスメントの問題を複雑にしている一因として、「ワーママは優遇されすぎている」という周囲からの誤解や反発があります。
これは、制度を利用して働く母親に向けられる、一種のハラスメントと考えることができます。
このような感情が生まれる背景には、いくつかの要因が考えられます。
一つは、育児中の従業員への配慮が、他の従業員への「しわ寄せ」として現れてしまうケースです。
例えば、ワーママが子どもの都合で急に休んだ際、その業務を他の誰かがカバーしなければならない状況が続くと、カバーする側に不満が溜まりやすくなります。
また、制度の内容や育児と仕事の両立の大変さについて、職場全体での理解が不足していることも大きな要因です。
「定時で帰れる」「休みが取りやすい」といった表面的な部分だけを見て、「楽をしている」「優遇されている」と一方的に思い込んでしまうのです。
こうした誤解から、「自分たちだって大変なのに」「少しは周りのことも考えてほしい」といった不満が、嫌味や非協力的な態度として現れることがあります。
しかし、制度を利用することは労働者の権利であり、それを理由に非難されるべきではありません。
本来は、個人の問題として対立するのではなく、組織全体で業務分担や人員配置を見直し、誰もが働きやすい環境を構築していくべき課題なのです。
ワーママの大変な事が理解されない職場環境
多くのワーママハラスメントの根底には、育児をしながら働くことの「大変さ」が、職場で十分に理解されていないという現実があります。
この無理解が、ハラスメントを生み出す温床となっているのです。
ワーママが抱える大変さは、単に「仕事と育児で忙しい」という言葉だけでは片付けられません。
予測不能な日々の連続
子どもの体調は非常に変わりやすく、突然の発熱や感染症で、登園できなくなることは日常茶飯事です。
そのたびに仕事を休んだり、早退したりする必要があり、職場に迷惑をかけてしまうことへの「肩身の狭さ」や「罪悪感」に常に苛まれます。
体力的な限界
朝は誰よりも早く起きて家事や子どもの準備をし、日中は仕事に集中し、終業後は息つく間もなくお迎え、夕食、お風呂、寝かしつけと、一日中休む暇がありません。
このような生活が続けば、体力的に限界を感じるのは当然のことです。
精神的なプレッシャー
「仕事も完璧に、育児も完璧に」という社会からの無言のプレッシャーや、子どもと十分に接する時間が取れないことへの自責の念など、精神的な負担も計り知れません。
こうした複合的で深刻な状況が理解されないまま、「やる気がない」「責任感がない」と一方的に判断されてしまうことが、心ない言葉や不当な扱い、すなわちハラスメントに繋がってしまいます。
-
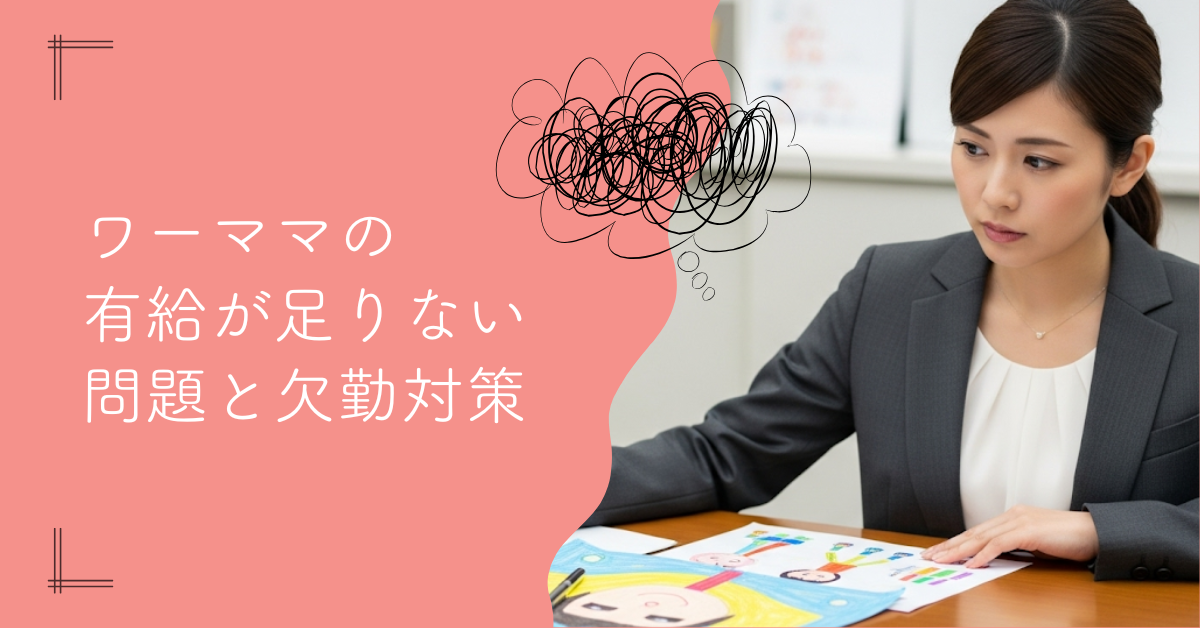
ワーママの有給が足りない問題と欠勤:どう乗り越える?
続きを見る
ワーママハラスメントの解決策と相談先

ここでは、ハラスメントという困難な状況に直面した際の具体的な解決策と、一人で抱え込まないための相談先について詳しく解説します。
- ワーママが退職する理由はキャリアの問題
- 被害に遭った時の具体的な対処ステップ
- 一人で抱え込まないための相談先一覧
- 企業に義務付けられている防止措置とは

子育てだけじゃなくて、親の介護とか、自分の体調とか、誰だっていつ何があるかわかんないんだから。
そういう時に、当たり前に助け合える会社が、本当に働きやすい会社だなって思う。
ワーママが退職する理由はキャリアの問題
ワーキングマザーが退職を決意する背景には、単に「仕事と育児の両立が難しい」という体力的な問題だけではなく、より根深いキャリアの問題が存在します。
その代表的なものが「マミートラック」です。
マミートラックとは、出産・育児を機に、本人の意欲や能力とは関係なく、昇進・昇格のコースから外れ、補助的な業務や責任の軽い仕事しか与えられなくなる状況を指します。
これは、上司の「育児中は大変だろうから」という善意の“過剰な配慮”が、結果的に働く母親の成長機会を奪ってしまうケースが少なくありません。
多くのワーママは、育児中でもキャリアを諦めたわけではなく、むしろ「責任ある仕事を全うしたい」「スキルアップして会社に貢献したい」と考えています。
しかし、マミートラックに乗せられてしまうと、やりがいのある仕事に挑戦できず、モチベーションが低下していきます。
「この会社にいても、もうキャリアアップは望めない」
「正当に評価してもらえない」
このような閉塞感が、優秀な人材であるにもかかわらず、転職や退職という選択を考えさせる大きな理由となるのです。
つまり、ワーママの離職は、個人の問題というよりも、機会の不均衡や正当な評価が行われない企業の組織的な課題であると言えます。
被害に遭った時の具体的な対処ステップ

もし職場でハラスメントを受けていると感じたら、感情的にならず、冷静に対処することが事態解決の鍵となります。
一人で抱え込まず、以下のステップを参考に、具体的な行動を起こしましょう。
Step1:詳細な記録をつける
まず、ハラスメント行為に関する客観的な事実を記録することが何よりも大切です。
後々、会社や第三者機関に相談する際に、これが重要な証拠となります。
- いつ: 年月日、時間
- どこで: 会社の会議室、自席など
- 誰が: ハラスメント行為者の氏名・役職
- 何を言われたか/何をされたか: 具体的な言動を正確に
- どう感じたか: 屈辱的だった、悲しかったなど、自分の気持ち
- 目撃者はいたか: 周囲にいた同僚など
これらの情報を、記憶が鮮明なうちにメモや日記に残しておきましょう。
Step2:証拠を収集する
具体的な言動の記録に加え、客観的な証拠があれば、より有利になります。
- メールやチャット: ハラスメントに該当する内容のメールなどは、削除せず必ず保存・印刷しておく。
- 音声の録音: 最近では、ICレコーダーやスマートフォンのアプリで簡単に録音できます。相手に無断の録音も、状況によっては証拠として認められる場合があります。
Step3:信頼できる人に相談する
一人で悩みを抱え込むと、精神的に追い詰められてしまいます。
まずは配偶者や家族、信頼できる友人に話を聞いてもらいましょう。
社内の同僚に相談する場合は、口が堅く、客観的な視点でアドバイスをくれる人を選ぶことが大切です。
Step4:自分の希望を明確にする
最終的に自分が「どうしたいのか」を整理することも重要です。
「ハラスメントをやめてほしいだけ」「行為者に謝罪してほしい」「部署を異動したい」「会社として再発防止策を講じてほしい」など、求めるゴールによって、次の取るべき行動が変わってきます。
一人で抱え込まないための相談先一覧
ハラスメントの問題は、当事者だけでの解決が難しいケースも少なくありません。
その際は、専門的な知識を持つ第三者の力を借りることが有効です。
社内外に様々な相談窓口がありますので、状況に応じて活用を検討してください。
| 相談窓口の種類 | 特徴 | こんな時におすすめ |
|---|---|---|
| 社内の相談窓口 | 人事部、コンプライアンス担当部署、労働組合など。最も身近な相談先で、迅速な対応が期待できる。 | まずは社内で解決を図りたい場合。具体的な事実関係の調査や、行為者への指導を求めたい時。 |
| 総合労働相談コーナー | 全国の労働局・労働基準監督署内に設置。予約不要・無料で専門の相談員が対応。労働問題全般について助言や情報提供を受けられる。 | どこに相談していいかわからない場合。法的な解釈や、他の解決機関について知りたい時。 |
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に関するハラスメントが専門。必要に応じて、会社への助言・指導や、紛争解決援助(あっせん)も行う。 | マタハラ、パタハラ、ケアハラなど、育児や介護に関するハラスメントで具体的な解決を求めたい時。 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 国が設立した法的トラブルの総合案内所。相談内容に応じて、解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で案内。収入などの条件を満たせば、無料の法律相談も可能。 | 弁護士に相談すべきか迷っている場合。法的な解決手段について詳しく知りたい時。 |
| 弁護士 | 法律の専門家として、具体的な解決策を提示。代理人として会社と交渉したり、労働審判や訴訟を行ったりすることができる。 | 会社との交渉が難航している場合。損害賠償請求など、法的な措置を真剣に考えている時。 |
企業に義務付けられている防止措置とは

労働者の人権を守り、安心して働ける環境を確保するため、法律によって企業にはハラスメントを防止するための措置を講じることが義務付けられています。
この義務は、大企業だけでなく、2022年4月からはすべての中小企業にも適用されています。
具体的には、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき、企業は以下の措置を講じなければなりません。
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- ハラスメントは許さないという方針を明確にし、就業規則などに規定すること。
- 研修などを通じて、管理職を含む全従業員にハラスメントに関する知識を周知・啓発すること。
② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 従業員が安心して相談できる窓口を設置し、その存在を周知すること。
- 相談担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること。
③ 職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ハラスメントの相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- 事実が確認できた場合は、速やかに行為者に対する措置や被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
- 再発防止策を講じること。
④ そのほか併せて講ずべき措置
- 相談者や行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること。
- ハラスメントの相談をしたことなどを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
これらの措置が講じられていない、または機能していないと感じた場合は、それ自体が企業の安全配慮義務違反にあたる可能性もあります。
-

ワーママの土日家事で終わる問題を解決するヒント
続きを見る
まとめ:なくそう職場のワーママハラスメント

この記事では、ワーママハラスメントの様々な側面と、その対処法について解説してきました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
ま と め
- ワーママハラスメントは法律で明確に禁止された行為
- 育休や時短勤務を理由とした不利益な扱いは許されない
- ハラスメントは働く母親のキャリア形成を阻害する
- 「優遇されすぎ」という誤解もハラスメントの一因となりうる
- 多くのハラスメントの背景には育児への無理解がある
- 被害に遭ったら、まずは冷静に記録と証拠収集を行う
- 一人で抱え込まず、信頼できる人や窓口に相談することが大切
- 社内だけでなく、労働局や法テラスなど社外の相談先も存在する
- 企業にはハラスメントを防止する法的な義務がある
- 上司の「過剰な配慮」が機会損失に繋がることもある
- マミートラックはキャリアに関する深刻な問題
- 自分の希望(どう解決したいか)を明確にすることが次の一歩
- 録音などの客観的な証拠は交渉を有利に進める材料になる
- 会社の相談窓口が機能していない場合は外部機関を頼る
- 誰もが働きやすい環境作りは組織全体の課題である

