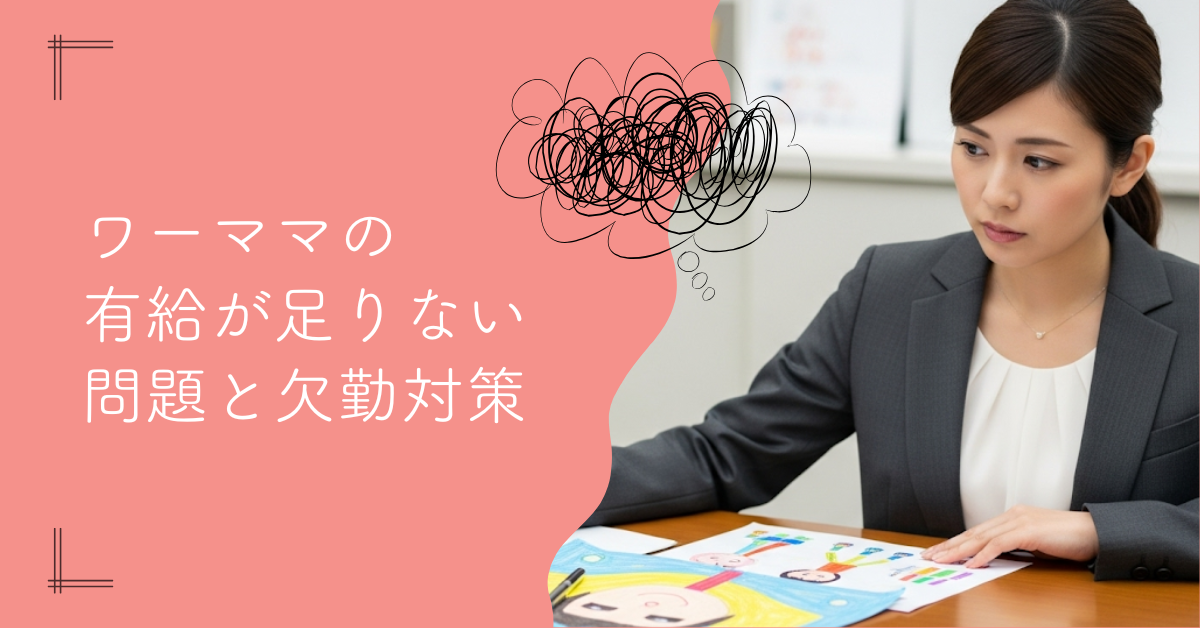※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
「時短勤務で有給が足りない」「学校行事で有給が足りない」「ワーキングマザーなのに休みすぎていると感じる」、そういったお悩みをお持ちではありませんか?
有給を使い切って欠勤した時に、パートであっても給与はどうなるのか、また、ご自身の体調不良や、一体どこからが休みすぎの基準になるのか、そして最悪の場合、ワーママが休みすぎを理由に退職せざるを得なくなるのかといった不安を抱える方もいるでしょう。
このブログ記事は、そんなあなたの疑問に寄り添い、具体的な解決策を提示していきます。
記事のポイント
- ワーママの有給が不足する背景と欠勤の具体的な影響
- 欠勤控除が給与や評価に与える影響
- 有給休暇以外の代替休暇制度とその活用方法
- 2025年4月からの法改正によるワーママへの影響
ワーママで有給が足りない場合の欠勤対策

- 欠勤控除が給与に与える影響
- 有給を使い切った後の欠勤の扱い
- 休みすぎの基準は?
- 時短勤務では有給が足りない場合
- ワーキングマザーが休みすぎと感じたら

うちも毎年20日の有給があっという間になくなるよ。
子どもが3人もいると、なんだかんだで学校行事とか個別の用事が多いんだよね。
自分の通院とか入れたらもうカツカツ!
計画的に使わないとすぐゼロになっちゃう。
欠勤控除が給与に与える影響
ワーママとして働く中で、有給休暇を使い果たし、やむを得ず欠勤してしまうケースは少なくありません。
多くの会社では、就業規則に基づいて欠勤控除が行われます。これは、給与が欠勤した日数分だけ減額されることを意味します。
有給休暇は所定労働時間に含まれ、取得すれば給与が支払われますが、欠勤は給与が支払われない休みです。
そのため、欠勤が増えると、手取り収入が予想以上に減ってしまう可能性があります。
給与が減額されるだけでなく、欠勤が続くと評価やボーナスにも影響が出る場合があります。
企業によっては、欠勤日数が多い従業員に対し、人事評価を下げたり、ボーナスの査定額を減らしたりする規定を設けていることがあるためです。
これは、企業が従業員の勤務態度や貢献度を評価する際に、出勤率を重要な要素とみなすためと言えるでしょう。
結果として、昇進やキャリアアップの機会にも影響を及ぼす可能性も考えられます。
事前に会社の就業規則を確認し、欠勤に関する具体的な規定を理解しておくことが大切です。
早めに会社に相談し、状況を説明して理解を求めることで、これらの影響を最小限に抑えることも可能になります。
有給を使い切った後の欠勤の扱い

有給休暇をすべて使い切ってしまった後に、病気や子どもの都合などで会社を休む場合、その休みは原則として「労働者都合」の欠勤として扱われます。
これは、自身の体調不良や私用だけでなく、家族の看病や通院の付き添いなども含まれる場合が一般的です。
欠勤扱いになると、当然ながらその分の給与は支払われません。
つまり、月給制であっても、欠勤日数に応じた給与の減額が行われることになります。
ただし、会社によっては、独自に「特別休暇」や「病気休暇」といった制度を設けているケースがあります。
これらの休暇は、有給休暇とは別に付与されるもので、特定の条件下で利用できることがあります。
例えば、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなど、特定の感染症による欠勤に対しては、通常の欠勤とは異なる扱いをする会社も存在します。
ご自身の勤務先の休暇制度について詳しく知りたい場合は、人事・労務の担当部署に就業規則について問い合わせることが賢明です。
傷病手当金制度のように、病気や怪我で長期欠勤せざるを得ない場合に生活を保障する公的な制度もありますので、必要に応じて活用を検討することも重要になります。
休みすぎの基準は?
「休みすぎ」の明確な基準は法律で定められているわけではありませんが、一般的には出勤率が8割を下回ると、注意が必要な目安とされています。
労働基準法において、労働者には年次有給休暇が付与されますが、この有給休暇は出勤したものとして扱われます。
したがって、有給休暇を適切に取得していれば、出勤率に大きな影響は出にくいものです。
しかし、有給休暇を使い果たし、欠勤が常態化してしまうと、業務への支障が生じる可能性があります。
これは、他の従業員への負担増大や、プロジェクトの遅延など、会社全体に影響を及ぼす可能性があるためです。
多くの企業では、出勤率や欠勤日数を人事評価の一つの要素として考慮しています。
出勤率が著しく低い場合、評価が下がるだけでなく、賞与の支給額にも影響が出る場合があります。
場合によっては、就業規則に則り、懲戒処分や解雇の対象となる可能性もゼロではありません。
ただし、解雇に至るケースは、無断欠勤や悪質な欠勤が継続的に発生した場合など、非常に限定的です。
一般的な体調不良や子どもの看護による欠勤であれば、まずは会社に相談し、状況を共有することが第一歩となるでしょう。
-

職場のワーママハラスメント|事例・原因から具体的な解決策まで
続きを見る
時短勤務では有給が足りない場合

時短勤務で働くワーママは、フルタイム勤務の従業員に比べて労働時間が短い分、有給休暇が足りなくなることへの不安を感じやすいものです。
本来、有給休暇の付与日数は、所定労働日数に基づいて決まります。
そのため、週の所定労働日数が少ない時短勤務の場合、フルタイム勤務者よりも有給休暇の付与日数が少なくなることがあります。
たとえ有給休暇が少なかったとしても、子どもの体調不良や学校行事など、休む必要がある場面は変わりません。
むしろ、保育園に通い始めたばかりの子どもは、頻繁に体調を崩すことが多く、「保育園の洗礼」とも呼ばれるように、有給休暇がすぐに底をついてしまうという声も聞かれます。
このような状況は、ワーママにとって大きなストレスとなり得ます。
そこで、有給休暇の計画的な取得はもちろんのこと、会社が提供している他の休暇制度や柔軟な働き方を検討することが重要になります。
例えば、子の看護休暇や特別休暇、フレックスタイム制度、テレワークなどの活用が考えられます。
これらの制度を上手に組み合わせることで、有給休暇が足りない状況でも、欠勤することなく必要な休みを取れるようになるでしょう。
ワーキングマザーが休みすぎと感じたら
ワーキングマザーとして日々奮闘されている方の多くは、お子さんの急な体調不良や保育園・学校行事などでやむを得ず会社を休む機会が増え、「もしかして、自分は会社を休みすぎているのではないか」と感じてしまうことがあるかもしれません。
特に、周囲の同僚や上司からの目が気になり、必要以上に罪悪感を抱いてしまうこともあるのではないでしょうか。
しかし、お子さんが小さいうちは、予測できない体調不良が頻繁に起こるものです。
これはワーキングマザーであれば誰もが直面しうる避けられない現実であり、決してあなただけが抱えている問題ではありません。
このような状況をひとりで抱え込むことは、精神的な負担を増大させ、ストレスの原因となってしまいます。
そこで、以下のポイントを参考に、状況を改善していきましょう。
会社との積極的なコミュニケーション
- 正直に状況を説明し、困っていることを会社に伝えることで、理解や協力を得られるケースは少なくありません。
- 突発的な休みに備えて、担当業務の分担体制を構築したり、緊急連絡フローを明確にしたりするなどの対策提案も有効です。
家庭内での連携強化
- パートナーと、お子さんの急な体調不良時や、保育園・学校からの呼び出しがあった際の対応分担について、具体的なルールを事前に決めておくことが重要です。
- 「どちらが早く迎えに行けるか」「当番制にするか」など、具体的なシミュレーションをしておくことで、いざという時に慌てずに対応できます。
- ご両親など、頼れる方が近くにいる場合は、緊急時にサポートをお願いできるよう、日頃から関係性を築いておくことも一つの手です。
外部サービスの積極的な活用
- 病児保育サービスへの事前登録は、お子さんが病気で集団保育が難しい場合に非常に役立ちます。利用枠に限りがある場合も多いため、早めに複数の施設に登録しておくことが賢明です。
- 病児保育に対応可能なベビーシッターサービスも選択肢に入れると良いでしょう。自宅で子どもの看病ができるため、移動の負担を減らせるメリットがあります。
- これらのサービスを上手に組み合わせることで、突発的な休みを減らし、心身の負担を軽減することにつながります。
自身の体調管理の徹底
- 十分な睡眠を確保し、バランスの取れた食事を心がけることは、免疫力を高める上で非常に大切です。
- ストレスを溜め込まないよう、適度な休息やリフレッシュの時間を設けることも欠かせません。
- 少しでも体調に異変を感じたら、無理せず早めに医療機関を受診することが大切です。無理をして悪化させてしまうと、かえって長期的な欠勤につながる可能性もあるため、早期の対応が鍵となります。
大切なのは、利用できる制度やサービスを最大限に活用し、心身の負担を減らすことです。
そして、ご自身の健康が保たれてこそ、仕事と育児を長期的に両立できます。
周囲に遠慮しすぎず、利用できるものは利用するという前向きな姿勢を持つことが、ワーキングマザーとして働き続ける上での鍵となるでしょう。
ワーママの有給が足りない問題と欠勤を乗り越える方法

- ワーママ自身の体調不良への対策
- 学校行事などで有給が足りない時
- 子の看護休暇の活用方法
- 2025年4月からの育児・介護休業法改正点
- ワーママの休みすぎで退職を考える前に

夫と協力して手分けしてるけど、それでも足りない月はヒヤヒヤする。
あと5日…いや10日くらい追加で欲しいって毎年思うもん。
ワーママ自身の体調不良への対策
ワーママは仕事と育児の両立で多忙な日々を送っており、自身の体調不良を後回しにしがちです。
しかし、無理を続けることは、自身の健康を損なうだけでなく、結果的に子どもの世話や仕事にも影響を及ぼすことになります。
子どもから風邪をもらってしまったり、睡眠不足が続いて体調を崩したりすることは少なくありません。
このような状況を避けるためには、日頃から自身の体調管理を意識的に行うことが重要です。
十分な睡眠を確保し、バランスの取れた食事を心がけることは、免疫力を高める上で非常に大切です。
また、ストレスを溜め込まないよう、適度な休息やリフレッシュの時間を設けることも欠かせません。
例えば、短時間でも趣味に没頭する時間を作ったり、軽い運動を取り入れたりすることで、心身のリフレッシュを図ることができます。
そして、少しでも体調に異変を感じたら、無理せず早めに医療機関を受診することが大切です。
無理をして悪化させてしまうと、かえって長期的な欠勤につながる可能性もあるため、早期の対応が鍵となります。
会社によっては、定期健康診断の他に、産業医との面談やストレスチェックなどの制度を設けている場合もありますので、積極的に活用を検討すると良いでしょう。
学校行事などで有給が足りない時

子どもの学校行事やイベントは、ワーママにとって有給休暇を消費する大きな要因の一つです。
運動会や発表会、授業参観など、子どもの成長を見守る大切な機会である一方で、有給休暇が足りなくなる原因となることも少なくありません。
これらの行事は通常、事前に日程が分かっているため、計画的に有給休暇を申請することが基本となります。
しかし、複数の子どもがいる場合や、突発的な体調不良と重なることで、有給休暇が不足してしまうことも考えられます。
このような状況に備えるには、まず年間を通しての行事予定を早めに把握し、有給休暇の取得計画を立てることが大切です。
また、前述の通り、会社によっては特別休暇や記念日休暇など、有給休暇とは別に取得できる休暇制度を設けている場合があります。
就業規則を確認し、利用可能な休暇制度がないか調べてみることをお勧めします。
例えば、近年ではフレックスタイム制度やテレワークが導入されている企業も増えており、これらを活用することで、行事に参加しつつも業務を柔軟に進めることが可能になるケースもあります。
ご自身の状況に合わせて、会社の人事担当者や上司に相談し、どのような選択肢があるのか確認することが重要です。
子の看護休暇の活用方法
有給休暇を使い切ってしまったワーママにとって、「子の看護休暇」は非常に重要な選択肢となります。
これは育児・介護休業法に基づき、小学校就学前の子どもを養育する労働者が利用できる法定休暇制度です。
子どもが1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日まで取得することができます。
この休暇は、子どもの病気や怪我の看護だけでなく、予防接種や健康診断の付き添いにも利用することが可能です。
大きなメリットは、時間単位での取得も可能な点です。
これにより、保育園や学校への送迎、病院への付き添いなど、短時間だけ必要な場合に柔軟に対応できます。
ただし、子の看護休暇を有給とするか無給とするかは、会社の就業規則によって異なります。
厚生労働省の調査によると、無給としている会社が多数を占める傾向にありますが、一部有給や全日有給としている会社もあります。
そのため、ご自身の会社の就業規則を確認し、子の看護休暇に関する規定を把握しておくことが大切です。
また、2025年4月からは、対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に延長され、取得事由には「感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式」が追加される予定です。
これらの改正により、より多くのワーママが子の看護休暇を活用しやすくなるでしょう。
2025年4月からの育児・介護休業法改正点

2025年4月1日から、育児・介護休業法が改正され、仕事と育児・介護を両立しやすい環境がさらに整備されます。
この改正は、特にワーママの働き方に大きな影響を与える可能性があります。
主な改正点は以下の通りです。
子の看護等休暇の拡大
これまで小学校就学前までが対象だった子の看護休暇が、小学校3年生修了まで拡大されます。
取得事由も、これまでの病気・けが、予防接種・健康診断に加え、感染症による学級閉鎖や入園・卒園式も対象となります。
また、継続雇用期間6か月未満の労働者でも取得が可能になるなど、より利用しやすくなります。
名称も「子の看護等休暇」に変更されます。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
これまで3歳未満の子を養育する労働者のみが請求できた残業免除が、小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。
これにより、残業を避けたいワーママにとって、より柔軟な働き方が可能になります。
短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加
3歳未満の子を養育する労働者が短時間勤務を利用できない場合に、代替措置としてテレワークが追加されます。
業務の継続性から短時間勤務が難しい職種でも、テレワークを活用することで、柔軟な働き方を選べるようになります。
育児のためのテレワーク導入(努力義務化)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように、事業主が措置を講じることが努力義務となります。
これは、今後テレワークがより普及し、ワーママが働き方を選びやすくなる一歩と言えるでしょう。
介護休暇の取得要件緩和
介護休暇の取得においても、継続雇用期間6か月未満の労働者に対する除外規定が廃止されます。
これにより、入社して間もない従業員でも介護休暇が利用できるようになります。
仕事と育児を両立するための柔軟な働き方の義務化(2025年10月施行)
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者向けに、始業時刻の変更、テレワーク、保育施設の設置運営、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度の5つの措置のうち、2つ以上を選択して実施することが義務付けられます。
労働者はこれらの措置の中から1つを選択して利用できるようになります。
これらの改正は、ワーママが仕事と育児を両立しやすい環境を整備するための重要なステップとなります。
ご自身の会社がこれらの改正にどのように対応しているか、人事担当者に確認することをお勧めします。
ワーママの休みすぎで退職を考える前に
「会社を休みすぎてしまっているから、もう退職した方が良いのではないか」と悩むワーママは少なくありません。
特に、子どもの体調不良が続き、有給休暇も底をついて欠勤が増えてしまうと、職場に迷惑をかけているのではないかという罪悪感や、自身の評価への不安から、そうした考えに至ってしまうことも理解できます。
しかし、安易に退職という選択をする前に、現状を打開するための様々な方法を検討することが大切です。
まず、現状の悩みを一人で抱え込まず、会社の上司や人事担当者、同僚に相談してみることを強くお勧めします。
もしかしたら、会社側もワーママの状況を理解しており、何らかのサポート体制や柔軟な働き方を提案してくれるかもしれません。
例えば、業務内容の見直しや、部署異動、あるいは一時的な業務量の調整などが可能な場合もあります。
次に、前述の通り、育児・介護休業法に基づく「子の看護休暇」や、会社の独自の休暇制度など、利用可能な制度がないか改めて確認してください。
これらを活用することで、有給休暇を温存しつつ、必要な休みを取得できる可能性があります。
また、ご家族、特にパートナーとの役割分担を見直すことも非常に重要です。
子どもの急な発熱時など、どちらが対応するのかを事前に決めておくことで、ワーママ一人に負担が集中するのを避けることができます。
病児保育サービスの利用や、ベビーシッターの活用も、いざという時の助けとなるでしょう。
退職は、キャリアにも経済状況にも大きな影響を与える決断です。
特に、将来的に再就職を考えた場合、ブランク期間が長くなると不利になる可能性も考えられます。
焦って決断するのではなく、利用できる制度やサポートを最大限に活用し、多角的に解決策を探ることが、後悔のない選択につながります。
-

ワーママの土日家事で終わる問題を解決するヒント
続きを見る
ワーママが有給が足りない時の欠勤対処法まとめ

ま と め
- 欠勤は給与減額や評価に影響を与える可能性を理解する
- 有給休暇を使い切った後の欠勤は労働者都合と判断されることが多い
- 傷病手当金や特別休暇など、会社の独自制度を確認する
- 休みすぎの明確な基準はないが、出勤率8割未満が目安になる
- 時短勤務でも有給不足になりやすいことを認識しておく
- 家族や会社と連携し、支援体制を構築することが重要
- 病児保育やベビーシッターの活用も有効な手段の一つ
- 子の看護休暇は小学校就学前の子どもを持つ労働者の権利
- 2025年4月からの育児・介護休業法改正で利用しやすい制度が増える
- テレワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方を検討する
- 自身の体調管理を怠らず、無理をしないことが長期的な鍵
- 退職を考える前に、利用できる制度や相談窓口を活用する
- 就業規則を定期的に確認し、自身の権利と会社の規定を把握する
- 業務内容の見直しや役割分担の調整を会社に相談する
- 困ったときは一人で抱え込まず、積極的に周囲に助けを求める