※当サイトでは、信頼できるサービスに限りプロモーションを実施しております。
共働きで子育てをしていると、まるで共働き子育ては無理ゲーなのではないかと感じてしまう瞬間が多々あるものです。
一体、共働きの子育てで一番大変な時期はいつなのでしょうか。
そして、子育てが楽になるのはいつからなのでしょうか。
共働きの悩みランキングを見ても、多くの家庭が直面する課題が浮き彫りになっています。
共働きで子育てをしていると、共働き子育ての後悔や、共働きで2人目は無理なのではないかという不安を抱えることもあります。
特に共働き子育てで実家が遠い家庭では、サポート体制の不足から共働き子育ての限界を感じることも珍しくありません。
しかし、共働きを辞めてよかったと感じる声がある一方で、無理なく両立するためのヒントも存在します。
この記事では、共働き子育ての現実と、それを乗り越えるための具体的な方法について詳しく解説していきます。
記事のポイント
- 共働き子育ての具体的な大変さとその時期
- 共働き家庭が抱える主な悩みと課題
- 両立の限界を感じたときの対処法
- 負担を軽減し、前向きに子育てをするためのヒント
目次
共働き子育ては無理ゲー?と感じる瞬間の分析

- 共働きの子育てで一番大変な時期はいつ?
- 共働きの悩みランキングから見る実情
- 共働き子育て限界を感じやすい理由
- 共働きで2人目育児は無理かも・・・
- 共働き子育て後悔しないための視点

うちは3人いるから、大変さも3倍だった気がする(笑)
末っ子の学童のお迎えから解放された時、心底ホッとしたもんね。
共働きの子育てで一番大変な時期はいつ?
共働き世帯が子育てで最も大変だと感じる時期は、多くの場合、子どもが乳児期、特に0歳から2歳頃までであると考えられます。
この時期は授乳や夜泣きによって親がまとまった睡眠を取ることが難しく、体力的にも精神的にも大きな負担がかかります。
加えて、頻繁なおむつ交換や離乳食の準備、入浴の介助など、手がかかる作業が多岐にわたるのが特徴です。
保育園に通い始めても、1年目は病気をもらいやすく、月に何度も休まなければならないケースも珍しくありません。
これは突発的な休暇取得につながり、仕事との調整に頭を悩ませる要因となります。
また、子どもの体調不良は親だけでなく、職場にも迷惑をかけてしまうのではないかという精神的なプレッシャーにもつながります。
その後、3歳から5歳頃になると、子どもは少しずつ自分でできることが増え、意思疎通もスムーズになるため、親の負担は軽減される傾向にあります。
しかし、小学校に入学すると、学童保育や長期休み、急な学級閉鎖や学校行事など、新たな時間の制約や調整が必要となります。
これらの「山」を乗り越えるたびに、共働き子育ての大変さを再認識する家庭も少なくありません。
共働きの悩みランキングから見る実情

共働き夫婦の悩みは多岐にわたりますが、調査によると、主に「時間管理」、「家事・育児の負担」、「子どもの体調不良や緊急時の対応」が上位を占めています。
これらの課題は、共働き子育てを「無理ゲー」と感じさせる大きな要因となっています。
1位:時間管理の難しさ
共働き家庭では、夫婦ともに仕事が忙しく、家事や育児、個人の時間の確保に苦労しています。
朝は子どもの支度から送り出し、夜は迎えから寝かしつけまで、分刻みのスケジュールで息つく暇がありません。
これにより自分の時間が取れず、精神的な疲労が蓄積しやすくなります。
子どもの急な体調不良や学校行事などでのスケジュール調整も難しく、大きなストレスとなるでしょう。
2位:家事・育児の負担の偏り
多くの家庭で、家事や育児の負担がどちらか一方に偏りがちです。
特に女性に集中する傾向があり、育児休業からの復帰後に負担が増したと感じる人も少なくありません。
食事の準備、洗濯、掃除に加え、子どもの送迎や病院付き添いなどが一方に偏ることで、身体的・精神的な不満や孤独感を抱きやすくなります。
根本的な解決には、夫婦間の意識と協力が不可欠です。
3位:子どもの体調不良や緊急時の対応
子どもの体調不良や緊急時は、共働き夫婦にとって大きな悩みです。
急な発熱などで仕事を休んだり早退したりする必要が生じ、職場へのプレッシャーを感じることもあります。
実家が遠い家庭では、病児保育やベビーシッターといった預け先の確保が負担となるケースも珍しくありません。
また、平日の学校行事やPTA活動への参加が難しいことも、親の懸念事項です。
これらの悩みは家庭環境で異なりますが、多くの共働き夫婦が直面する共通の課題と言えるでしょう。
夫婦でよく話し合い、お互いを理解し、協力し合うことが、これらの悩みを軽減する鍵となります。
共働き子育て限界を感じやすい理由
共働き子育てで「限界」を感じる瞬間は、時間、お金、心に余裕がない状態が続くと顕著になります。
ワンオペ育児が常態化している家庭では、送迎や食事準備、寝かしつけなどを一人でこなし、心身ともに疲弊しがちです。
パートナーに頼れず「自分ばかり頑張っている」と感じると、孤独感から燃え尽き症候群に陥る可能性もあります。
また、夫婦間で家事や育児の分担が偏っていたり、すれ違いが生じたりすることも大きな要因です。
話し合いがうまくいかず、パートナーの「言われたことしかやらない」姿勢が続くと、孤立感が深まり、諦めの気持ちから限界に達することもあります。
さらに、他の家庭と比較して劣等感を抱くことも一因です。
SNSなどで実家の協力が手厚い家庭や、手がかからない子どもの話を聞くと、「なぜ自分たちだけ」と感じ、疲弊感や無力感が募るかもしれません。
これらの精神的な負担に加え、保育料や教育費などによる経済的な不安も、限界を感じさせる要因となり得ます。
貯金ができず将来への安心感が持てないと、「何のために働いているのか」という疑問に直面し、精神的なゆとりを失ってしまうことがあるでしょう。
共働きで2人目育児は無理かも・・・

共働き家庭にとって、2人目の育児は大きな壁となることがあります。
これは、1人目の育児で経験した時間的、体力的、精神的な負担が倍増する懸念があるためです。
特に、乳幼児期の育児は親の心身に大きな負荷がかかります。
それが2倍になることを想像すると、時間や睡眠の確保がさらに難しくなるのは明らかでしょう。
経済的な側面も懸念材料です。保育料や教育費、生活費は子どもが増えるほど増加します。経済的な理由から2人目は難しいと判断するケースもあります。
また、夫婦間の協力体制も重要です。1人目で分担に偏りがあった場合、2人目ではさらに負担が集中する可能性が高まります。
コミュニケーション不足は関係に亀裂を生じさせる原因にもなりかねません。
しかし、2人目育児で生活が豊かになったと感じる家庭も存在します。
子ども同士で遊ぶことで親の手が空く時間が増えたり、親自身が育児経験を積むことで戸惑いが減ったりする側面もあります。
無理だと感じるかは、家庭の状況やサポート体制、夫婦間の連携によって大きく左右されると言えるでしょう。
共働き子育て後悔しないための視点
共働き子育てで後悔しないためには、いくつかの大切な視点を持つことが重要です。
完璧を目指さず、自分たちに合ったバランスを見つけることが鍵となります。
まず、すべてを完璧にこなそうとすると心身が疲弊してしまいます。
例えば、毎日手作りの食事にこだわらず、お惣菜や外食に頼る日があっても良いでしょう。
子育てで手を抜ける部分は積極的に抜き、心のゆとりを優先してください。
次に、夫婦だけで抱え込まず、積極的に人に頼ることが大切です。
家事代行やベビーシッター、地域のファミリーサポート制度など、利用できるサービスを賢く活用しましょう。
実家が遠くても、外部サービスで負担を軽減できます。
また、他人と比較しないことも重要です。
SNSや周囲の家庭を見て劣等感を抱く必要はありません。
自分の家庭のペースを大切にし、何が一番幸せな選択なのかを基準に考えることで、後悔を減らすことにつながります。
そして、夫婦間の密なコミュニケーションも不可欠です。
忙しい中でも、お互いの状況や気持ちを共有する時間を設けましょう。家事や育児の分担を定期的に見直し、感謝の気持ちを伝え合うことが、夫婦関係を良好に保ち、協力を促します。
これらの視点を持つことで、共働き子育てにおける「無理ゲー」感を軽減し、後悔なく子どもの成長を見守り、生活を楽しむことができるでしょう。
-
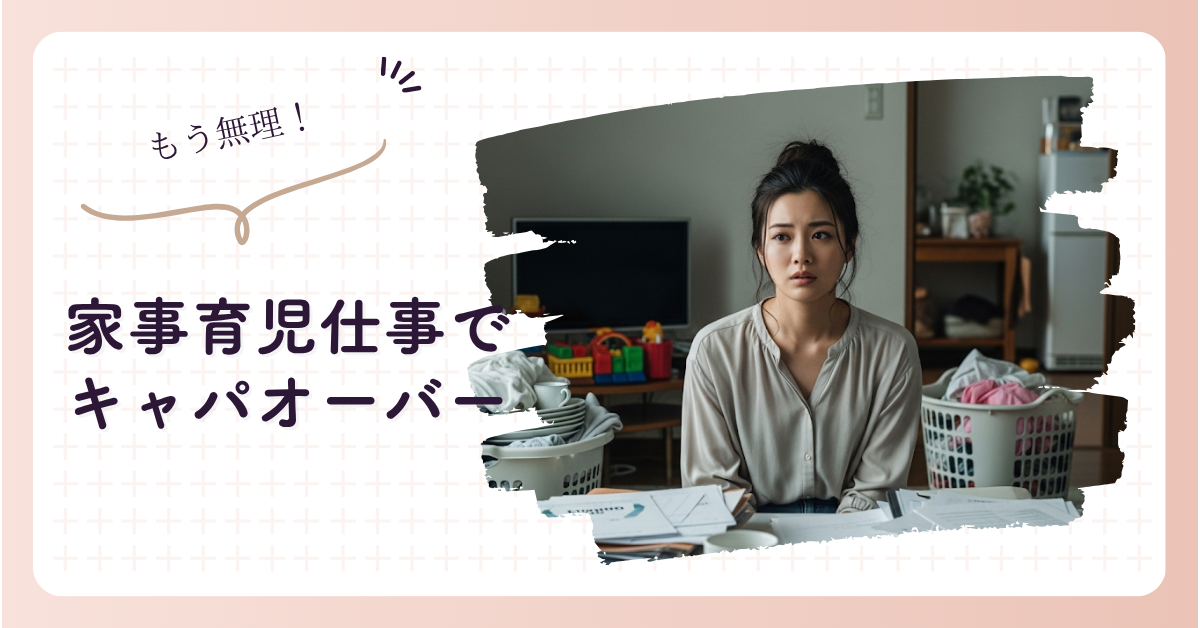
家事育児仕事でキャパオーバー!もう無理と感じたら
続きを見る
共働き子育て無理ゲー状態を乗り越える対策とヒント

- 子育てが楽になるのはいつ?変化を理解する
- 共働き子育て実家が遠い家庭の課題と解決策
- 共働きを辞めてよかったと感じる瞬間
- 夫婦で協力するための仕組みづくり
- 外部サービスを活用する重要性
- 共働き子育て無理ゲー状態を改善する視点

こっちがイライラする前に「これやってくれると助かる!」って具体的に言うようにしたら、結構動いてくれるようになったかな。
まぁ、今でも時々「それじゃない!」ってなるけど、そこはご愛嬌ってことで!
子育てが楽になるのはいつ?変化を理解する
子育てが「楽になった」と感じる時期は、子どもの成長段階によって変化します。
一般的には、子どもが成長し、できることが増えるにつれて親の負担は軽減される傾向にあると言えるでしょう。
この変化を理解することは、共働き子育ての長期的な見通しを立てる上で役立ちます。
具体的には、3歳頃になると、子どもは言葉を理解し、意思疎通がスムーズになります。
トイレトレーニングが完了するとおむつ替えの手間がなくなり、また、ある程度自分でできることが増えるため、親が常につきっきりで世話をする必要が減ります。
小学校に入学する低学年頃になると、生活リズムが整い、自分で身支度や準備ができるようになります。
さらに、友達と遊ぶ時間が増えることで、親と離れて過ごす時間が増えるのもこの時期の特徴です。
これにより、親は自分の時間や仕事に充てる時間を確保しやすくなります。
そして、小学校高学年になると、子どもは自分で考え、行動できるようになる力が一段と伸びます。
習い事や部活動などで活動範囲が広がり、親の手を離れる時間も増えるため、親はより多くの自分の時間を持つことができるようになるものです。
| 子どもの年齢 | 親が楽になると感じる主な理由 |
|---|---|
| 0〜2歳頃 | 手がかかることが多い時期 |
| 3歳頃 | 意思疎通がスムーズになる |
| 小学校低学年 | 生活リズムが整い身支度も自分で可能 |
| 小学校高学年 | 自分で考え行動できるようになる |
もちろん、これはあくまで一般的な傾向であり、子どもの個性や発達状況、家庭環境によって楽になる時期は異なります。
夜泣きが長引く場合や、手のかかる子どもを育てている場合は、もう少し時間がかかることも考えられます。
しかし、子どもの成長とともに子育ての形は変化し、徐々に親の負担が軽減されていく過程があることを知っておくことは、精神的な支えとなるでしょう。
共働き子育て実家が遠い家庭の課題と解決策

共働き家庭で実家が遠いと、子どもの急な体調不良や長期休暇の預け先など、夫婦二人の負担が集中しやすくなります。
突発的なトラブルへの対応
実家が近ければ祖父母に頼れますが、遠いとそれができません。
夫婦どちらかが仕事を休む必要が生じ、キャリアに影響が出る可能性もあります。解決策として、病児保育サービスの活用やリモートワークの利用がおすすめです。
夫婦で勤務調整し、交代で対応することも大切です。
長期休暇の預け先問題
夏休みや冬休みといった長期休暇は、実家が遠いと預け先に困る大きな悩みです。
学童保育や民間の習い事、サマースクールなどを活用しましょう。
夫婦で有給を交互に取り、ファミリーサポート制度の利用も検討してください。
精神的な負担の軽減
実家が遠いと相談相手が限られ、孤独感から精神的な負担が増大することもあります。
地域のママ友・パパ友を作ったり、SNSのオンラインコミュニティを活用したりしましょう。
何よりも、夫婦間の密なコミュニケーションを大切にし、お互いの悩みやストレスを共有し、協力し合うことが精神的な支えとなります。
実家からのサポートが得られない分、外部サービスや地域のつながりを積極的に活用し、夫婦で協力しながら子育てを乗り越えることが重要です。
共働きを辞めてよかったと感じる瞬間
共働き子育てが「無理ゲー」と感じた後、仕事を辞める選択をする人もいます。
これは主に、仕事から解放されることで得られる時間的・精神的なゆとりによるものです。
まず、時間に余裕が生まれることで、子どもの体調不良や学校行事など、急な事態にも焦らず対応できるようになります。
仕事によるプレッシャーから解放され、子どもとの時間を十分に確保し、成長を丁寧に感じられるようになるのは大きな喜びです。
精神的なゆとりも大きなメリットです。共働き子育ての多くのストレス要因から解放され、心に平穏が戻ることを実感する人は少なくありません。
ストレス性の体調不良が改善されることもあります。
また、家庭内の雰囲気が改善されることも理由の一つです。
夫婦間の家事・育児分担の偏りによる衝突が減り、ゆとりを持って接することで夫婦関係が円滑になります。
子どもにも笑顔で接する時間が増え、親子の絆が深まるでしょう。
経済的な不安が生じる可能性はありますが、それ以上に得られる精神的な安定や家族と過ごす時間の豊かさが、仕事を辞める選択を正当化する大きな理由となるのです。
この決断は各家庭の状況によりますが、自身の健康や家族の時間を優先した結果、後悔のない選択だったと捉えるケースは多く見られます。
夫婦で協力するための仕組みづくり

共働き子育てを円滑に進めるには、夫婦間の協力が不可欠です。
漠然と「協力しよう」と考えるのではなく、具体的な「仕組み」作りが重要になります。
家事・育児のタスク可視化
まず、家事や育児のタスクを可視化しましょう。
お互いの担当が不明確だと不公平感が生まれやすいため、一週間のリストを作成し、担当を書き出すと良いでしょう。
これにより、タスクの偏りに気づき、公平な分担について話し合うきっかけとなります。
次に、予定を共有する仕組みも有効です。
共有カレンダーアプリなどを活用し、子どもの行事や夫婦の仕事スケジュールを共有することで、急な事態にもスムーズに対応できます。
これは負担の集中を防ぎ、お互いへの理解を深めることにもつながるでしょう。
ルーティンの見直しと効率化
日々のルーティンを見直し、効率化を図ることも効果的です。
朝の支度や夜の食事準備など、定型的な作業の動線や手順を夫婦で確認し、無駄がないか話し合ってみましょう。
例えば、前夜の準備や時短家電の導入は、日々の負担を大きく軽減してくれます。
食洗機やロボット掃除機、洗濯乾燥機などは、家事時間を大幅に削減し、夫婦のゆとりと時間創出に貢献する可能性があります。
コミュニケーションの質向上
前述の通り、夫婦間のコミュニケーション不足は大きな課題です。
忙しい中でも定期的に「夫婦会議」の時間を設け、家事・育児分担だけでなく、仕事やストレス、将来の計画などを率直に話し合いましょう。
お互いの頑張りを認め、感謝を伝え合うことも大切です。
こうした仕組み作りを通じて、夫婦が当事者意識を持って子育て・家事に取り組むことが、共働き子育てを無理なく続ける鍵となります。
外部サービスを活用する重要性
共働き子育ての負担を軽減し、「無理ゲー」状態を打破するには、夫婦だけで抱え込まず、外部サービスの活用が非常に重要です。
サービスを借りることで、心身にゆとりが生まれ、家族で笑顔で過ごせる時間が増える可能性があります。
家事代行サービスの活用
家事代行サービスは、共働き家庭の大きな助けとなります。
例えば、週末の掃除を依頼すれば、夫婦は休息や子どもとの時間に充てられます。
水回りや大掃除など部分的な利用も可能です。
身体的・精神的負担が軽減され、心にゆとりが生まれるでしょう。
ベビーシッターや病児保育の利用
子どもの預け先として、ベビーシッターや病児保育の活用も有効です。
急な仕事や外出時、あるいは子どもが体調を崩した際など、頼れる人がいない場合に心強い存在です。
特に病児保育は、専門スタッフが病気の子どもを預かるため、安心して仕事に集中できます。
自治体の助成制度も確認してみましょう。
ファミリーサポート制度の利用
地域の住民同士が子育てを助け合う「ファミリーサポートセンター」も有益な制度です。
保育園の送迎や一時預かりなど、必要な時にピンポイントでサポートを受けられます。
比較的安価で、地域に根ざした支援が特徴です。
食事関連サービスの利用
毎日の食事準備は共働き家庭にとって大きな負担です。
ミールキットや食材宅配サービス、冷凍弁当などの活用を検討しましょう。
これらを利用すれば、買い物や献立、調理時間を大幅に短縮できます。
たまには外食やテイクアウトに頼るのも、無理なく続ける工夫です。
これらの外部サービスには費用がかかるというデメリットもありますが、それによって得られる時間や心のゆとりは計り知れない価値があります。
無理を続ける前に、利用できるサービスがないか調べてみることが、共働き子育て継続の鍵となるでしょう。
共働き子育て無理ゲー状態を改善する視点

共働き子育てが「無理ゲー」だと感じる状態を改善するには、多角的なアプローチが大切です。
夫婦の意識改革だけでなく、社会的なサポートや制度の活用も視野に入れることが、持続可能な子育てにつながります。
完璧主義からの脱却
まず、完璧主義を手放すことが最も重要です。
家事も育児もすべて完璧にこなそうとすると心身が疲弊してしまいます。
市販品や外食を上手に取り入れ、家事の負担を減らすことも有効です。
部屋の整理整頓も、衛生面が保たれていれば問題ないと割り切り、心のゆとりを生みましょう。
経済的な計画の見直し
共働きでも経済的な余裕を感じにくい家庭は少なくありません。
家計全体を見直し、固定費の削減を検討しましょう。
児童手当や自治体の子育て支援制度など、公的なサポートを最大限に活用することも有効です。
将来の資金計画については、専門家に相談し、漠然とした不安を解消することもおすすめです。
職場環境と働き方の見直し
現在の職場環境が共働き子育てに適しているか見直すことも重要です。
時短勤務やフレックスタイム制、リモートワークなど、柔軟な働き方が可能な職場であれば、子どもの急な体調不良や学校行事にも対応しやすくなります。
もし現在の職場でこれらの制度活用が難しい場合、転職を検討することも、長期的な視点で見れば家族の生活の質を高める選択肢となり得ます。
子育てしやすい住環境の選択
住んでいる地域の特性も共働き子育ての負担に大きく影響します。
保育園の数や待機児童の状況、子育て支援施設の充実度、職場へのアクセスなどを考慮して住む場所を選びましょう。
病児保育施設や休日も利用できる子ども向けの施設が近くにあるかなど、自分たちのライフスタイルに合った環境を選ぶことが日々のストレスを大きく軽減する要素となります。
これらの多角的な視点からアプローチし、自分たちに合った工夫や仕組みを取り入れることで、共働き子育ての「無理ゲー」状態を改善し、より快適で豊かな生活を送ることができるようになるでしょう。
-

共働きで2人目は無理?諦める前に知るべき7つの対策
続きを見る
共働き子育ては無理ゲー?乗り越えるためのポイント

ま と め
- 共働きの子育ては時に困難を感じることがあります
- 子どもの乳児期は特に身体的・精神的な負担が大きくなりがちです
- 時間管理は共働き夫婦の最大の悩みの一つです
- 家事や育児の負担が一方に偏ることで不満が生じます
- 子どもの体調不良や緊急時の対応は常に課題となります
- 夫婦間のコミュニケーション不足も悩みの原因となります
- ワンオペ育児や経済的不安が重なると限界を感じやすくなります
- 他の家庭との比較は劣等感や孤独感を招くことがあります
- 2人目育児はさらに負担が増すとの懸念を抱く夫婦もいます
- 子育ては子どもの成長とともに徐々に楽になる傾向にあります
- 完璧を目指さず手を抜けるところは抜く意識が大切です
- 病児保育や家事代行など外部サービスを積極的に活用しましょう
- 夫婦で家事・育児のタスクを可視化し協力体制を築きましょう
- 時短家電の導入や食事の準備の簡略化で時間を生み出せます
- 経済的な計画の見直しや公的支援の活用も重要です
- 職場環境の見直しや柔軟な働き方を検討することも有効です
- 自分たちに合ったペースを見つけることが後悔しない鍵となります

